<後編>苦手なものほど、よく観察できる。言語哲学者・三木那由他さんに聞く、人見知りが会話を研究する理由
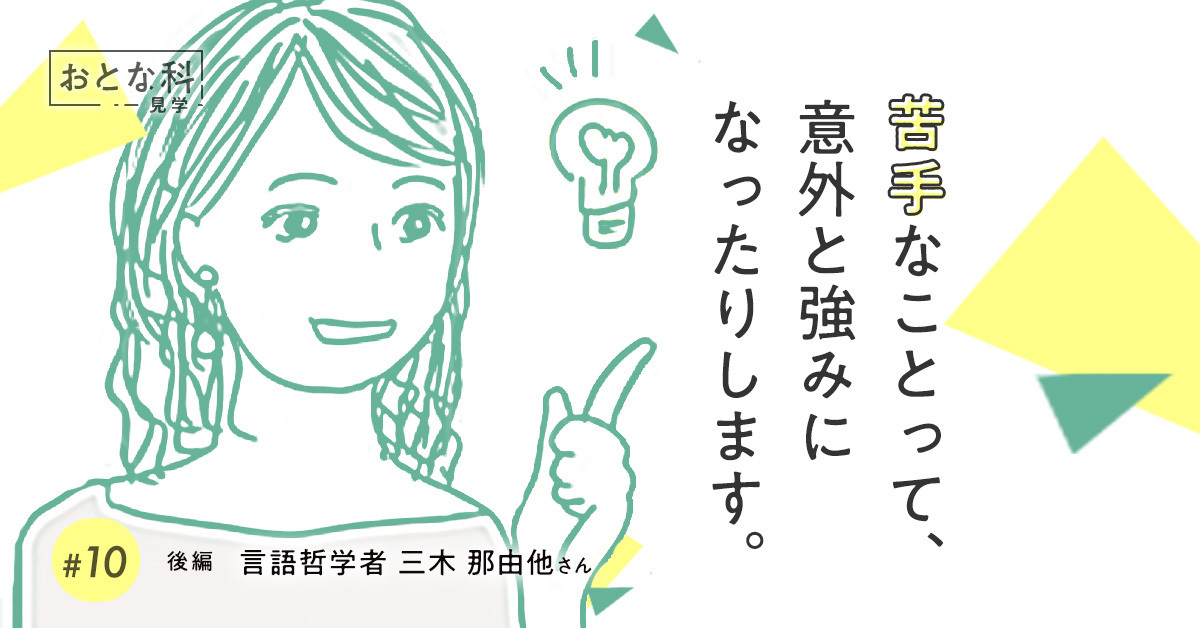
プロフィール

三木 那由他(みき・なゆた)さん
大阪大学大学院講師。専門は分析哲学、特にコミュニケーションと言語の哲学。著書に 『話し手の意味の心理性と公共性』(勁草書房、2019年)、 『グライス 理性の哲学』(勁草書房、2022年)、 『言葉の展望台』(講談社、2022年)、 『会話を哲学する』(光文社新書、2022年)がある。文芸誌『群像』とウェブメディアRe: Ronで連載中。大学院への出願も歓迎しています。 https://researchmap.jp/nayutamiki
Q3.なぜ「会話」を研究テーマにしたんですか?
A. 苦手だったからこそ、人一倍、会話について考えてきたからです。
ここまでお話ししてきたように、私は「会話」について研究しています。でも、白状すると、私自身はおしゃべりが大の苦手です。
小さいころから人と会うこと自体が得意ではなかったそうで、物心つく前に「公園デビュー」に連れて行かれたときですら、親の足にしがみついて意地でも砂場へ着陸しなかった…。それほど筋金入りだったそうです(笑)。

そんな人が、なぜ会話やコミュニケーションを研究テーマにしているのか。不思議に思われるかもしれません。
これには背景があって、やっぱり得意な人って自然とできてしまうから、会話するのもあたりまえで、あんまり観察するきっかけがないと思うんですけど、私は苦手だからこそ、よく観察している。苦手だからこそ、人一倍考えてきたことが研究につながっているのだと思います。
たとえば私は、飲み会の帰り道には「何かヘンなことを言ってしまった気がする」とばかり、悶々と考えてしまいます。もしこれが会話が得意で大好きな人だったら、自然に楽しくこなせてしまうから、会話自体をあとから思い返すこともあまりないんじゃないでしょうか。
苦手だからこそ、コミュニケーションについて、反省や反芻をする機会が多くなるのです。
苦手なことについて、なぜうまくいかないんだろう? どうしたらいいんだろう? と考える機会が多い。だから、自然と、そのことについて考えや知見がたまっていくんだと思います。

また、世の中には、自分と同じ苦手を持つ人もたくさんいるはずです。実際、私のように、コミュニケーションがとことん苦手という人はたくさんいらっしゃいますよね。
だから、苦手分野を持っていることで、同じ苦手を持つ人に共感できるし、単に共感するだけでなく、「私がじっくり観察してきたら、こういうことが見えてきたよ」ということを語っていくことができます。
それって同じ苦手を持つ人にとっては役に立つだろうし、場合によっては、普段それを苦手に思っていない、スムーズにやれている人にとっても、何か活かしてもらう機会になることもあると思います。
こうして考えてみると、その対象のことを苦手な人のほうが、案外、適切な対処法や意外な視点、広く使えるような新しい知識を見出しやすいのかもしれません。
だから、みなさんも苦手なことがあってもきっと大丈夫。苦手なことって、意外と強みになったりします。

<前編>はこちら
<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:山内 宏泰
漫画:あい茶





