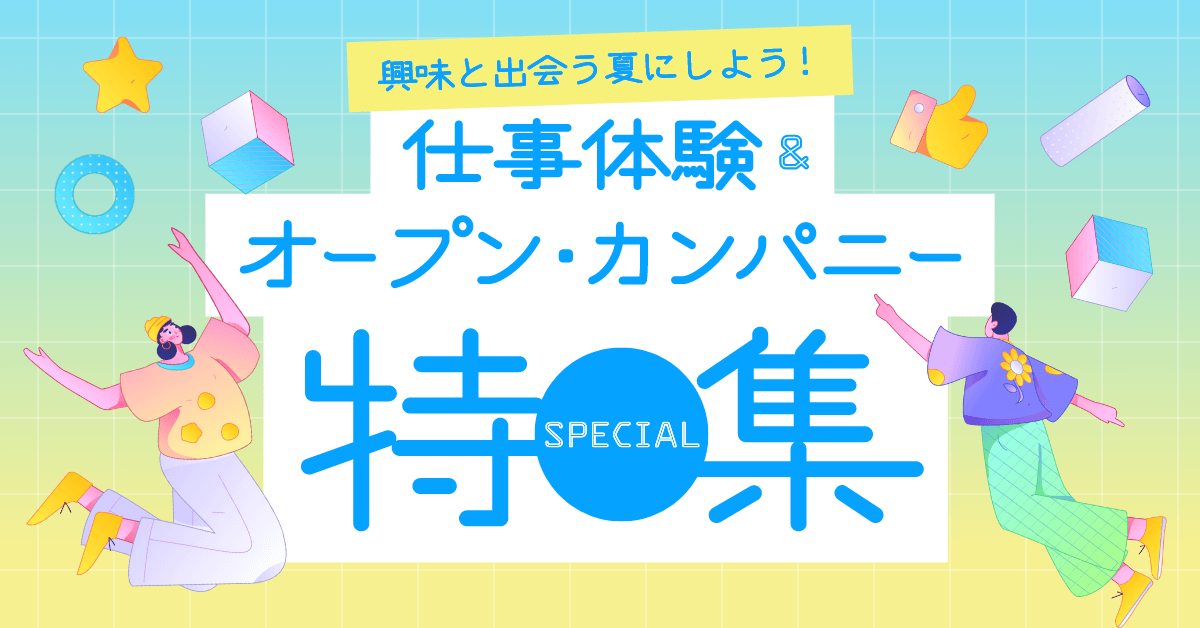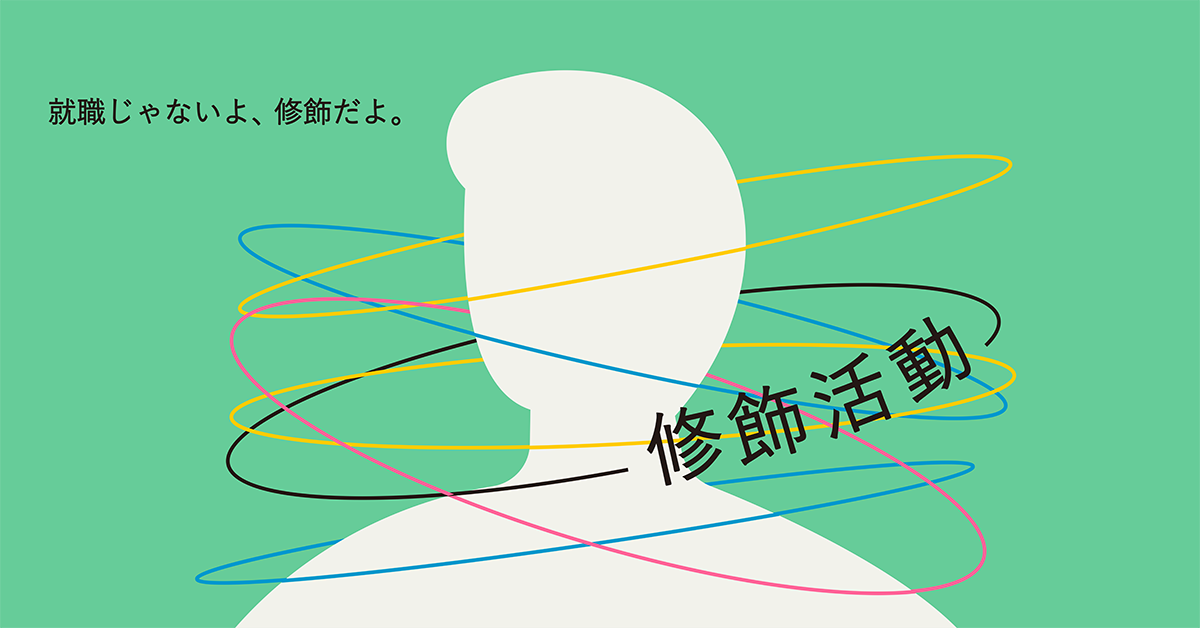<中編>一人一人を観察するから、かけるべき適切な言葉が見つかる。声がけは選手に合わせて。東洋大学 陸上競技部・酒井俊幸監督に聞く、言葉の選択
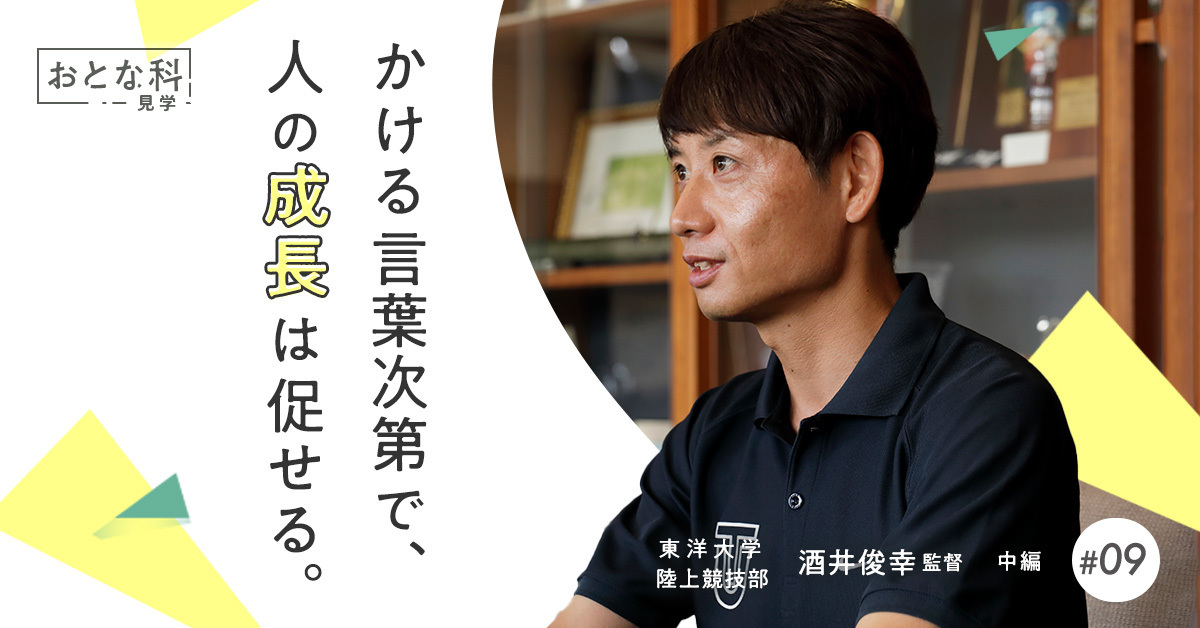
強いチームに必要なのは、チームの哲学に「言葉」を与えること。そして、そのわかりやすく短い「言葉」を反復すること。「その1秒をけずりだせ」というスローガンと、2023年度のチームに掲げた4つのフレーズは、選手の集まりを「チーム」としてまとめあげるものです。
中編では、チームに掲げる言葉ではなく、選手、一人ひとりにかける「言葉」の選択について、酒井監督に聞いてみましょう。
>前編はこちら
プロフィール

酒井 俊幸(さかい・としゆき)さん
東洋大学陸上競技部(長距離部門)監督。 1999年東洋大学経済学部経済学科卒。 東洋大学陸上競技部キャプテンを経て、コニカ(現・コニカミノルタ)に入社。 引退後は、母校である学校法人石川高等学校にて教員として陸上部顧問を務めた。 2009年より東洋大学陸上競技部長距離部門の監督に就任。箱根駅伝、全日本大学駅伝、出雲駅伝などでチームを数々の優勝に導く。世界レベルで活躍する選手たちを多数育成。
Q2.言葉だけで、人は成長できるものですか?
A.人の成長を促すのも止めるのも、かける言葉次第です。
人の心に訴え、行動を変え、成長させるのに必要なのが「言葉」です。指導者の影響力が大きいからこそ、その人に合った言葉を、タイミングよくかけなくてはいけません。
では、各々に対する適切な言葉は、どう見つければいいのか。
それは、相手をつぶさに観察することに尽きます。練習やレースのときだけでなく、普段の生活から些細なところにまで目を配り、それぞれの性格やコンディションを見抜く努力が、指導者には必要です。

箱根駅伝のレース内にも、言葉の重要性が垣間見える場面があります。各チームの監督はレース時、運営管理車に乗って走っている選手の後方につきます。各区間で何度か、車内からマイクで選手に声をかけることができますが、1回1分以内と時間が限られています。
そのあいだに、ペース、順位、前後との距離やタイム差など必要な情報を伝えたうえで、選手の力になる言葉を投げ込まなければいけないので大変です。
その言葉選びは、選手によって明確に使い分ける必要があります。
その選手は、「後ろとの差が詰まってきたぞ」など、適度なプレッシャーを与える声がけをして、反発力と爆発力を期待する「鼓舞型」なのか。それとも、後ろ向きな情報は与えずに「いいペースだ、このままいけばいい」と励ますほうが力を出し切れる「安心型」か。

選手にはどちらのタイプもいるので、しっかり見極めなければいけない。そして、指導者としては「鼓舞型」と「安心型」、どちらの声がけもうまくこなせなければいけません。そのあたりはこちらの演技力が試される部分です。
実際の声がけの例を、さらに挙げてみましょう。
2022年8月に開かれた北海道マラソンに、東洋大陸上競技部の3名の選手が挑戦し、当時4年生の柏優吾選手が日本人トップの2位という好結果を残しました。
柏選手はとにかく真面目に陸上競技に打ち込んでいるのに、なかなか結果が表れないタイプでした。本番になると、緊張から力を出し切れないことが多いのです。
でも、そういう選手にこそ結果をだしてほしいじゃないですか。指導者としてこの子の花を咲かせないといけないな、と思っていました。

そこで、さまざまな想定外を想定内に入れないといけない駅伝ではなく、敢えて、初マラソンに挑戦してもらいました。マラソンは30kmまでペースメーカーがいるので、選手はストレスレスで走れるんですよね。
マラソン前には、「俺は喫茶店でソフトクリームでも食べながら、テレビを見て待ってるよ。完走だけしてきなさい」とだけ言って、柏選手を送り出しました。できるだけストレスのない、無欲な状態で彼を走らせたかったんです。
すると見事に結果が出て、その後の柏選手は、駅伝でもマラソンでも、吹っ切れたパフォーマンスを見せるようになりました。
ひとつ自信をつけると、人はこれほど伸びるものかと感嘆しました。

<前編>はこちら
<後編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:山内 宏泰
漫画:まるいがんも
撮影:菊田 香太郎