<前編>いま、社会に対して貢献ができるという感覚を取り戻す必要があります。投資家・藤野英人さんに聞く、「働くこと」の捉え方
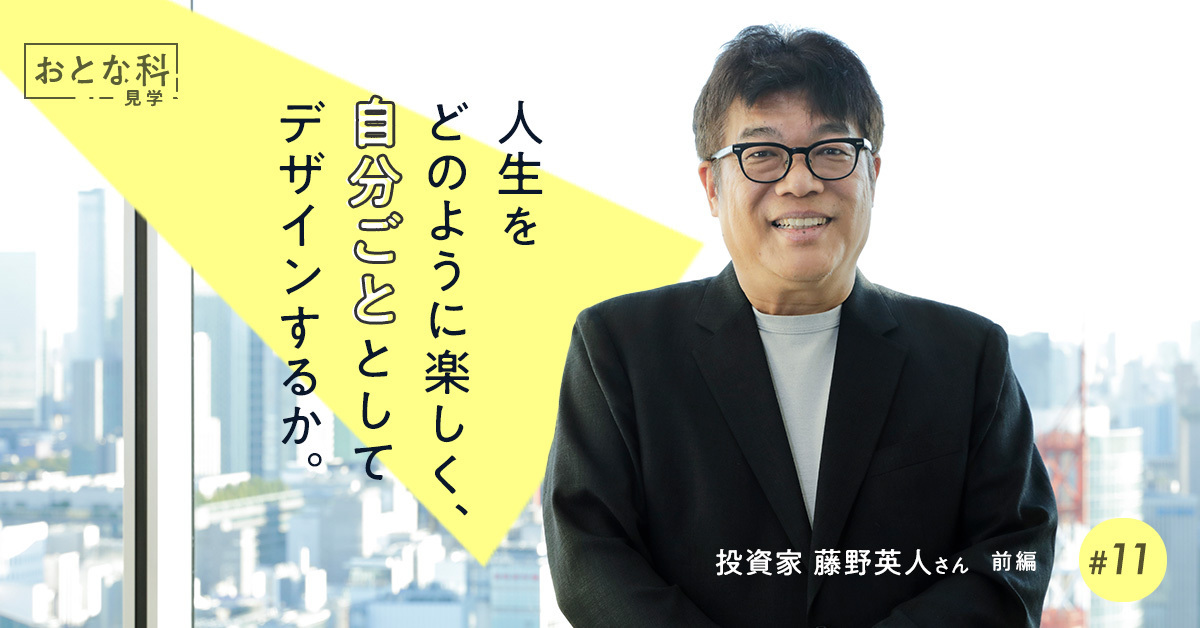
仕事に前向きなイメージが持てず、「社会に出て働く」と考えると、なんだか憂鬱な気持ちになってしまう人はいませんか? でも「働くこと」って、じつは楽しいものだと思うのです。
藤野さんは、「受動的な考えから脱すること」が、仕事を楽しむためのヒントだと言います。それってどういうことでしょう? 藤野さんに聞いてみましょう。
プロフィール

藤野 英人(ふじの・ひでと)さん
レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役会長兼社長・最高投資責任者。1966年富山県生まれ。国内・外資大手資産運用会社でファンドマネージャーを歴任後、2003年レオス・キャピタルワークス創業。主に日本の成長企業に投資する株式投資信託「ひふみ投信」シリーズを運用。著書に 『投資家が「お金」よりも大切にしていること』、 『投資家がパパとママに伝えたい たいせつなお金のはなし』など。
Q1.働くことを前向きに捉えるためには、どうすればいいですか?
A.「自分は受動的な存在である」という考え方から抜け出しましょう。今は、生き方の幅が広がっています。自分次第で道が切り開ける、おもしろい時代なんですよ。

働くことを前向きに捉えられない人は、まだまだ日本に多いですよね。仕事を「ストレスと時間をお金に変えるもの」だと思ってしまっている。そういう人は、会社のことを「学校」の延長線上にあるもののように捉えているのだと思います。
毎日行かなければいけない場所、縛られる場所、強制される場所。我慢して働いて、我慢料が給料としてもらえる場所…。長い労働人生でこのような考え方を持ってしまうと、きっと人生は楽しくないし、おもしろくなりません。

会社という言葉は、英語で「カンパニー」ですよね。じつは、カンパニーとは、「仲間」という意味を持つ単語です。ともに働く仲間とビジョンや思いを同じくして、商品やサービスを生み出すおもしろさやたのしさがある場所。それが会社なのです。
もし働くことや会社に後ろ向きなイメージを持っている人がいたら、まず「自分は受動的な存在である」という考え方から抜け出すことが大事です。
みなさんの多くはこれまで、「自分は社会を変えうる存在だ」という教育を受けてこなかったかもしれません。だから働くことを受動的なものだと思ってしまう。でも、そんなことはありません。
自分は価値ある人間であり、社会に対して貢献ができるという感覚を取り戻す必要があります。
いまの高校生たちを見ていると、すこしずつですが着実に、教育が変わって、学生たちのマインドも変化してきていると感じます。これはおそらく、SDGs教育の賜物です。
SDGsは、貧困・環境・ジェンダーなど、17のジャンルでそれぞれ開発目標を掲げています。その17個の具体目標を前に「あなたはどの分野で社会を変えたいですか?」と問う教育が行われ始めている。そうすると、自分が向き合う課題が明確になり、「社会を変えよう」という意識を持ちやすくなるのです。

教育に加え、近年、会社も変わってきています。「健康経営」や「人的資本経営」という言葉が出てきたり、ダイバーシティに目が向けられるようになって、ひとりひとりの労働者の人生や価値観が大切にされるようになってきました。
そこに人手不足の背景も加わり、労働者からすると、起業や転職のチャンスが増えている。じつは、いまは、生き方の幅がどんどん広がっているおもしろい時代なんですね。
「人生をどのように楽しく、自分ごととしてデザインするか」は、とても大事な視点です。それが実現できる社会になってきているのに、目先の年収で会社を選ぶような古い価値観に従ってしまうのはもったいないですよね。
人生には想定外なこともたくさん起きると思いますが、失望したくないから安定思考になってしまう「失望最小化」ではなく、人生に希望を持ち、おもしろがっていく「希望最大化」で生きることができれば、きっと働くことに対してのイメージも前向きなものになるはずです。
受動的な姿勢から脱し、自ら人生を切り開いていきましょう。

<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:あかしゆか
漫画:水縞アヤ
撮影:菊田 香太郎



