
- トップ
- 特集
- 日本経済新聞連動特集
- 新卒採用広告特集
- 学生座談会 就活中の進化が成功の道 会社には「温度感」共有を期待
学生座談会
就活中の進化が成功の道
会社には「温度感」
共有を期待
終身雇用を前提にしない働き方が広がる中、天職とどう巡り合うか。日本経済新聞社は希望職種への就職を決め、2025年春から社会人となる大学生5人の座談会を開催、それぞれの思いを語ってもらった。そこからは、就活中も〝進化〞を続けて内定を決めた道のりが見えてくると同時に、必ずしも転職ありきでなく、むしろ会社やその上司、同僚との間で働く姿勢や熱量、いわば「温度感」を共有して勤続したいと願う本音が浮き彫りになった。
PROFILE

Aさん
共立女子大学文芸学部。金融業界で働く父親の影響で同業界に興味を持ち、その後リース業界に志望を絞り込み、内定。

Bさん
慶応義塾大学文学部。環境問題に取り組むNPOへの参加を経て、都市開発での課題解決に関心を持つ。鉄道・不動産業界に内定。

Cさん
共立女子大学文芸学部。化粧品メーカー志望だったが、人を助ける仕事に就きたい、と志望を変更。生命保険業界に内定を決める。
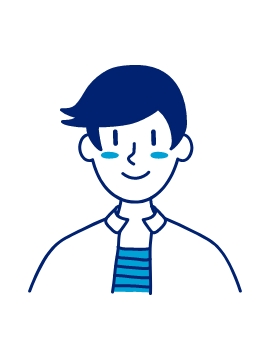
Dさん
中央大学文学部。業界を絞らず、海外駐在が可能な企業を中心に就活を行う。商材がある企業に強みを感じ、自動車メーカーに内定。

Eさん
慶応義塾大学経済学部。就活中に同僚と協力して成果を出す社風に引かれ、志望先を商社に絞る。電設資材を扱う専門商社に内定。
OB・OG訪問「35人」
自身の就活で意識した点、苦労した点は何でしたか?
Aさん:3年生の夏ごろからインターンシップ&キャリアに参加して、4年生から本格的に就職活動を開始。始めるのが少し遅かったから、ES(エントリーシート)の作成や適性検査の勉強で、1日6時間費やすこともありました。私は面接に苦手意識があったので、よく聞かれる質問をネットの情報などを参考に50個ほど洗い出し、一つひとつに模範解答を作って備えたり、母に面接練習をお願いしたりしました。
Bさん:父と同じ業界を志望していたので、専門的な疑問などをよく相談していました。面接練習は、鏡に向かって質疑応答を繰り返したほか、SNSで同じ業界志望の人を見つけ、お互いにビデオ会議ツールで模擬面接にも参加しました。
Cさん:私の場合、母と兄に協力してもらって、1対2の面接練習を行いました。ESやガクチカのことなどは家族も含め、周りの人に素直に相談できたのですが、ESがなかなかパスできなかった時期もありました。自分でも言語化できないモヤモヤした悩みも結構あって。人に話すにはまとまりがなくてちょっと……といったときは、AIを使いました。考えていることをとりあえず入力して、AIを使って清書して、自分の思考を整理するイメージです。
インターンシップ&キャリアやOB・OG訪問は積極的に行ったのですか?
Dさん:インターンシップ&キャリアは志望業界を決める一つの要因となりました。当初、自分は海外で働けるかを重視していて、夏には業界を問わず10社以上のインターンシップ&キャリアに参加しました。とくに商社が多かったのですが、インターンシップ&キャリアを通じて、海外で活躍するには名刺代わりとなる自社商品の存在が重要と考え、冬インターンシップ&キャリアからは志望をメーカーに絞りました。
Bさん:私は違ったのですが、友人の志望業界などでは、インターンシップが本選考に直結することもあったようで、重要視していましたね。私の場合は志望業界がOB・OG訪問の回数を重視する傾向だったこともあり、1社につき5人は行うなど、積極的に申し込んでいました。ただ、突然連絡すると断られることもあったので、マッチングサービスや、一度に大勢の話を聞ける座談会も活用しました。
Eさん:自分もOB・OG訪問の依頼には苦労し、後半からは訪問先の人に紹介してもらえるよう、行動しました。最初にお伺いできた人と交流を深める中で人脈を広げていき、最終的に35人くらいに訪問できたと思います。
ES、広さより深さ
ESが色々な会社で通り始めたきっかけは?
Eさん:広さより深さを重視した内容にしてから、ESの通過率が上がった気がします。当初はガクチカとして、野球サークルの関東大会でベスト8に進出したことなどを重点的に取りあげていました。ですが、友人に「この内容、お前じゃなくてもよくない?」と言われてしまって。結果だけでなく、その過程で自分が何を工夫したかまで語らなくては、自分を知ってもらうには不十分だと気づいたんです。練習の参加率を増やすためにどう呼びかけたか、一人ひとりとの会話の内容まで掘り下げるようにしたら、次の選考に進めるようになりました。
Dさん:自分は幼少から続けているクラシックバレエでの実績をESに書いていました。ES自体の通過率はよかったのですが、競技の珍しさから、面接で聞かれるのは大会の仕組みやルールのことが大半で、聞いてほしいこと、言いたいことを残したまま終わる面接が多かったです。面接を見越し、自分の内面を伝えられる内容にしなくてはいけないと思いました。その後、同じ大会の出来事でも、練習体制を改善した過程や集団でのリーダーシップなど、職場での自分を連想できる内容に焦点を当て直したことで、手応えを感じる面接は増えていきました。
それ、面接で言う?
面接が成功したポイントは何だったのでしょう?
Aさん:企業の社風にあった自分をアピールできたことだと思います。私が志望していたリース業界は相手に寄り添い、適切なサービスを提供する仕事です。誰かのことを考えるのは、自分のキャラクターにも合っていると思えたので、自信を持って面接に臨めたのが結果につながりました。
Eさん:「それ、面接で言っちゃっていいの?」というところまで、思い切って伝えられたことがよかったと思っています。ある企業の面接で、飲み会の頻度を聞かれたんです。周囲と比べると多いほうだと思っており、不真面目な印象を与えてしまうかと不安になりましたが、正直に答えたら「営業に向いているね」と。好意的に受け取ってもらえたのか、内定まで進むことができました。
Cさん:成功のポイントとはちょっと違うかもしれないのですが、たくさん質問してもらえて、面接官の人も笑って受け答えしてくれた面接は内定をいただけることが多かったです。やっぱり、面接は自己アピールしてこそだと感じています。
自分を取り繕って内定をもらったとしても、その企業で自分らしく働くのは難しいのではないかと思います。自分がどれだけその企業に勤めたいか積極的にアピールし、自分の性格や希望するキャリアも包み隠さず伝える。ありのままの自分を受け入れてくれる企業で働きたいと思いますし、本心を言語化しているうちに、自分の強みや就活軸もより明確になりました。

就職活動を終え入社先を決めた今、自身の就活について振り返り、語り合った。
勤続・転職両にらみ
内定をもらった会社で長く働いていく自信はありますか?
Bさん:友人には同じ会社で勤める自信がない、という人もいて、確かに転職を前提に就職先を選ぶ学生も少なくない印象はあります。でも私自身は長く勤め上げるつもりでいます。就職を決めた会社は福利厚生が充実していてライフプランも考えやすく、働き続けるイメージをはっきり持てました。知名度も高くて、両親がとても喜んでくれた、ということも決断を後押しした面があったように思います。
もっとも、転職を全く考えていないわけではなくて、将来は転職することもあるかもしれない、ということは考えています。どちらの選択肢も持っておきたい。だからこそ、長く働けて、かつ、早くから様々な経験を積める会社ということで選んだということだと思っています。
Dさん:複数の会社から内定をいただきましたが、比較した時、やはり会社ごとの「特色」というものがあると感じました。その中で最も自分の希望に近い企業を選んだつもりです。もし将来、思い描いた海外での働き方ができない、というふうに感じられたら、転職も検討すると思います。ただ、その時に自分が転職市場で競争力がない、ということにならないようにしないと。そのためには前職の経験を生かすのが一番の近道だと考えているので、まずは確実にスキルを磨いていくつもりです。
キャリア、先輩も参考
就職先で悩んだ時はどうすればいいんでしょう
Aさん:私は内定者懇親会が決め手になりました。2社から内々定をもらっていて、4年生の8月後半まで、どちらを選ぶかで悩んでいたんです。そんな中、懇親会が開催されたので、決断のヒントになるかも、と足を運んでみると、職場の雰囲気や給与など待遇や忙しさの度合といったリアルな話を聞けました。そのおかげで行きたいと思える会社を選べたと感じています。
Cさん:私は懇親会で「仕事はどれくらい忙しいですか?」「産育休からの復職率は?」など、気になっていた点を先輩社員にぶつけてみました。採用面接でも同じ質問をして、それなりに答えを聞いてはいましたが、自分が配属される部署で、実際に働いている人の話も聞いてみたくて。
特に、結婚や育児などライフプランと仕事の両立ができるかどうかについては正直不安だったのですが「ほとんどの人が戻ってくるよ」と、現場のリアルな声を聞けました。何より、自分が理想とするキャリアの参考になる先輩が身近にいるのは、心強いと感じました。
希望と違う配属となったらどう受け止めますか?
Aさん:私は営業として、お客様と密な関わりを持ちながら働きたいと考え、リース業界を志望しました。ただ、最終的には働きやすさや、産育休からの復職しやすさなどを考えて入る会社を選んだので、その結果営業以外の部署に配属されても、即転職という道は選ばないように思います。
Bさん:自分は、多様な部署を回れる「ジョブローテーション」を行っている会社を選んだので、希望しない職種で長く働かなければいけない〝配属ガチャ〞は心配していません。最初が希望通りでなくても、いつかは希望部署に行ける可能性が高いからです。
ただ、ジョブローテーションがなかったとしても、3年間は頑張ってみるんじゃないかな……。でも多分、それは「3年」が一つの目安といわれているからで、世間の風潮が「5年間は働け」だったら5年間を基準にすると思いますね。
まずは順応を意識
仕事で自分が育っていくうえで、会社には何を求めますか?
Eさん:自分は面接でこの明るい性格を評価してくれた会社、内定者懇親会で会った先輩社員の人柄にも引かれた会社へ就職を決めました。会社のペースに合わせる心構えはしているつもりです。
ただだからこそ、会社と仕事に対する温度感を共有したいと思っています。熱量を持って取り組む社風だというのであれば、先輩や上司には新入社員にそれを求めるだけでなく、自らが見本となるような姿を見せてほしいんです。自分たち若手にも同じ熱量を持って向き合ってもらえるとうれしいですね。
Dさん:もし指導が厳しくてつらいなと思っても、海外勤務という譲れない目標があるので、頑張ってくらいついていくつもりです。逆に全く指導されないような環境だったとしても、自分のスキルアップのために積極的に質問して、学んでいこうと思います。
Cさん:私は大学で参加していたサークルが、先輩後輩の垣根を越えた和気あいあいの雰囲気が特徴だったので、入社先の先輩にも、優しく親身に接してもらえるとうれしいと思うでしょうが、厳しい環境に置かれた際、自分がどう成長できるか、知りたい気持ちもあります。実際にはたじろいでしまうかもしれませんが、挑戦してみたいとも思っているんです。
Column
AI面接導入じわり
設問など工夫問われる
コロナ禍で「オンライン」が珍しくなくなった企業の採用面接に、さらなる先端技術導入の動きも出てきた。人工知能(AI)の活用だ。面接担当者の主観が入らない定量的な評価が期待できるとされ、飲食業や地銀の一部で試行例も広がる〝AI面接〟にどう備えるか。立教大学の小林哲郎准教授に聞いた。
現状は画面上の質問に答える形式が一般的だ。戸惑う学生は多いかもしれない。だがAIを使っても、企業には広く深く学生を理解したいという思いがあることを考えてほしい。
表情や声色からAIに人の印象を数値化させる研究も進んでいる。相手が人間でないことに油断せず、面接官と対面するのと同じ熱意を示せるかどうかが次のステップにつながる。場数を踏めば、自分なりの傾向と対策が見えてくるはず。臆せず前向きに捉えることが大事だ。

企業には人事担当者の負担軽減というメリットがある半面、設問のあり方や、学生の回答時間の調整など工夫の課題は少なくない。全員に画一的な質問を行うのではなく、AIの判断基準を開示して、何に注力して答えるべきかという指針を学生に伝えていくのがいいだろう。信頼性を担保するうえで、学生本人に評価をフィードバックしていくことも重要になる。
PROFILE
立教大学
スポーツウェルネス学部 准教授小林 哲郎氏
AIによる表情、音声のデータ分析からの印象の根拠となる総合的な指標の解析を目指す就職面接アドバイス・システムの開発中。
企画・制作=日本経済新聞社Nブランドスタジオ
特集TOPへ戻る