
-
中正 雄一代表取締役社長
大阪府出身。米屋の家業を継ぐことを念頭に大手製パン会社に新卒で入社。そこで出会った尊敬する先輩が独立し、夫婦で保育園を営むことに興味を持ち、30歳で保育業界へ転身。その先輩のもとで3年間経験を積み、2006年グローバルキッズを創業。2023年4月時点で東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪に160施設以上、従業員約4,000名の会社へと育て上げてきた。

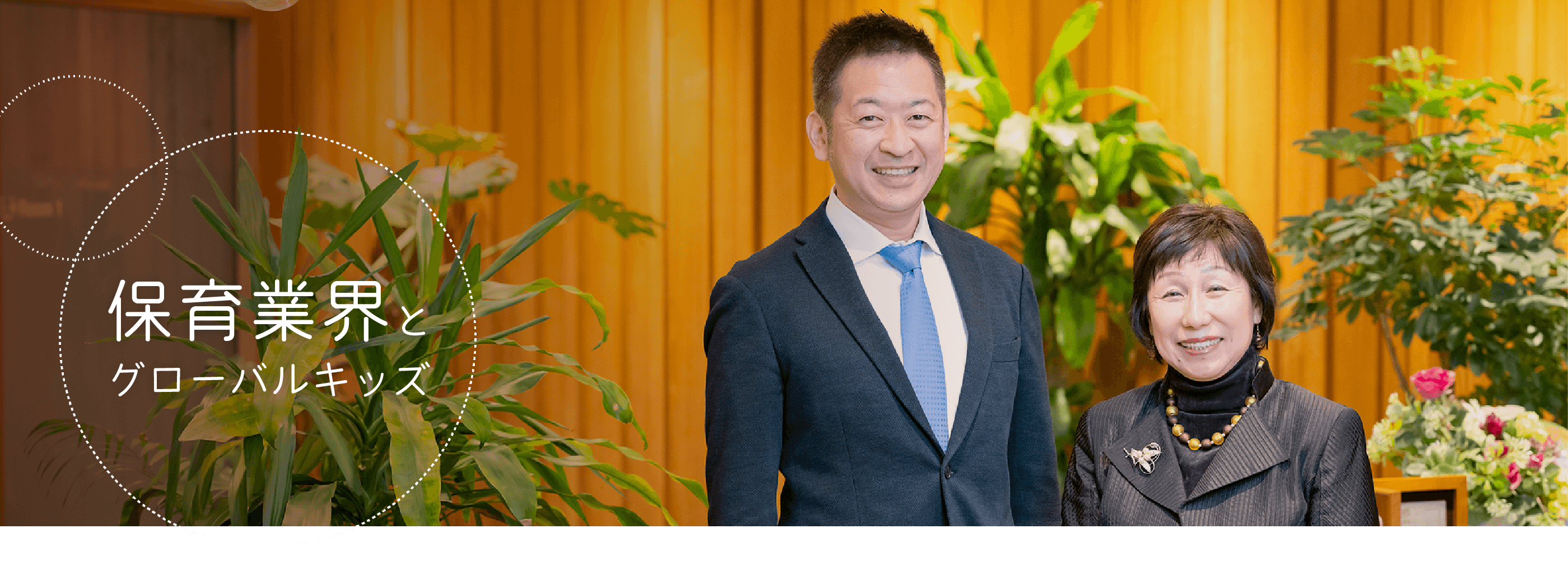
少子化、待機児童など、様々な問題に直面してきた保育業界。今後求められるのは、これまでを踏襲するのではなく時代に沿いながらこれからを創り上げていくことだそうです。そこでそうした背景をどう捉え、今後何をするべきかについて、業界トップクラスの存在へグローバルキッズを育て上げた代表・中正氏と子育て、家族研究の第一人者で、同社の社外取締役にも就く汐見氏に、業界のこれからや保育士として働く意義などについて、語り合っていただきました。
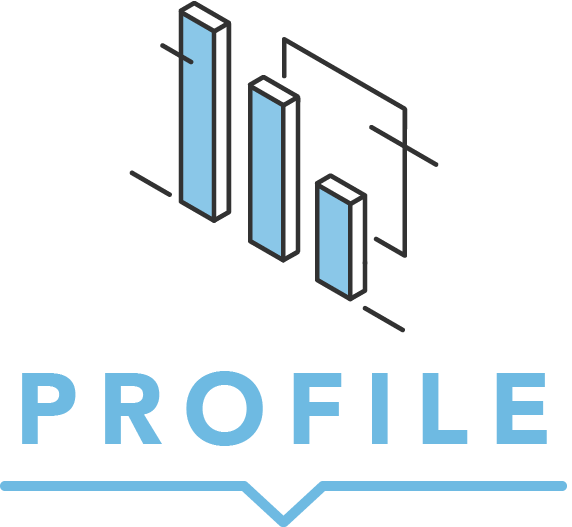

中正 雄一代表取締役社長
大阪府出身。米屋の家業を継ぐことを念頭に大手製パン会社に新卒で入社。そこで出会った尊敬する先輩が独立し、夫婦で保育園を営むことに興味を持ち、30歳で保育業界へ転身。その先輩のもとで3年間経験を積み、2006年グローバルキッズを創業。2023年4月時点で東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪に160施設以上、従業員約4,000名の会社へと育て上げてきた。

汐見 和恵社外取締役
42歳で大学、大学院へ進学。そこで学んだ家族社会学と社会福祉学を活かし、幅広く子育てと家族を研究する第一人者として知られる。現在は一般社団法人 家族・保育デザイン研究所所長を務めながら、夫である教育・保育評論家の汐見稔幸氏とともに、保育の未来創造に取り組んでいる。2021年12月より、グローバルキッズ社外取締役へ就任。
 これからの保育士に必要なことは?
これからの保育士に必要なことは?
 汐見 和恵
汐見 和恵日本における教育は長い間"教える"ことが人を育てると考えていましたが、最近はそれはちょっと違うということで、教育の方向が変わってきているのです。型にはめるのではなく、個を伸ばすーまさに中正さんが大好きな金八先生はその代表のような人ですね。
 中正 雄一
中正 雄一そう言っていただいてグローバルキッズと私が間違っていないなと確信できました(笑)。実は職員に願うことも、通う子どもに願うことも一緒で、テーマは自立と共生。それをしっかり養っていくために必要な環境は教えたいことを押し付けるのではなく、一人ひとりが考えるチカラを養い、紋切り型ではない風土を築き上げることだと思っています。
 汐見 和恵
汐見 和恵そうなんですよね。人はそれぞれ自分で自分を育てる存在です。だからこそ、しっかり歩んでいけるようにその人に寄り添って成長をサポートしていくことが必要です。
 中正 雄一
中正 雄一私自身は企業の社長なので、保育士とは立ち位置が異なるものの、何を目指していくかを定め、そこに向けて動いていくという仕事の根幹は同じ。それから様々なことを築いていく訳ですが、異なる個性でも同じ目標を定めれば自ずとまとまっていくんですよね。
 汐見 和恵
汐見 和恵そうした意味でも子どもがどんな時でも安心して通い続けたくなるように、一人ひとりを肯定する保育に取り組むことが、今後より求められていくと思います。
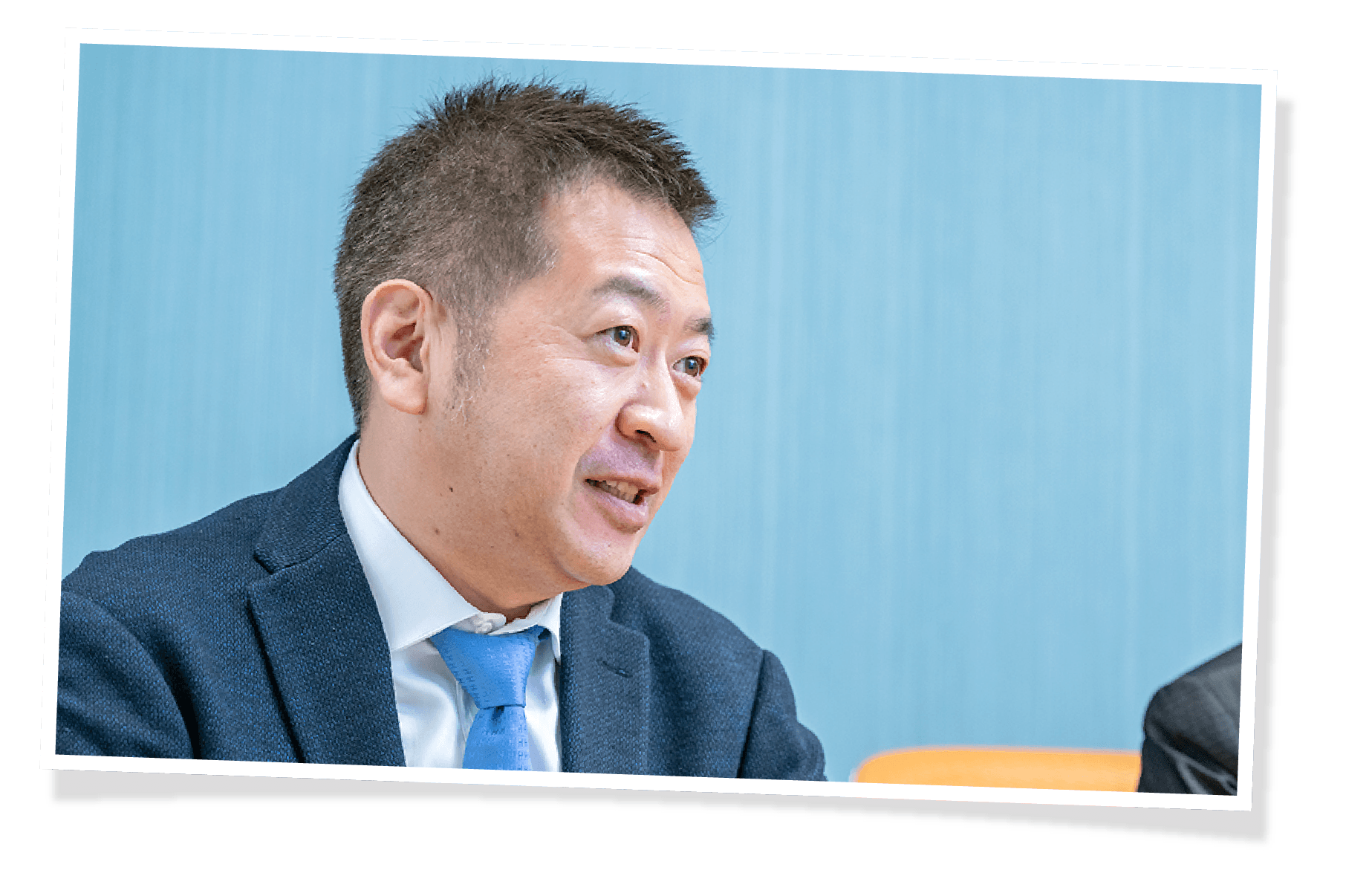

業界内でどうイメージされていると思いますか?
業界内でどうイメージ
されていると思いますか?
 中正 雄一
中正 雄一待機児童問題で保育園が足りないという状況のど真ん中で事業を展開してきたこともあり、数をどんどん増やしているなというイメージをこれまで抱かれてきたと思います。ただ時代が求めることの変化に合わせ、グローバルキッズの取り組みも柔軟に対応してきたため、その認識は確実に変わってきたと思います。
 汐見 和恵
汐見 和恵保護者の方からはどう認識されているとお感じですか?
 中正 雄一
中正 雄一"グローバルキッズ"という社名のイメージがまだまだ先行しています。「英語教育をやっているんですよね、だから早期教育の場に」とのニーズはまだまだ多いのですが、それは決してグローバルキッズがやっていきたいことと合致している訳ではありません。
 汐見 和恵
汐見 和恵確かにその先行するイメージ通りの運営を行うと、現場を縛り付けることに直結する可能性が高いですね。目指す頂と現場は違っていて当然ですが、そうであってもグローバルキッズだからこそ示せる価値や保育を貫くことは大切。そこに取り組んでいく中で、主体的に動ける現場を育てていくべきだと思います。
 中正 雄一
中正 雄一そこは私も同感ですね。保育の現場でより重要となるのは、早期教育の機会を与えることではなく、安心して子どもを預けられる保育への信頼をいただくこと。だからこそ取り組んでいかなければならないのは、保護者の目線を過度に重要視するのではなく、先生との信頼関係など当たり前の日常に対する評価を高めていくことだと思います。
 汐見 和恵
汐見 和恵これからは入れる園を探すのではなく、保護者が入れたい園を選べる時代となるはず。この取り組みを続ければ、早いタイミングで業界や保護者からの認識は変わっていくでしょう。


これから業界はどう変わっていくと思いますか?
これから業界は
どう変わっていくと思いますか?
 汐見 和恵
汐見 和恵待機児童の解消を目指して園の数が一気に増えましたが、2018年に制度が改定され、さらに少子化が進んでいくこれからは、ただ保育だけしていれば良いという状況ではありません。保育という立場に、より"育てる"というテーマが必要不可欠となっていくでしょう。
 中正 雄一
中正 雄一保育士だけではなく、教育者という存在に私たちはちょっとした怖さを抱いていた側面がありましたが、これから求められていくのはそうした怖さではなく、子どもに憧れられるように存在感を示していくこと。「輝いた大人を魅せていこう」と職員に私は伝えているのですが、大人が楽しく生きている姿に子どもは憧れ、自分も将来そうなりたいと思ってくれると確信しています。
 汐見 和恵
汐見 和恵先生が教えて、その通りに動いていれば良い時代ではもうないので、今まで通りでは、21世紀に通用する人に育つことができないと私は思っています。その視点で考えると、中正さんが掲げるビジョンには共感しかありません。それがあったからこそ、社外取締役への打診をお引き受けしたんですよ。
 中正 雄一
中正 雄一ありがとうございます。私自身、働く職員にも楽しく生きている実感を保育の現場から感じ取ってほしいと願っているんですよね。だから保育だけにフォーカスすることなく、色々と外で学ぶ機会を設けながら、人間として成長し続けてほしい。そこで得た刺激も子どもに伝えながら、楽しむこと、頑張ることを素直に受け取られるような保育に取り組んでほしいですね。
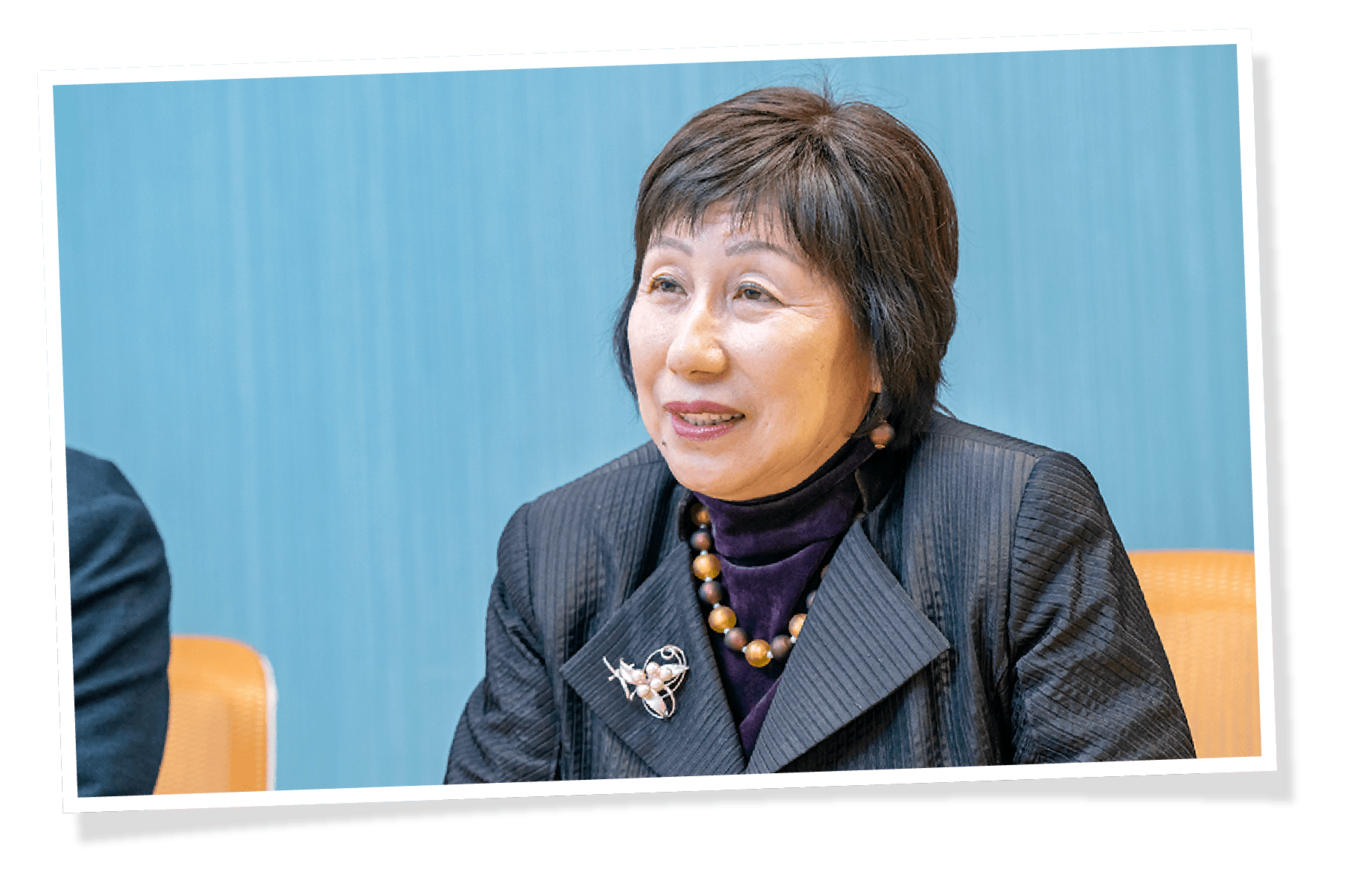

この先、企業として何を目指していきますか?
この先、企業として
何を目指していきますか?
 中正 雄一
中正 雄一私が設置した施設のほとんどは保育園ですが、中には小学校や中学校も含まれています。将来的には高等学校、大学と一貫して"自立と共生"を養える存在になることを実現したいと思っています。
 汐見 和恵
汐見 和恵中正さんの人に対する想いや考え方には、本当に感銘を受けます。事実、人を育てるのは、育ちに深く関わることもあって専門性が非常に高い仕事。学ぶ場所が変われば、それぞれに個性があるので、目指すものが異なってしまいますね。そうした視点で将来を考えると、ぜひそれを実現してほしいと願っています。
 中正 雄一
中正 雄一ただ、企業としてこれをむやみに行ってもダメだと確信しています。人を育てる事業を真っ当に展開していくためには、働く人も正しく育てていかなければなりません。その視点を創業当初から大切に取り組んできました。
 汐見 和恵
汐見 和恵お伺いしています、先生方が日々しっかり学んでいけるように、押し付けではなく任せることを大切にしているのですよね。
 中正 雄一
中正 雄一日々の取り組みの中で職員が考え、相談し合い、創ることを基本にしています。例えば、もっと子どもが全身を使って遊べるようにしたいと思ったら、実現のために色々と考えなければいけませんよね。それが職員の成長には非常に重要です。もちろん施設にそれらを押し付けるのではなく、企業としてしっかりとサポートを行い、安心して楽しく仕事に取り組み、成長し続けられる文化を創る。それがしっかり整った先に、目指したい未来があると確信しているんですよ。
 汐見 和恵
汐見 和恵これを成し遂げる取り組みは、業界全体に新しい風を必ず吹き込ませることに繋がっていくはず。私も社外取締役として、しっかり協力していきたいですね。
