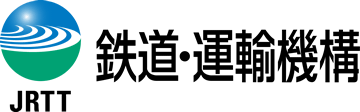生まれ育ったまちの
新幹線建設に貢献できる
かもしれない
理工学部 電気工学科 2020年入社
JRTTの電気系職員が担当する設計・工事は、変電、電車線、電力、通信、信号の5部門。列車の動力源の供給や列車制御、列車無線など、列車の安全走行を支える分野から、照明、旅客案内、監視カメラといった駅業務の分野まで、幅広い分野をカバーしている。
※掲載内容は取材当時のものです。
電車線路設備の設計がキャリアのスタート
大学では電気インフラ系の研究室の鉄道班で、網状接地(メッシュ接地)や送電用鉄塔への雷害対策などを学んでいました。幼い頃から鉄道が好きで、叶うならば鉄道に関わる仕事がしたいと思ってこの研究室を選びました。JRTTの存在は中学生のときに知りました。授業で地域の歴史や未来について調べる機会があり、地元の福井県に北陸新幹線が延伸されること、新幹線の建設は国の事業としておこなわれていることを学んだのです。
就職先としてJRTTを志望した理由は、人事担当の方の人柄です。就職活動の一環で相鉄・JR直通線の羽沢横浜国大駅の建設現場を見学した際、電気系統の技術に関する質問をしました。すると後日、メールでとても丁寧な回答が届いたのです。応募するかどうかもわからない一人の学生に対して、こんなに誠実に対応してくれるのかと感動して志望しました。また当時、北陸新幹線(金沢・敦賀間)(2024年3月開業)の延伸工事が進められていたことも理由の一つです。実は、大学院への進学も視野に入れながら就活をしていたのですが、開業までの期間を考慮すると、学部卒での入社が叶えば地元の福井県で新幹線建設に貢献できるかもしれないという想いを抱くようになりました。人生を左右する決断ということで非常に悩みましたが、可能性がゼロでないのなら挑戦してみたいと思い、JRTTへの入社を決めたのです。
入社して最初に担当したのは、西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の電車線路設備の設計業務です。具体的には、現場で進められている電車線工事で発生する課題解決のサポート、設計変更に伴う図面作成や積算業務など。そのなかで心がけていたのは、先輩、上司と積極的にコミュニケーションをとって自分を知ってもらうことです。新人にも裁量を与え、そのうえでフォローしてくれるチームだと入社後の早い時期から感じていましたので、失敗を怖れず積極的に様々な業務に関わってみようと考えていました。
 「採用面接でアピールしたのはコミュニケーション力。誰とでも打ち解けられる性格なので、チームの潤滑油になれると思ってそう伝えました。この点は今でも私の強みです」
「採用面接でアピールしたのはコミュニケーション力。誰とでも打ち解けられる性格なので、チームの潤滑油になれると思ってそう伝えました。この点は今でも私の強みです」
感動を分かち合えたことを忘れない
地元で新幹線建設に貢献したい。入社前の願いが叶ったのは2年目のことでした。北陸新幹線(金沢・敦賀間)の電車線設備の施工監理技術者として、福井鉄道電気建設所(福井県)に着任しました。私の担当工区は、福井県と石川県の境にある加賀トンネルから越前市の武生トンネルまでの約50km。電化柱の建植や電車線の敷設工事に関する施工監理をおこなうため、毎日のように現場へ通いました。
初めての現場で最も難しいと感じたのは、言葉の選び方。現場の安全・工程・品質を守ることに新人もベテランもないのですが、発注者側の人間と受注者側の人間が立場や経験を超えて信頼関係を構築するのはそう簡単ではありません。事故を防ぐために厳しく指摘しなければならない場面もありますが、言葉の選び方を間違うと誤解が生まれ、円滑なコミュニケーションを取ることが難しくなり、工事が進まなくなってしまう恐れがあるので、毎日が試行錯誤の連続でした。だからこそ、現場代理人の方に評価していただいたときはうれしかったですね。同じ職場の仲間が「現場代理人の方が、川﨑さん、めちゃくちゃ頑張ってると言っていたよ」と口々に教えてくれました。それが励みになりました。
この現場では生涯忘れることはないと思える出来事が二つありました。一つは2023年9月の入線架線試験に立ち会えたことです。入線架線試験は『イーストアイ』と呼ばれる検測用新幹線車両を時速30キロで走行させて構造物や線路、電車線などに不具合がないかを確認する試験で、私は越前武生駅の分岐点で待機して走行中のパンタグラフと電車線を目視でチェックしました。幻の新幹線と呼ばれる『イーストアイ』をこの場所から見ることができるのは限られた人だけですので、仕事を終えた後は鉄道ファンの一人として感慨に浸りました。
そしてもう一つは、開業の感動を家族と分かち合えたことです。開業直前、関係者や住民の皆さんを招いておこなう試乗会に、私は福井県に暮らす両親と祖父を招待しました。走行時間は15分程度ですが、時速260キロで走る新幹線から、生まれ育ったまちを家族と見ることができました。足が不自由でなかなか外に出なくなっていた祖父が喜んでくれたのが嬉しかったですね。JRTTに入社して本当によかったと思えた瞬間でした。父とは開業当日も新幹線に乗りました。「すごい仕事をしたなあ」と言ってくれたときの誇らしい気持ちは、この先も忘れることはないと思います。
 受注者側の現場代理人、他系統の技術者と何度も協議を重ねて落としどころを見つける仕事。「言葉の選び方ひとつで相手との関係が変わるので、今も悩みながら日々学んでいます」
受注者側の現場代理人、他系統の技術者と何度も協議を重ねて落としどころを見つける仕事。「言葉の選び方ひとつで相手との関係が変わるので、今も悩みながら日々学んでいます」
設計段階の課題を解決するのが楽しい
現在は東京にある鉄道技術センターで北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の札樽トンネル、札幌駅、札幌車両基地の電灯電力設備の設計を担当しています。主な電灯電力設備としては、駅のホームとコンコースの発車標、駅やトンネルの照明、線路を切り替える分岐器のヒーター、配電所の変圧器や分電盤などがあります。設計の仕事はこうした設備や電源の配置を決めることで、外部の設計コンサルタントとやりとりを重ねて図面をつくりあげていきます。
担当工区のなかで特に面白さを感じているのは、札幌駅と新小樽駅(仮称)の間に位置する札樽トンネルです。このトンネルの特徴は、NATMとシールド工法の2つの異なる工法で建設を進めていることで、札幌側では整備新幹線で初めてシールド工法を採用しています。
トンネルの建設方法が今までにない形になると電灯電力設備の設計も影響を受けるため、新たな方法での設計が要求されます。初めての連続で大変なこともありますが、前例がないからこそ自分の意見を反映しやすく、その点が楽しかったりもします。入社以来、電車線設備を担当してきた私にとっては電灯電力設備の設計自体が初めてなので、どれだけ学んでも知識が追いつかず、力不足を感じることもあります。それでも、新しいことを学び、工夫する楽しさがはるかに上回っています。JRTTに蓄積された鉄道建設の膨大なノウハウのなかから見つけたヒントをもとに、先輩や上司、他系統の技術者と話し合いを重ねて解決する。そこにやりがいを感じています。
今後は札樽トンネルをはじめ、設計を担当した工区で工事の施工監理を担当したいと考えています。そして将来は、施工監理業務で学んだシールド工法のノウハウを生かし、大都市での新幹線建設に携わりたいですね。
 「同じ部署には3年下の後輩がいますが、電灯電力設備の設計に関しては彼の方がキャリアが長いため教わることも多い。互いに知識と技術を補完しながら進めています」
「同じ部署には3年下の後輩がいますが、電灯電力設備の設計に関しては彼の方がキャリアが長いため教わることも多い。互いに知識と技術を補完しながら進めています」
MESSAGE
入社後の5年間を振り返って最もありがたかったのは、気心の知れた同期の仲間が同じ職場にいてくれたことです。私の場合、初めての異動先が生まれ育ったまちでしたので生活面ではまったく不安はありませんでしたが、仕事は初めて経験することばかり。同じ状況で頑張っている仲間が近くにいることがとても心強かったです。
特に大きかったのは、土木、機械、建築、事務など、他系統の同期の存在です。JRTTでは異なる系統同士で連携する機会が多く、ときには自系統を代表してしっかりと主張しなければならない場面もあります。先輩にはなかなか言えないことも同期の仲間になら言える。それで救われたことが何度もあります。休日は日帰りで温泉地へ一緒に出かけることが多かったですね。私以外は都会育ちでしたが、みんな地方での生活を楽しんでいました。
同期の仲間との距離が縮まったのは、入社後の新入職員研修です。一緒に学び、1日の終わりにお酒や食事を楽しむことで仲良くなりました。社内外を問わず、コミュニケーションの手段や人との関わり方は時代とともに変化していますが、JRTTは直接的なコミュニケーションを大切にしていると感じます。研修の際には系統を超えてできるだけ多くの人と関わり、気を許せる仲間をつくっておくと、仕事が楽しくなり生活も豊かになると思いますよ。
 JRTTでは新人も初年度の4月から有給休暇の取得が可能(20日間)。「1年目でも上司に直接『休みます』と言える職場です。勤務時間を柔軟に変更できるところも気に入っています」
JRTTでは新人も初年度の4月から有給休暇の取得が可能(20日間)。「1年目でも上司に直接『休みます』と言える職場です。勤務時間を柔軟に変更できるところも気に入っています」