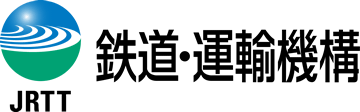北陸新幹線。
開業の感動は
何度でも味わいたい
大学院 建設社会工学専攻 2018年入社
長年にわたって磨き続けてきた技術や最新の工法を駆使して、橋りょうやトンネル、軌道などの構造物を建設するのが土木系統の職員です。建設路線の調査、計画、構造物の設計・発注・施工監理、地方公共団体や鉄道事業者との協議、技術開発の推進など、その業務は幅広く、交渉力や調整力を発揮できる場面もたくさんあります。
※掲載内容は取材当時のものです。
発注者側の技術者として計画から建設まで担当できる
大学院では、コンクリート研究室の材料グループに所属。北九州モノレールのメンテナンスに役立てるため、建設材料や構造物のアルカリシリカ反応(ASR/コンクリート中の骨材に含まれるシリカ鉱物とアルカリとの反応によりアルカリシリカゲルが生成され、膨張やひび割れを引き起こす現象)のメカニズムと、診断、補修・補強方法を研究していました。
JRTTの事業や土木系職員の業務については、この研究室のOBで西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の土木工事に携わっていた先輩から聞きました。新幹線や鉄道に対して特別な思い入れはなかったですが、スケールの大きな仕事ができること。発注側の技術者として計画から建設まですべての工程を担当できること。この2つに魅力を感じて志望しました。
採用面接でアピールしたのはプレゼンテーション力です。この研究室は土木学会やシンポジウムで発表する機会が多く、起承転結のストーリー構成を意識してエピソードを組み込むことの大切さを学んでいましたので「物事を相手の立場で分かりやすく伝える自信があります」とアピールしました。
1年目の配属先は大阪支社(現:北陸新幹線建設局大阪事務所)で、北陸新幹線(金沢・敦賀間/2024年3月16日開業予定)の第2福井トンネル、鯖江橋立高架橋、第2鯖江トンネルの建設工事に関する発注手続きや設計・工事内容の変更について社内の関係者へ説明し、承認を得る業務を担当。このほか、トンネル入口部における斜面防災の現地調査などが主な業務でした。また、JRTT内の他部門や受注者である建設コンサルタント会社との工法検討や作業進捗に関する打合せにも参加しました。
そのなかで心がけていたのは、不明点をそのままにしないこと。先輩・上司は「いつでも何でも聞いてくれ」と言ってくれていましたが、まず自分で調べてどうにもならないことだけを聞くようにしていました。専門用語や社内規程などは自分で調べたり、考えることを徹底したことで早く理解できたと思っています。
 「大阪支社では構造物の建設費や事務手続きの手順・社内規程について理解を深めることもできました。大阪での生活もとても楽しかったですし、いいスタートを切ることができました」
「大阪支社では構造物の建設費や事務手続きの手順・社内規程について理解を深めることもできました。大阪での生活もとても楽しかったですし、いいスタートを切ることができました」
工事関係者との調整をおこなった
建設工事の施工監理を初めて経験したのは、入社2年目の春。福井県の越前鉄道建設所に異動し、鯖江橋立高架橋(全長2,561m)を担当しました。初年度に大阪支社で担当していた3つの構造物のうちの一つですね。
土木系職員が現場でおこなう主な業務は5つあります。1つは現地調査。工事に先立ってトンネル斜面の防災対策、高架下の整備状況を確認します。2つめが現場立ち会い。施工状況や品質をチェックします。3つめが工程管理。JRTTの他部門(軌道、電気、建築など)、受注者側の代表者との打合せ、進捗確認が中心です。4つめが事務手続き。大阪支社でおこなっていた契約変更などの事務手続きに必要な書類を作成したり、契約変更をする理由を整理します。そして5つめが地元対応です。地元に対して工事の時間帯や騒音対策、環境対策などに関する説明などをおこないます。
最も難しいと感じたのは、業務フローやタスクの標準化です。鯖江橋立高架橋は工事延長が長いことから5つの工区に分け、それぞれ異なる建設会社が工事を担当しており、多くの工事関係者が携わっていたため、すべてを受注者側に任せてしまうと作業の手順や品質に差が出てしまう可能性がありました。それを防ぐために各工区の代表者との情報共有を徹底し、同じ作業手順、同じ品質となるよう監理していました。時にはどうしても伝わりきらないこともありましたが、そのような場合は他の工区を見てもらい、違いを認識していただくといったこともしていました。
年齢も現場経験も上の技術者に指示を出すのは簡単ではありません。しかし、そこでためらっていると軌道工事や電気工事といった、後工程にも影響が出かねませんので、いいものをつくりたいという気持ちは誰もが持っていると信じて、何がよくて何がだめなのかを明確にして伝えていました。だからこそ、想いが通じたときはうれしかったですね。
JRTTでは一定期間(2〜5年程度)ごとに異動があるため、私は鯖江橋立高架橋の完成を待たずに東京支社へ異動となりましたが、しゅん工後に実施される鉄道事業者の監査には立ち会うことができました。事務手続きから担当して、現場では毎日、完成に近づいていく様を見ていた構造物を隅々までチェックする。その仕事には今まで味わったことのない大きな感動と達成感がありました。開業後、担当した区間を新幹線に乗って通る日が今から楽しみです。
 「定められた工期の中で土木工事をおこない、次の工事にバトンを繋いでいく、現場での緊張感は想像以上でした。限られた時間のなか、工事関係者と協力しあい最善な方法で工事を完了させる思いで粘り強く進めていきました」
「定められた工期の中で土木工事をおこない、次の工事にバトンを繋いでいく、現場での緊張感は想像以上でした。限られた時間のなか、工事関係者と協力しあい最善な方法で工事を完了させる思いで粘り強く進めていきました」
新横浜駅の盛り上がりは想像をはるかに超えていた
東京支社へ異動後は、相鉄・東急直通線の開業準備を担当。鉄道事業者との協議用資料や議事録の作成、備品の手配をはじめ、事務手続きと調整業務が主な仕事でした。そのなかで特に印象に残っているのは、開業を5ヵ月後に控えた2022年の10月に実施した総合監査です。
総合監査は列車の安全走行を確認するための走行試験で、JRTTの監査員や鉄道事業者の立ち会いのもと「羽沢横浜国大駅」から「日吉駅」間で20日間にわたって実施。私は走行試験の進行係として、試験項目を記載した手順書の作成や内容の周知をはじめとする「シナリオ作成」と呼ばれる業務を担当しました。
最も大変だったのは、走行と通信に必要な電力を電車線に供給するスケジュールを決めることでした。土木系職員の私は電力や通信の知識はほとんどありませんので、上司や先輩、電気系統の職員から基礎知識を教わりながら日々のシナリオを作成し、トランシーバーを手に試験車両に同乗していました。走行試験は終電通過後から始発までの時間帯だけではなく、昼間も営業線ダイヤの間隙を利用して実施します。何かトラブルがあると営業線に大きな影響を与えてしまうため、試験内容を鉄道事業者と入念に調整し、密な連携を心掛けていました。
そんな準備を経て迎えた相鉄・東急直通線の開業(2023年3月18日)は、先輩たちと新横浜駅に集まり、列車に乗りました。前日の深夜には20名を超える人たちが列を作っておられたので注目度の高さ、期待の大きさを改めて実感しましたが、当日の盛り上がりは想像をはるかに超えていました。写真や動画を撮影する人。列車に向かって手を振る人。そこにいる誰もが笑顔で喜んでくれているのがうれしかったですね。JRTTに入社して本当によかったと思えた瞬間でした。
現在は、新横浜駅を建設するために環状2号線から一時的に撤去していた照明設備や道路の案内標識、歩道橋などの復旧工事を進めています。行政が定めている環境整備に関する方針や規格は、短期間で変わるため、協議にしても書類作成にしても柔軟な対応力が求められます。そこが少し難しいですが、新しい知識を経験できることにやりがいを感じています。道路を構成する設備や標識の目的を学んだことで日々の散歩も楽しくなりました。
 「開業を実現できたのは、JRTTの職員、鉄道事業者、受注者の皆さんをはじめ、関係者全員が同じ方向を向いて結束したからこそ。この感動は何度でも味わいたいです」
「開業を実現できたのは、JRTTの職員、鉄道事業者、受注者の皆さんをはじめ、関係者全員が同じ方向を向いて結束したからこそ。この感動は何度でも味わいたいです」
MESSAGE
鉄道の建設工事は地方都市においても時間厳守。作業が可能な時間帯や曜日は、行政や地元の住民の皆さんと交わした約束を守ることが原則なので、週末は確実に休むことができます。有給休暇(年間20日付与)や夏季特別休暇(年間7日間付与、7月~9月の期間に任意のタイミングで取得可能)も気兼ねなく申請できる職場ですので、地方に配属されたときはぜひ、その土地のグルメや文化を探訪してほしいですね。先輩や上司は観光名所やおいしい店をたくさん知っていますので、私も越前鉄道建設所(福井県)にいたときは教えてもらったところに毎週のように出かけていました。そうやって生活を楽しむことが、全国的な異動を実りあるものにするポイントだと思います。
土木工学は経験工学と言われているように、JRTTの技術者も鉄道建設に必要な知識と技術は現場で学んでいきます。施工監理技術者として現場に出る時期はかなり早いですが、JRTTでは計画や設計、発注などを経験してから現場に出るという流れができていますので、大学で基礎をしっかり学んでおけば大丈夫。研究室や学会で発表した経験も、JRTTの他部門や鉄道事業者、行政との協議の際にきっと役立つと思います。また、JRTTでは近年、技術継承を急ピッチで進めていて、私も大学のように組まれた講義を毎週受講しています。仕事との両立は簡単ではありませんが、学ぶことが好きな人にも合っている職場ですよ。
 環状2号線の復旧工事は2023年度末に完了予定。「今後の異動先は決まっていませんが、将来的には地元九州の土木工事に携わりたい。いずれは整備計画路線の環境調査にも携わってみたいですね」
環状2号線の復旧工事は2023年度末に完了予定。「今後の異動先は決まっていませんが、将来的には地元九州の土木工事に携わりたい。いずれは整備計画路線の環境調査にも携わってみたいですね」