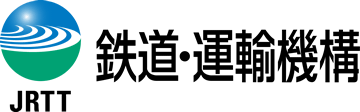同期の仲間との絆が
仕事でも生活でも
大きな支えになる
法学部 法学科 2019年入社
用地取得や入札・発注手続き、国内の海運事業者への資金的・技術的支援、組織運営に関わる管理業務など、多種多彩な仕事でものづくりを支えるのがJRTTの事務職。専門的な知識が要求され、数字と向き合う場面も多いので、日本全国どこにいても事業スケールの大きさを十分に実感できるはずだ。
※掲載内容は取材当時のものです。
新幹線の存在がどんどん大きくなっていった
将来は「全国いろいろな場所で仕事がしたい」「公的な仕事で多くの人の役に立ちたい」と考えていました。その中でJRTTの存在を知りました。説明会では鉄道建設事業の規模と経済効果を知って衝撃を受けたのを憶えています。私にとって交通手段のひとつでしかなかった新幹線の存在が、その日からどんどん大きくなっていきました。入社の決め手は人事担当の方の人柄です。特にうれしかったのは、面接の後、京都まで来て採用に至った理由を話してくれたことです。一人の学生とこんなふうに向き合ってくれる人がいる組織なら、どの職場でも安心して仕事ができると思い、決断しました。
初任地は北海道。初めての仕事は北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の用地取得業務でした。用地取得業務は新幹線の建設に必要な事業用地を取得する仕事で、沿線住民の方への説明会の開催、補償金額の算出、地権者の方との交渉・契約、不動産登記申請などをおこないます。着任したのはこの業務の最盛期。新人の私は、上司と委託先の市の担当者が進める地権者の方との交渉に同席し、議事録を作成することからスタート。最初は専門用語や流れを理解することに専念していましたが、1年目の後半に入る頃には「もっと役に立ちたい」という想いで話し合いに参加。地権者の方のご家族や趣味に関する話題になったときに話を膨らませて場を和ませる程度でしたが、上司が評価してくれたことが自信になり、それから徐々に交渉・契約の話にも加わるようになりました。
想像以上に難しかったのは、地権者の方の身になって考え、納得していただくことです。私が担当した札幌市内はほとんどがトンネルの区間。愛着ある土地を離れていただく必要はありませんが、ご理解を得るまでに時間を要すことがほとんど。「自宅の地下を毎日新幹線が通る。あなたは平気ですか?」と問われて言葉に詰まったこともありました。だからこそ、契約していただけたときは大きな達成感がありました。賛同していただいた多くの方から「開業を楽しみにしています」と言っていただけたので、北海道新幹線への期待も十分感じることができました。
 「用地取得業務で意識していたのは、専門用語に頼らずに伝えること。地権者の方にご説明する際は、技術職の先輩の協力を得て回答に使う言葉や表現を精査していました」
「用地取得業務で意識していたのは、専門用語に頼らずに伝えること。地権者の方にご説明する際は、技術職の先輩の協力を得て回答に使う言葉や表現を精査していました」
歓声が飛び交うホームに立ち、胸がいっぱいに
初めての異動は入社3年目。異動先は大阪府にある北陸新幹線建設局の総務課でした。ここでは局内の庶務を担当。公的機関であるJRTTが自治体や建設会社に発出する公文書の管理。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて公開する各種情報の審査・整理。建設所内で使用する備品の調達などをおこなっていました。目立たない仕事ですが、あらゆる系統の職員と関わるので人脈が拡がり、事務的なスキルを磨くこともできました。
そして4年目には石川県にある北陸新幹線建設局渉外部へ異動。着任したのが北陸新幹線(金沢・敦賀間)の開業まで1年というタイミングでしたので、PRイベントの企画・運営。マスコミ各社の取材対応。地域住民の方からの問い合わせ対応。プレスリリースの作成など、開業関連の広報・渉外業務の多くに携わりました。
なかでも忘れられないのは、2023年9月に始まった『イーストアイ』(線路や架線を点検しながら走行する車両)による総合監査・検査(車両が安全に走行できることを確認する業務)です。その初日、私は写真撮影のために駅から離れた田園地帯で待機していました。すると地域の方々が集まって来られて「このまちで新幹線に乗れるなんて本当に楽しみ。開業まであと少しね。がんばって」と声を掛けてくださいました。最高の形で開業を迎えていただけるようにベストを尽くそうと誓った瞬間でした。
その1週間後、金沢・敦賀間の新駅6つに一般の方々を招待(各駅に500名)して開催した入線イベントも大盛況でした。このときは駅で運営をおこなっていましたが、ホームに列車が入線すると大歓声が上がり、まるでライブ会場のような熱気でした。多くの方が新幹線を待ち望んでくれている姿に感動で胸がいっぱいになりました。
開業当日は、早朝から小松駅で出発式に参加。一番列車を見送った後、福井県主催の開業式典対応。夕刻に石川県へ戻り石川県主催の開業式典対応後、事務所に戻ってマスコミ各社からの問合せ対応などをおこないました。仕事に追われて慌ただしく過ぎていきましたが、最後に残ったのは心地いい疲労感。「ついに新幹線が開業した」ということを十分に実感した1日でした。
 北陸新幹線建設局(石川)では、開業イベントの企画や広報・渉外業務を担当。「新幹線建設で地域が変わる。入社前の説明会で聞いたことは本当だったと実感しました」
北陸新幹線建設局(石川)では、開業イベントの企画や広報・渉外業務を担当。「新幹線建設で地域が変わる。入社前の説明会で聞いたことは本当だったと実感しました」
誰にとっても学びやすい研修プログラムにする
現在は本社で人材育成を目的とした施策の企画・立案をおこなっており、私の仕事は大きく分けて3つあります。一つは、若手職員のスキル向上プログラムの企画・運営です。これはおおむね入社10年目までの職員が対象の施策で、対象職員ひとりひとりが1年間の目標を設定し、専門スキルと共通スキルを高めていきます。専門スキルは、事務系統の職員でいえば用地取得・補償や予算、物品契約・物品管理など。共通スキルは説明・報告やスケジュール管理など、どの系統でも必要とされるスキルです。入社6年目の私はこのプログラムの対象者でもありますので、自身の経験や感覚も大切にしてプログラムのベースづくりを進めています。
二つめは講演会の企画・運営です。機構の事業に関係の深い有識者の方などにご講演いただき、職員の「多角的な視野の獲得」や「視野の拡大」につながる機会を提供しています。地方機関の職員も受講できるようにオンラインでの配信もおこなっています。そして三つめが、新人研修や階層別研修の企画・運営です。私はサポート役として会場の書類や会場設備の準備などを担当しています。
すべての業務で意識しているのは、職員の負担を最小限に留めることです。仕事をしながら学ぶことの大変さ、難しさは私自身も知っていますので、誰にとっても学びやすく取り組みやすいプログラムづくり、セミナー開催を目指しています。だからこそ、開催後のアンケートに「とても分かりやすかった」「これからもぜひ続けてほしい」という回答があるとうれしくなります。次回はもっといい内容にしようと意欲が湧いてきますね。
 4つの拠点で異なる業務を担ってきた一色さん。「対外的な仕事が合っている気がします。いつかは事業が進捗している北海道に戻って、また新たな経験を積んでみたいという気持ちもありますね」
4つの拠点で異なる業務を担ってきた一色さん。「対外的な仕事が合っている気がします。いつかは事業が進捗している北海道に戻って、また新たな経験を積んでみたいという気持ちもありますね」
MESSAGE
JRTTの人材育成に関する取り組みを客観的に見て「いいな」と思うのは、研修の機会が増えたことです。現在、入社1年目から5年目までは、毎年同期が一堂に会する研修を実施します。全国で頑張っている仲間との絆は、仕事でも生活でも大きな支えになります。私自身、どの部署でも同期の仲間に助けられてきましたので、社会に出てからはぜひ同期の絆を大切にしてほしいと思います。
これから全国的な異動を経験する皆さんには「初めて暮らすまちでも好きなことを通じて友達をつくる」ということをおすすめしたいですね。配属先にはおそらく年齢の近い先輩や同期の職員がいると思いますが、職場以外にも気を許せる人がいれば仕事も生活もさらに楽しくなりますよ。私は学生時代に打ち込んだバドミントンの社会人サークルに参加して友達をつくっています。
 「どの職場にも共通したJRTTの良さは、先輩や上司にいつでも相談できる温かい雰囲気。配属されたすべての職員にのびのびと仕事をしてほしい。そんな思いが伝わってきます」
「どの職場にも共通したJRTTの良さは、先輩や上司にいつでも相談できる温かい雰囲気。配属されたすべての職員にのびのびと仕事をしてほしい。そんな思いが伝わってきます」