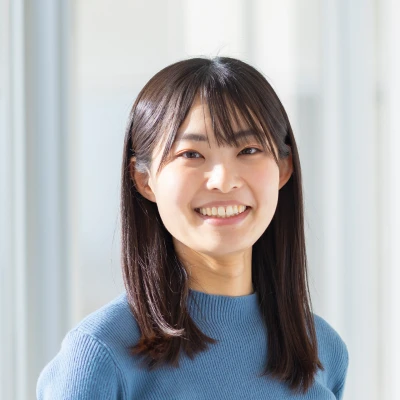解析技術のミッションは、半導体の開発や製造工程で発生する不良の原因を迅速に特定し、改善に結び付けることで、製品の品質向上に貢献する重要な役割を担っています。
半導体は、開発から設計、量産、出荷まで様々な工程を経て製造されます。製造工程の中では、予期しない不良が発生するため、製品技術、プロセス技術、デバイス技術など関連部署と解析技術が一緒になり原因究明に取り組みます。
解析技術では、発生した不良症状から故障原因を推測し、実際の不良原因を特定するために、電気的な解析装置(パラメータアナライザー、発熱解析装置など)を使用したり、X線CTなどの非破壊検査、電子顕微鏡を用いて構造的な異常がないかを調査するなど、多くの解析技術や装置を使用します。結果として数十nm程度の異物が不良の原因だったこともあります。そうした様々な検査や装置を駆使して原因究明を行うことから、半導体デバイスにおける「医者」や「鑑識官」のような職種に例えられます。

解析技術は電気解析、構造解析、形態観察、化学分析など多岐にわたりますが、中でも私は、原子レベルの表面の組成や化学状態を明らかにする表面分析の領域を担当しています。
私が取り組んできた中での大きな経験は、あるデバイスの新規開発において、イメージセンサーをパッケージと電気的に接続するための金属端子で形成されているボンディングパッド表面の汚染量が基準値を超えていたため、量産までに汚染量を低減させるべく、デバイスエンジニアやプロセスエンジニアなど関係者が集まる中で解析エンジニアの代表として参画したことです。
量産の開始日が迫る中、改善試作品作製→解析→メカニズム考察を短期間で繰り返し行い、汚染量低減に向けた取り組みを実施しました。早急に正確な結果をアウトプットする必要があり、緊張感をもって取り組んだことが印象に残っています。
初めはなかなか汚染量が低減せず苦戦しましたが、多面的にアプローチしたことで徐々に低減させることができ、量産開始さらにはメカニズム解明にも貢献することができました。
また、解析結果のアウトプットでは、解析の立場から気づいた製造工程の改善に向けた施策を提案したりするなどして、開発の手助けとなるような働きかけも同時に行いました。

開発品で発生する新たな不具合の原因を早急に見つけることで、新規デバイス開発の促進に貢献でき、最終的にはお客様の満足度向上に貢献できる仕事です。
解析技術は、デバイスをつくる職種とは違い、デバイスを物理的に破壊しながら中身を見て解析していく職種ですから、デバイスの構造を自分の目で実際に見ることができるという面白さがあります。開発から出荷まで、様々な工程の多種多様なデバイスを扱うため、日々新しいデバイスの構造を目にしながら、最先端の開発に携わっているという手応えを感じることができています。
もちろん、幅広いデバイスやプロセス、解析の知識・技術を習得することができますし、自分が対応した解析で不良原因の究明やメカニズム解明ができ、開発側で新しいアクションが起きたときや、良品率や品質向上に直接的に貢献できたときは、とてもやりがいを感じることができる仕事です。