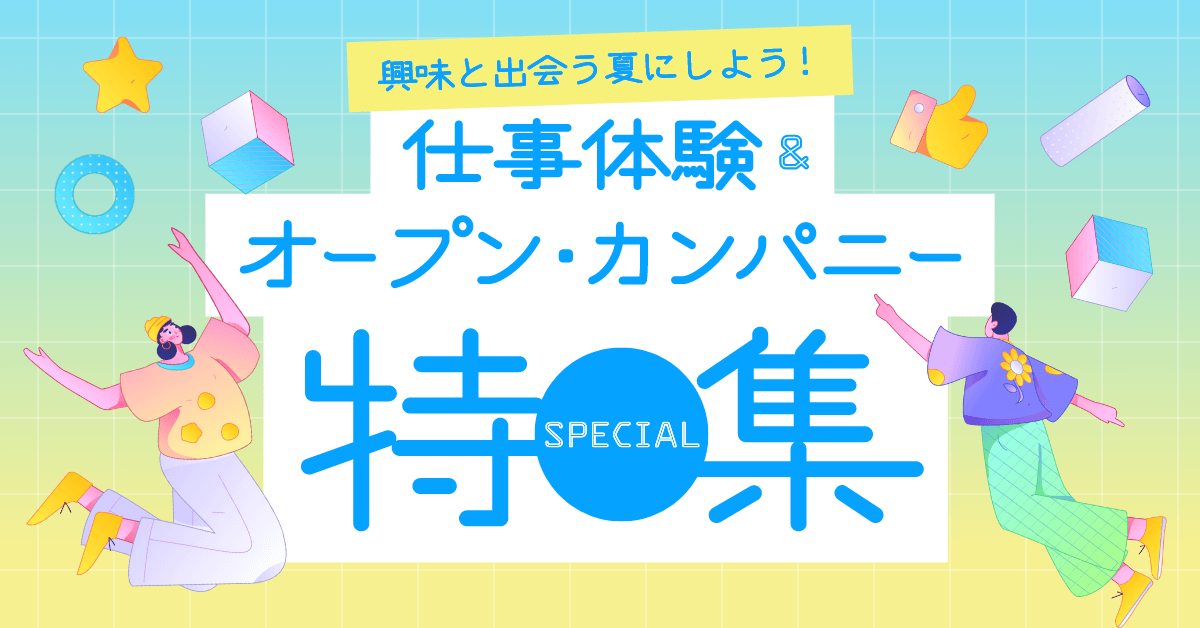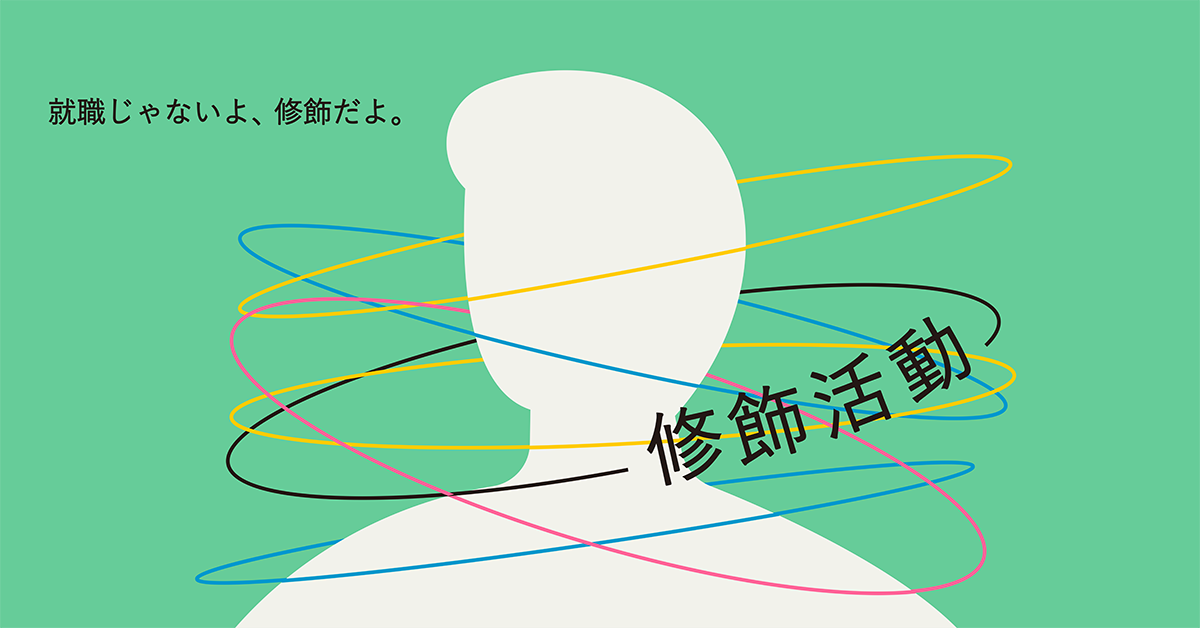<後編>「私たちの舞台は地球だ」と思えるためには。天文学者・縣秀彦さんに聞く、「視野を広げる」ことの必要性
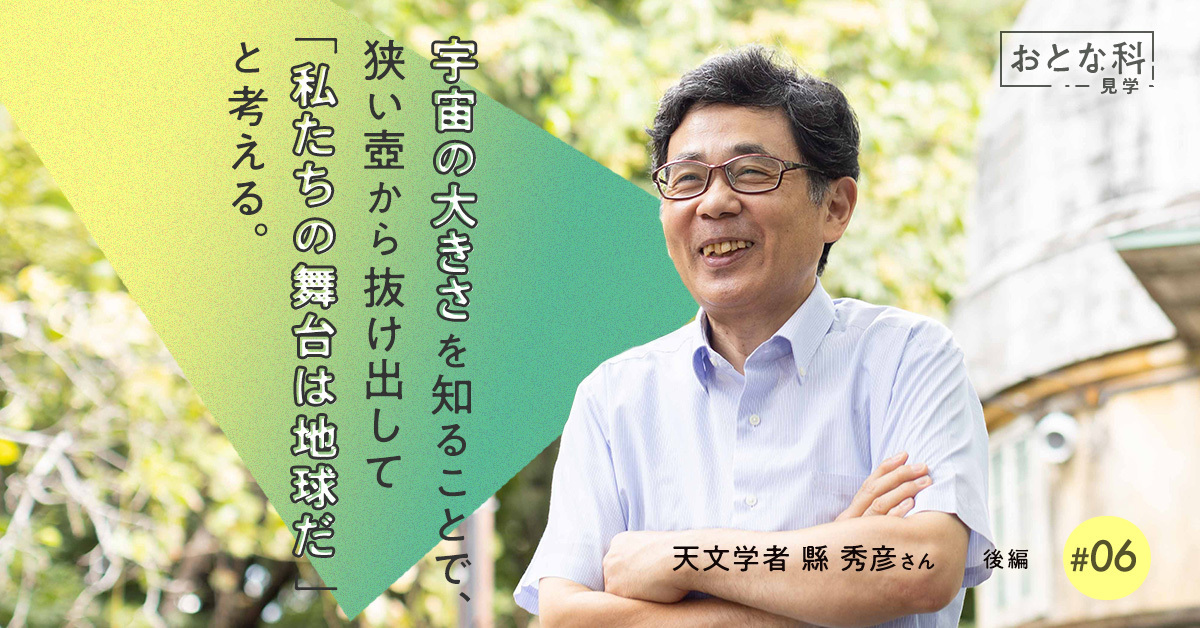
プロフィール

縣 秀彦(あがた・ひでひこ)さん
1961年生まれ。国立天文台 准教授。専門は天文教育と科学コミュニケーション。東京大学教育学部附属中学・高校教諭を経て現職。1999年より現在は研究機関に所属しながら、科学教育研究と科学普及活動を行う。 科学系の博物館、イベント、番組等の企画監修、情報発信活動の経験も豊富。
Q3.いまの時代だからこそ、天文学が役に立つことはありますか?
A.現代はスペシャリストの時代。視野を広げ、「蛸壺化」から脱するために、天文学は役に立つと思います。
いまはすごく便利な世の中になりましたよね。必要な情報を、スマホだけですぐに得ることができる。昔は、星を見ることは直接的に「役に立つ」ことだったんです。自分の現在地を確認したり、だいたいの時刻を調べたり……。でも、いまでは、そういうことは必要なくなりました。
では天文学は、いまの時代でどう生きるか。天文学は「視野を広げる」ものとして役に立ってくれると思います。

いまは便利すぎる時代だからこそ、もう少しそれぞれが視野を広げる必要があると思うんです。みんな「スペシャリスト」を目指しすぎて、どんどん蛸壺化しているような気がしてならないんですね。
たとえば、大学って、学部の細分化がすごいでしょう。少し前の時代では、物理学科とか化学科とか、あってもその下に三つほどカテゴリがある程度だったけど、いまは、ものすごく細分化されている。
仕事でもそうです。「サイエンティスト」というのは19世紀頃に生まれた言葉。その前は「哲学者」とか「知識人」といったような、ざっくりとした分類だったんだけど、次第にそれが細分化して、職業にもかなり細かな名前がつくようになりました。
もちろん、大学生などの若いときは、職能──つまり自分が仕事をするためのスキルとか、キャリアを繋ぐために専門分野を身につける時期でもあるから、細分化は悪いことではありません。でも、広く物事を見渡せる視野がないと危険です。

ゼネラリストじゃなくてスペシャリストな世の中になっている。そうすると、「自分の専門分野以外のことは全くわからない」という状況になってしまう。
そういうことが進んでいくと、仕事だけではなく、普段の生活など、どんな場面でも蛸壺に入ってしまう可能性があるんですよね。
スペシャリストが、思考や気持ちまでスペシャリストになってしまうと、「自分さえ良ければいい」とか、自分の家族、会社、住んでる地域、国さえ良ければいいという風になってしまう。そういう傾向が、いま、社会的には進んでしまっている気がします。
人に対して寛容でなくなっていく。寛容性がない生きものが社会をつくると、社会は破滅してしまいます。

そんな蛸壺化を防ぐひとつの道が、私は天文学にあると思っています。宇宙の大きさを知ることで、広い視点を持つことができる。蛸壺から抜け出して、目線を上げることで、寛容になることもできる。
地球に国境をつくったのは人間ですよね。蛸壺から抜け出て、「私たちの舞台は地球だ」と思えたら、いいなと思います。
これが、いまの時代だからこそ、天文学が役に立てることなのではないでしょうか。

<前編>はこちら
<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:あかしゆか
漫画:都会
撮影:井上 英祐