知る
know

業界&シゴト研究
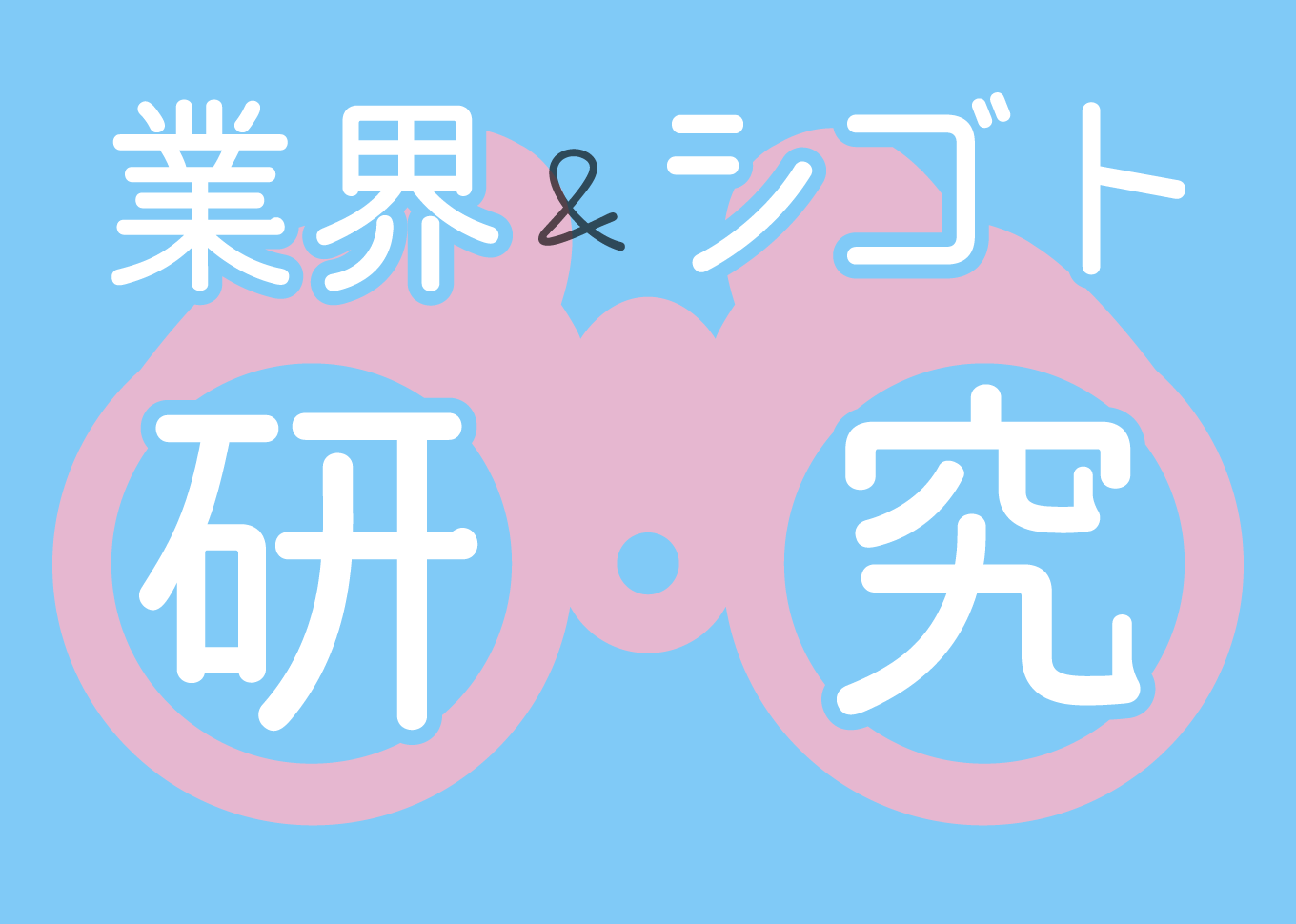
保育所のスケジュールと仕事
保育所の1日のスケジュール
保育士の勤務時間は1日8時間が基本です。ただ、延長保育もあり、早朝や夜など子どもたちが保育所にいる時間には幅があります。その幅に対応するため、ローテーションを組んで勤務することになります。例えば、早番は朝7時から午後4時まで(間に休憩時間を含む)。中番は朝8時から午後5時まで。遅番は朝10時から午後7時まで、というように。土曜日に預かる保育所も多いので、休みも日曜日を基本として、あとはもう1日、週のどこかで取ります。
では、具体的に、保育所の1日のスケジュールはどのようなものでしょうか? これは、子どもの年齢によっても内容が違います。ある日のスケジュールを例にしてみましょう。
ある日のスケジュール例

延長保育(早朝)の子どもがやって来ます。保護者から預かるときには子どもたちの健康状態もチェック。0~1歳児は検温もします。

保育開始。クラスに分かれて遊びます。0歳児と1・2歳児はおやつの時間も入ります。0~2歳のクラスは保育士1人につき子ども数人、3~5歳クラスは保育士1人につき子ども数十人を見守ります。クラスは複数の保育士で受け持つのが基本。

1~5歳児は食事の時間。1時間ほど前に離乳食を取った0歳児は遊び・睡眠の時間です。食事時間は、マナーを教える機会。箸、スプーン、フォークの持ち方や椅子に座る姿勢、挨拶を指導。

食後のお昼寝。年次により睡眠時間やタイミングは異なります。なかなか寝付けない子どもには事前の工夫が大切。保育士も交替で昼食を取り、保育日誌をつけたり職員会議をしたり、有効に使います。

子どもたちが目覚め、おやつや着替え、遊びの時間となります。

保育終了。迎えに来た保護者に連絡ノートを渡し、子どもたちを見送ます。

延長保育開始。保育終了まで、室内遊びを行います。子どもたちが全員帰ったら、園内を掃除して保育士も帰宅します。
“欠けている”保育を補う仕事

保育所で預かる子どもたちは、保護者からの“保育に欠ける”ことが前提ですから、保育所では、不足の部分を補うことが期待されています。その主たるものが、生活習慣を身に付けさせること。基本となるのは、まず、「そうじ・整理整頓」。おもちゃなどを使った後は片付ける習慣をつけさせます。そうじをしてキレイにする=気持ちいい、と感じさせるのです。次は「着替え」。補助から始めて、少しずつ自主性を高めていきます。自分で着替えて、衣服をたたむことができるように指導します。「食事のマナー」は道具の持ち方やあいさつ、さらに好き嫌いなく食べられるような食育の役割も持っています。「手洗い・うがい・歯磨き」は、病気を予防し、清潔な衛生習慣に繋がるものです。「排泄」はおむつを外す練習からトイレの使い方、年長さんなら食事中に行かないなどのマナーも含めて教えます。「睡眠」も体調や生活リズムを整える重要なプログラム。年次によって時間は変わってきます。このように、1日のスケジュールの中に、成長に合わせた生活習慣の指導が組み込まれているのです。
保育所の1年の行事
子どもたちの情操教育の一環として、四季を意識させるために、保育所では年間にさまざまな行事を行います。季節感のある行事のほか、お泊まり会や祖父母の集いなど、年次ごとに異なるプログラムも用意されています。
年間行事例
- 4月
入園お祝い会

- 5月
こどもの日 保護者会
健康診断 遠足
- 6月
歯科検診 お泊り会
プール開き
- 7月
七夕 盆踊り
納涼会
- 8月
プール遊び

- 9月
防災訓練 お月見
祖父母の集い
- 10月
運動会
ハロウィン 遠足
- 11月
芋掘り 秋祭り
保護者会
- 12月
クリスマス会

- 1月
餅つき

- 2月
節分
発表会
- 3月
入ひな祭り お別れ会
卒園式

