20卒
2021年1月12日
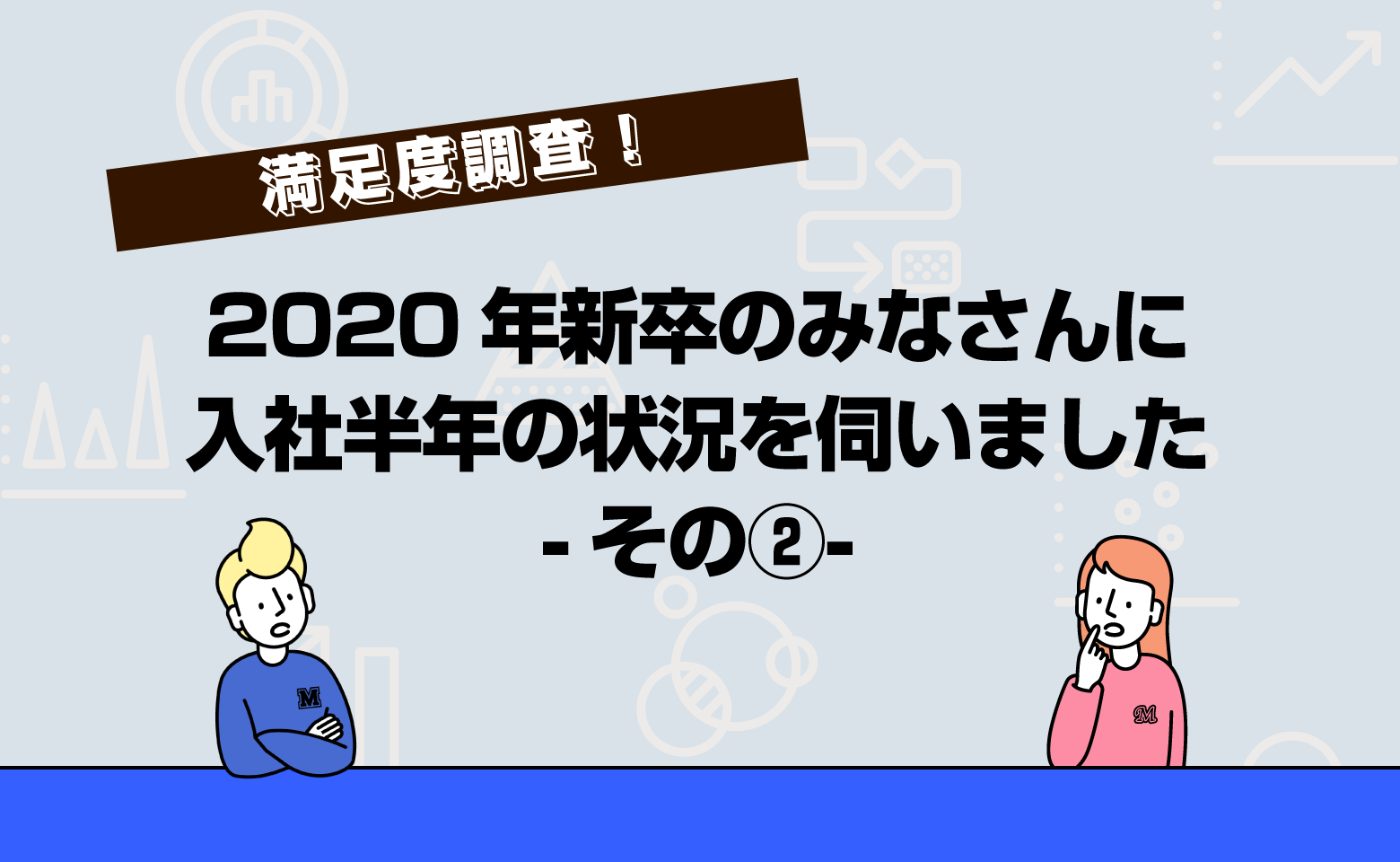
2020年10月調査
<調査概要>
■調査期間:2020年10月12日(月)~2020年10月18日(日)
(就職活動時のデータの調査期間:2019年7月25日(木)~2019年7月31日(水) 「マイナビ 2020年卒 学生就職モニター調査 7月の活動状況」)
■調査対象:2020年卒業予定として就職活動を行い、その状況をモニター調査で回答した方を対象とした追跡調査
(マイナビ 2020年卒 学生就職モニター調査 7月の活動状況」回答時点で大学4年生及び院2年生だった方)
■調査方法:WEB上のアンケートフォームより入力
■有効回答数:893名 [内訳:文系男子 170名 理系男子 253名 文系女子 220名 理系女子 250名]
前回に引き続き、コロナ禍の新卒入社となった2020年卒のみなさんに伺った、入社後半年の状況についてレポートしていきます。
就活準備中に気になることと言えば、インターンシップに参加した企業と入社の関係では無いでしょうか?現在の勤務先のインターンシップに参加していた方がどれ位いたのかを聞いてみると、その割合は33.8 %となっていました。文理で見てみると、文系( 29.1 %)に比べ、理系(41.7 %)の方が高い割合となり、さらに就活時理系学部生だった人は 39.1 %、理系院生だった人は 44.2 %という回答でした。以前の記事で、理系学生のインターンシップ参加目的が「確かめる」であったことも加味すると、専門的に学び、目指す業種や職種が早い段階で固まっている理系のみなさんの参加率が高くなっていたのではと考えられます。
また、インターンシップに参加していた人のうち、 1 回だけ参加したのは 61.2 %、 2 回以上参加したのは 38.8 %と、 4 割弱が 2 回以上参加していたことがわかりました。参加した人の参加日数の平均は 3.8 日で、実習などのプログラムの違いの影響か、理系( 4.3 日)の方が文系( 3.0 日)よりやや参加日数が多くなっていました。
現在の勤務先のインターンシップに何日間参加したか
インターンシップの満足度については、最も高い「満足度5」だった人が 36.0 %、次に高い「満足度4」だった人が44.8 %でした。文理で分けてみると「満足度5」だった人の割合は文系の方が理系より多いという結果となりました。
現在の勤務先のインターンシップの満足度
さて、インターンシップ参加は勤務先への満足度にどの程度影響するのでしょうか。まず、勤務先のインターンシップに参加していた人と参加していなかった人で、「入社予定先の総合満足度」から「勤務先の総合満足度」への変化を比較したところ、どちらも同じように低下しており、大きな差はありませんでした。
次にインターンシップの参加日数別で比較したところ、すべてで満足度が下がっていましたが、「 2 日または 3 日参加」で一番下落幅が大きくなっており、「 6 日以上参加」では、比較的下落幅が小さくなっていました。この結果から見ると、勤務先との接触時間が長い方がミスマッチが減らせると言えるのでは無いでしょうか。
総合満足度比較・勤務先のインターンシップ参加日数別
最後にインターンシップの満足度別「3以下」「4」「5(最も高い)」で比較したところ、「インターンシップ満足度3以下」「満足度4」では、満足度が大きく下がったのに対し、「インターンシップ満足度5」ではあまり下がらなかったことがわかりました。20年卒学生のインターンシップ参加が 2018 年夏~翌春だとすると、その時の満足度が約 2 年を経て入社半年後の満足度に影響していることになります。
総合満足度比較・勤務先のインターンシップ満足度別
要因を見てみたところ、「インターンシップ満足度5」では特に「社員の印象と帰属感」が入社後も高いまま維持されていることがわかりました。多くの企業を見て、比較検討ができる就活準備期間のうちに、様々な企業に触れること、そして「いいかも」と思った企業とは積極的に接点を持ち、イメージと実態の乖離をなくしていくことが入社後の満足度やミスマッチを防ぐのに大切だと言えます。
社員の印象と帰属感比較・勤務先のインターンシップ満足度別
インターンシップの重要性が見えたところで、入社後半年が経過して感じた、「就活時の就職先決定要因」と「今だから感じる就活時に知っておきたかったこと」を比較してみました。
「(就活時に)就職先決定で重要だった情報」は、それぞれ「労働条件」に関わる情報である「給与や賞与に関する情報」( 59.0 %)「福利厚生制度に関する情報」( 55.5 %)「勤務地に関する情報」(54.7 %)がいずれも 5 割を超え高い割合でした。一方の「就職活動時に知っておけばよかった情報」でも、「就職先決定で重要だった情報」で高い割合だった「給与や賞与に関する情報」(23.9 %)「福利厚生制度に関する情報」 (24.3 %)が高い割合となりましたが、最も高い割合だったのは「実際の仕事内容に関する社員の話」( 26.0 %)、次いで「社員の人間関係に関する情報」(23.0%)となりました。「労働条件」に加え「人に関わる情報」について、知っておけばよかったと思うことが多いようです。
就職先決定で重要だった情報と就職活動時に知っておけばよかった情報
これらの結果について、「現在の勤務先総合満足度」が高い人とそうでない人では差があるのでしょうか。ここでは「現在の勤務先総合満足度」が最高の「満足度5」である人と「満足度3以下」の人で比較をしてみました。その結果、「就職先決定で重要だった情報」では大きな差は出ませんでしたが、「就職活動時に知っておけばよかった情報」では明確な差が現れました。
勤務先総合満足度と(就活時に)就職先決定で重要だった情報の関係
勤務先総合満足度と就職活動時に知っておけばよかった情報の関係
特に「実際の仕事内容に関する社員の話」を「知っておけばよかった」とする割合は、「満足度5」では 16.0 %だが、「満足度3以下」では36.3 %で、 20.3pt の差がつきました。また、「自分が成長できる環境があるか」は、「満足度5」では 5.6 %だが、「満足度3以下」では 22.9 %と、17.3pt の差がついています。入社後の仕事や勤務先の環境などに関する情報を就職活動時に得ておけば、入社後のミスマッチを防ぐことができるので、勤務先総合満足度を高く保てる可能性が高いと思われます。
次回の更新では勤務先の満足度と配属の関係や、テレワークの普及で気になる在宅と出社の割合、入社後半年で転職を検討したかなどについてレポートします。