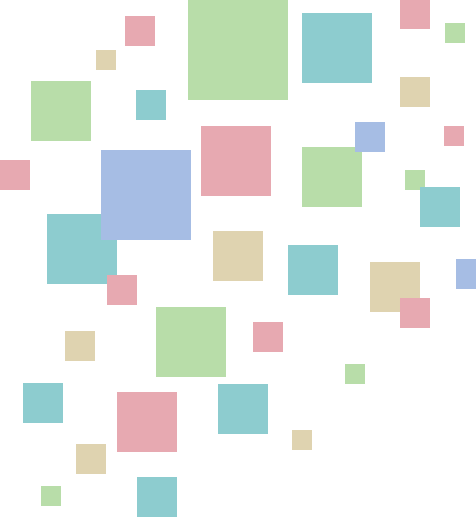福祉の仕事って、偏ったイメージでとらわれがちだけど、
本当は楽しく、経験を積めば積むほど未来の可能性が広がる仕事!
関西福祉科学大学で教鞭を執られている遠藤洋二教授に、
福祉業界の現状やキャリアデザインについてプロの目線から就職活動をする学生の皆さんへの
メッセージをいただきました。


福祉というと介護福祉士やホームヘルパーといった介護職を思い浮かべる人が多いでしょう。そのイメージから、福祉職には4Kというマイナスイメージが定着してしまいました。厚生労働省も専門部署を立ち上げ、消費税10%導入に合わせて予算を担保しようと動き出していますが、介護職においては給与・待遇面で厳しい状況が続いているのは事実。こうした現況の中、福祉を目指す学生にとって最も大切な課題は、キャリアパスが確立した就職先を見極めることです。
福祉職には、介護福祉士に代表される介護職と、人の暮らしを支える社会福祉士(相談援助職)があります。中でも社会福祉士(ソーシャルワーカー)の領域は、高齢者のみならず、児童福祉、少年非行、災害支援などの場において、相談援助という個別支援から地域支援、さらには政策立案までという幅広いもの。そのミッションをひと言で言えば『静かにいのちを守る仕事』です。例えば不登校の児童に対して、その子が何を求めているかを調査(アセスメント)し、どうアプローチしていくかを考え、具体的なサービスを創造していく。この過程はまさに想像(イマジネーション)×創造(クリエーション)。その全てがあなた自身のオリジナルとなるのです。もちろんアプローチに失敗すれば、あなた自身が傷つくこともあるでしょう。しかし自らのアプローチがすぐさま結果となって現れ、「対象者の変化」が確実に見える。ここに福祉の面白さとやりがいがあるのです。

福祉の道を目指す人は「高齢者が好きだから」「人のために尽くしたい」という思いが強い。入り口はこれで間違っていません。介護職として現場を知ることも大事です。しかし若い方にはしっかりとしたキャリアデザインを描いてほしいと思います。なぜなら福祉は、皆さん自身が社会を変えていくことができる数少ない業界だからです。
ソーシャルワーカーの仕事は、個人・家族といったミクロレベルから、集団・施設のメゾレベル、そして地域や国へ政策提言するマクロレベルまで、非常に幅広いものです。しかも活躍の場は、福祉施設や医療機関に留まらず、刑務所から災害支援現場、グローバルな分野では難民支援や疾病予防、発展途上国の教育支援まで大きく広がっています。私は学生によくこう話しています。「官公庁を動かせる人材になれ」と。社会の動きや政治の流れを知り、福祉全体を鳥瞰して自らが政策を立案し、社会を変えるためのロビー活動までを行う。これも福祉職を選ぶ人の大きなの目標であるべきなのです。
キャリアデザインは、皆さん自身のライフデザインそのもの。ロールスロイスやフェラーリに乗るような生活がしたい、という人に福祉の道は勧めません。しかし、人生80年を楽しく過ごしたいなら福祉職ほど面白いものはないでしょう。そしていつか福祉の世界でも、業界のイメージを覆すような風雲児が登場することを願ってやみません。福祉の世界は宝箱のようなものです。皆さん自身で、その宝を見つけてください。