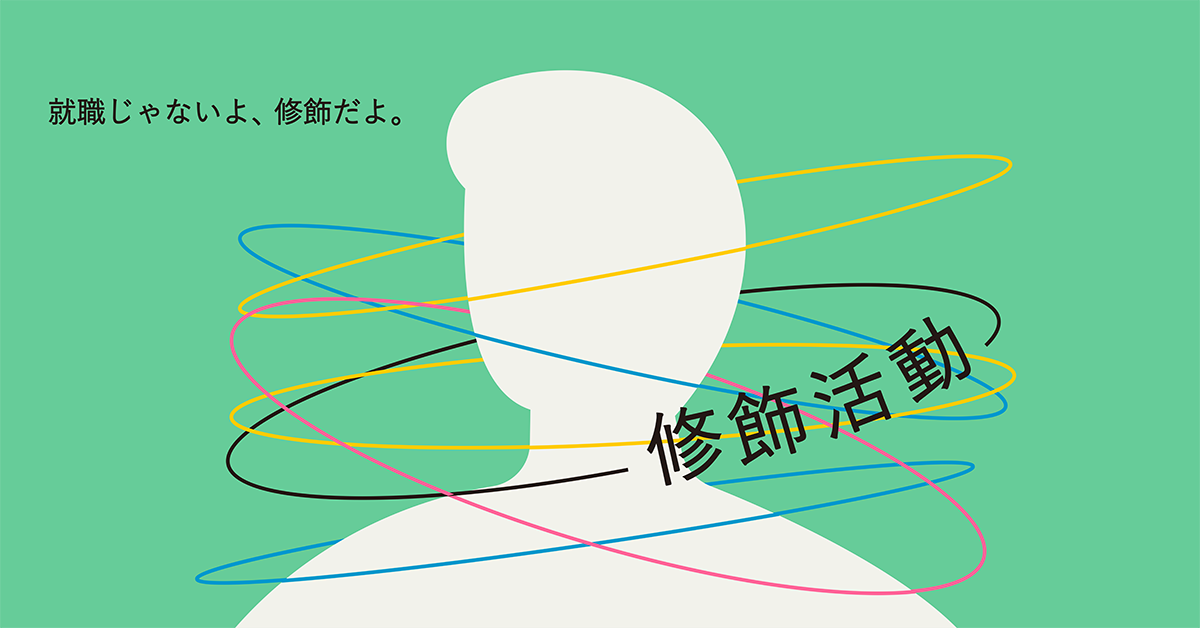<前編>名著とは、現代を読む教科書である。「100分de名著」TVプロデューサー・秋満吉彦さんに聞く、「名著」が持つ力
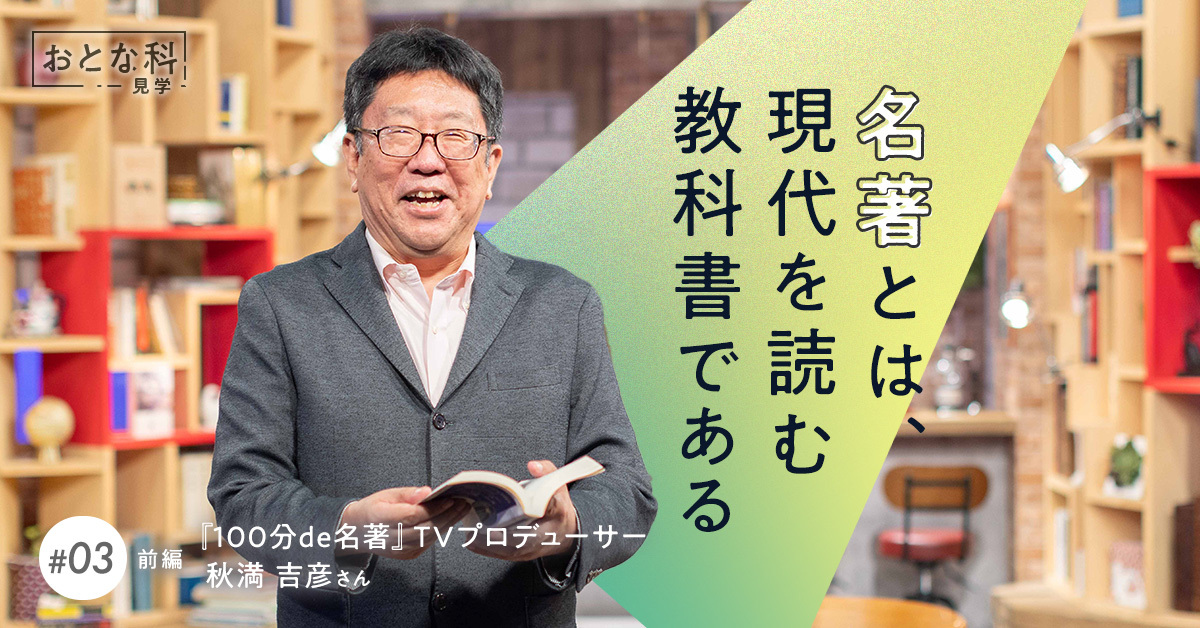
誰もが一度は読みたいと思いながら、なかなか手に取ることができない古今東西の「名著」を、25分×4回=100分で読み解き、紹介する。そんな内容で濃いファンに支持されている番組が、NHK Eテレの「100分de名著」。
今回は、そんな人気番組のつくり方を、番組プロデューサーを務める秋満さんに聞いてみましょう。まずは、この番組が掲げるコンセプト、そして、「名著」とは何か、という質問から始めてみます。
プロフィール

秋満 吉彦さん
1965年生まれ。大分県中津市出身。熊本大学大学院文学研究科修了後、1990年にNHK入局。ディレクター時代に「BSマンガ夜話」「日曜美術館」等を制作。その後、ドラマ「菜の花ラインに乗りかえて」、「100分de平和論」(第42回放送文化基金賞優秀賞)、「100分deパンデミック論」(第48回放送文化基金賞優秀賞)、「100分deメディア論」(第55回ギャラクシー賞優秀賞)等をプロデュースした。現在、NHKエデュケーショナルで教養番組「100分de名著」のプロデューサーを担当。
Q1.「名著」って何を基準にしているのですか?
A.「歴史の風雪に耐えてきた作品かどうか」です。
それだけ多くの人の人生を支えてきたといえる古典には、現代を生きる私たちの悩みや疑問に応えてくれる面がきっとあります。
「100分de名著」では、2011年のレギュラー放送開始以降から数えて、133もの名著を取り上げました(*2023年9月時点)。じつに多くの名著それぞれに対し、この人しかいないだろう、と思える先生に作品の案内人を務めていただき、回を重ねてきた、ということになります。
本番組のコンセプトは、「名著とは、現代を読む教科書である」です。それがどういうことか、お話ししましょう。

近年で反響が大きかった回に、たとえば『資本論』があります。ご存知の通り、19世紀の思想家カール・マルクスが著した長大かつ難解な一冊なので、「いま読んで、はたして役に立つの?」とまずは思ってしまいそうですね。
でも内容に目を向けてみると、じつは、現代に通ずるさまざまな社会思想のエッセンスが含まれているんです。とりわけ、世界的な気候変動に対してどう対処すればいいか、格差社会に対してどう対応するかといった喫緊の課題について、ヒントをたっぷりと読み取ることができる。
同書を取り上げたのは、2021年1月、コロナ禍真っ只中のとき。世界経済が大打撃を受けるなか、いまこそ一部の人の利潤よりも、人々の共有財産である「コモン」を守らなければいけない、そんな考えが『資本論』にははっきりと示されていたのです。
この回を見事にナビゲートしてくださったのは、経済思想研究者の斎藤幸平さん。

番組の企画は、放送のだいたい1年くらい前からつくり始めるのですが、私が斎藤さんにご挨拶したときは、大きな話題を呼んで広く読まれた著書『人新世の資本論』の刊行前。
そのタイミングでも、『資本論』という書物が持っている大いなる可能性を、「こんなにわかりやすくていいの?」と言いたくなるほど明快に説いていただきました。
番組放送時も、その勢いままに、多くの方に届き、普段は「100分de名著」をご覧にならないような若い年代の視聴者層にも届く結果となりました。まさに、これこそ「名著」の力です。
名著とは、ある種の普遍性を有しており、たとえ古い時代に書かれたものだとしても、現代の問題を見据えるために有効な、私たち現代人がどう生きていけばよいかのヒントを与えてくれるんです。
普遍性があるから、どの時代でも多くの人に読まれ、歴史の風雪に耐え得る。それは、それだけ多くの人の人生を支えてきた作品だと言える。

私自身のことを振り返っても、「名著」が人生を変えてくれた思い出があります。
将来の展望もやりたいことも決めきれず、行き詰まりを感じていた大学院二年生のとき、人にすすめられて読んだフランクルの『夜と霧』に目を開かれました。自我ばかり出していたのを改め、自分がこの世界に何を求められているかを真っ先に考えるべきだと教わったのです。
『夜と霧』は、モラトリアムだった自分の背中を強く押してくれて、現在の仕事へ就く道筋をつくってくれました。
自分のためではなく、つねに誰かのため、多くの人のたちのために何かを為そうというのは、いま私が番組づくりに取り組むうえでも、最も大切にしている心構えです。

<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:山内 宏泰
漫画:うえはらけいた
撮影:井上 英祐