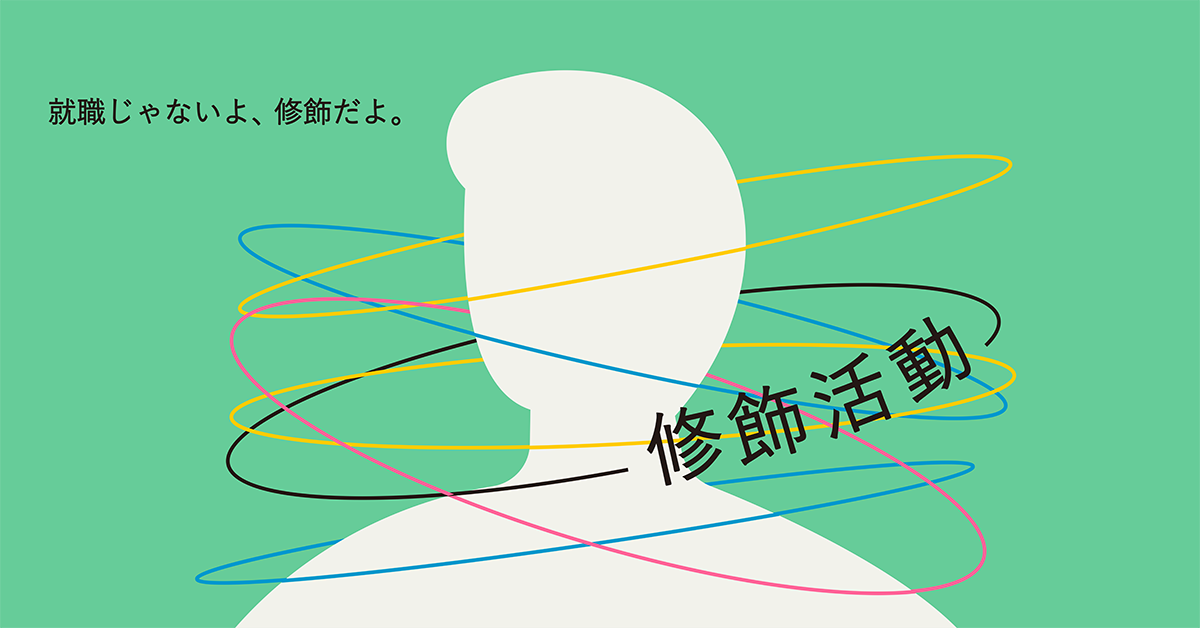<前編>我々はどこから来たのか、我々は何者か。天文学者・縣秀彦さんに聞く、天文学が教えてくれること
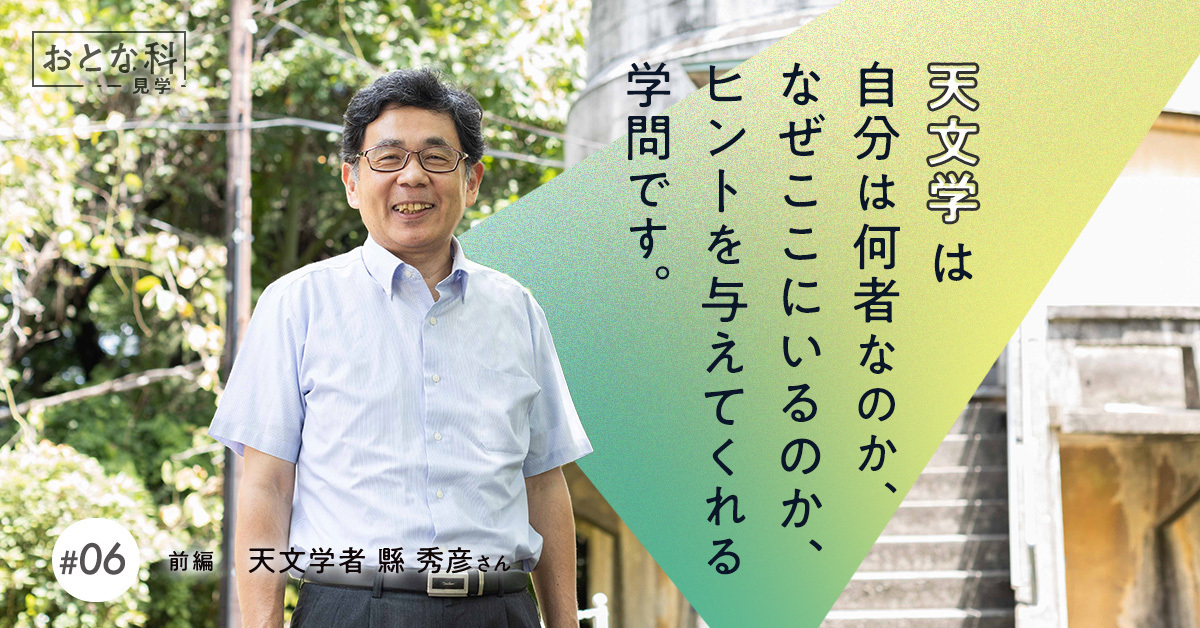
最近、いつ星を見上げましたか? 頭上にいつもある、星や宇宙のこと。1日も欠かさず私たちを見守ってくれる当たり前の存在だけど、じつは、なかなか知らないことが多そうです。
星や宇宙を研究対象にする天文学も同じこと。「天文学って何のための学問なの?」という問いに明確に答えられる人は多くないかもしれません。
いったい、天文学ってどんな学問なのでしょう? 縣さんにお話を聞いてみましょう。
プロフィール

縣 秀彦(あがた・ひでひこ)さん
1961年生まれ。国立天文台 准教授。専門は天文教育と科学コミュニケーション。東京大学教育学部附属中学・高校教諭を経て現職。1999年より現在は研究機関に所属しながら、科学教育研究と科学普及活動を行う。 科学系の博物館、イベント、番組等の企画監修、情報発信活動の経験も豊富。
Q1.天文学って、いったい何をする学問なのでしょう?
A.この世の森羅万象を知り、自分が何者かを探究するための学問です。
ポール・ゴーギャンの有名な作品に、『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』というタイトルの絵画があります。人間は、この絵が伝えているようなことを探究する欲望であり願望を持っている生きものです。それは「知的好奇心」と言えます。
何十年、何百年先と、自分が死んだ後のことまで考えて、将来を憂いたり希望を持ったりする。そんなふうに、過去や未来を考えて生きている生きものは、人間以外には存在しません。

このように、「時間軸」の上で生きているのが人間の素晴らしいところ。そう考えたときに、その時間軸の一番「外側にあるもの」って、結局は宇宙じゃないですか? 宇宙はこの世界全体、つまり森羅万象です。
だから、宇宙について考えることは、「この世の中って、一体なんなの? 私たちはどこからきたの?」を考えることでもある。
知的好奇心を持つ人間だからこそ知りたいと思えるもの。それが天文学なんですよ。
昔の人は、お金持ちになって生活に余裕が出てくると、宇宙について調べようと天文学者を雇って支援をしたそうです。天文学にお金を出す人がいるというのは、「自分自身の存在を知りたい」という気持ちの現れですよね。
天文学を学んでいくと、人間という生きものは、物質としても命としても、また文化文明を継承する主体としても宇宙に繋がっているということがわかります。だから、細かなことまで知る必要はないけれど、ざっくりとでもいいから天文学を学び、「宇宙観」みたいなものを持つといいと私は常々思っているんです。

宇宙観は、人生観や社会観と重なるところがあります。宇宙と自分は決して切り離せるものじゃない、社会と自分も絶対に切り離されたものじゃない。
そう思えると、自分は、この宇宙を作ってきた長い時間軸の中で必要なものなんだと思えるようになる。自分と社会が接続していると感じられる。人はすべからく、とても貴重な奇跡のような存在なんです。
宇宙という壮大なテーマに向き合うと「自分はちっぽけだなあ」と感じることがあります。そう思えることで救われることもある。
一方で、「こんなちっぽけな存在は、いてもいなくても同じ」と考えてしまうこともあるかもしれませんが、じつは逆です。宇宙に比べるとちっぽけな存在、でも、たしかに、貴重な奇跡の存在なんです。
そう思うと、人間が生息可能な地球って、こんなに大切な星なんだ、ということも実感できます。
天文学とは、過去と未来を繋いで、“自分自身の存在をたしかめるため”の学問。自分は何者なのか、なぜ必要なのか、なぜここにいるのか。そういうことのヒントを与えてくれるのが、天文学だと僕は思っています。

<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:あかしゆか
漫画:都会
撮影:井上 英祐