<後編>受け取ってもらえるかわからないけれど、相手を信じて差し出すこと。文化人類学者・松村圭一郎さんに聞く、「仕事」と「贈与」の関係性
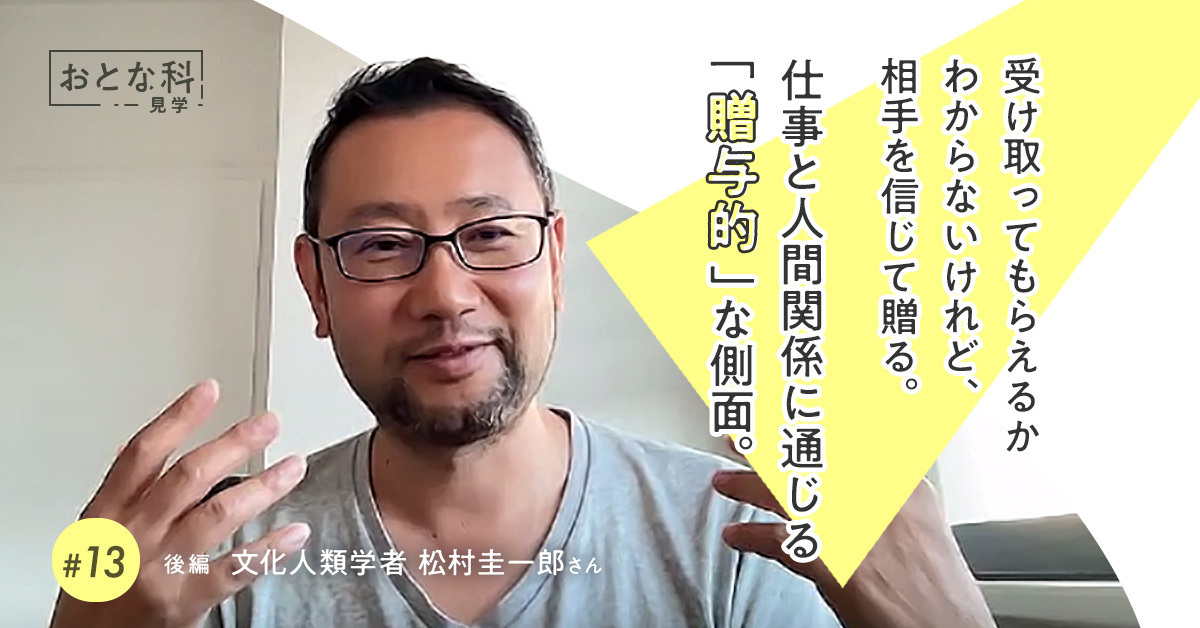
プロフィール

松村 圭一郎(まつむら・けいいちろう)
1975年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。著書に 『所有と分配の人類学』(ちくま学芸文庫)、『これからの大学』(春秋社)、 『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)などがある。
Q3.日々、どんなことを考えながら仕事をされていますか?
A.仕事には「贈与」的な側面があると感じます。贈与とは、収支がゼロにならない曖昧なもの。そして、受け取ってくれるかどうかわからなくても、相手のことを思って差し出すことです。
一般的に「仕事」とは、対価をもらって、そのお金のために働くことだと考えられているかもしれません。ただ、実際に働きはじめると、仕事とは「人間関係」でできていると日々感じます。
それはどんなに仕事が機械化・自動化されようが、きっとこれからも変わらない部分だと思います。人間的なつながりや、感情や、信頼関係。そういうものが、働く中ではとても大事なんです。
たとえば私は、京都にある「ミシマ社」という出版社から本を出させてもらっているのですが、代表の三島さんは大学時代の同級生です。最初、彼に「いつか一緒に本をつくろう」と声をかけてもらって、10年以上かかって、その夢が実現しました。お互いに、あの人と一緒に何かをしたい、あの人の期待に応えたい、という思いが働くうえで大切なんです。

いまではもちろんそれだけではないですが、仕事には、「この人だからこそお願いしたい」とか、「この人の依頼は断れない」と進んでいくことが実際たくさんあります。やっぱり、それは人間関係ですね。
そして、人間関係におけるやりとりとは、お金がもらえるからとか、ギブアンドテイクといった「交換的」なものではなく、もっと曖昧で、人格的な感情や思いを含んだものですよね。そこが「贈与的」だなといつも思います。
贈与とは何かをもう少しわかりやすく説明すると、収支がゼロにならないもの。貸し借りの量がわからない、気にならないような関係性です。誰でも、好きな人に何かしてあげたい、と思うことはありますよね。そのとき、あからさまに見返りを求めたり、きっちり相手にあげた分をとり返そうとしたりしない。それが贈与的な関係です。
そこで、人間関係を「贈与的」でなくて、完全に収支関係を精算するような「交換」にしてしまうと、やりとりが済んでしまえば、人間関係は切れてしまいます。たとえば自分の親に対し、子育てにかかった費用を耳をそろえて全額返した子どもがいたら、その親子関係は途絶えてしまうでしょう。人間関係において、「交換的」に綺麗さっぱり精算することは、関係をやめることとイコールです。仕事に置き換えると、お金を払ってもらったら、あとは相手がどうなろうと知らない、という態度と同じです。
「仕事」も含め、この社会は、基本的には交換的に出来上がっていると私たちは思いがちです。でも、じつはほとんどのことのベースにあるのは贈与的なものなのです。

そして「人間関係」のほかにも、仕事には贈与的な側面があると感じています。それは「受け取ってもらえるかわからないけれど、相手を信じて贈る」という側面です。
私自身の話を例にしますが、私が大学で教壇に立つようになった最初の頃、まったく学生に自分が与えたいと思っていることを受けとってもらえない、と感じていました。自分が学生だったときもそうだったので人のことは言えませんが(笑)、全然授業を聞いてくれないんです。授業さえやっておけば給料は出るので適当に済ますこともできるけれど、それだと、なんだか働いている気になりません。
最近は、「仕事は表現活動と同じだ」と思うようになりました。たぶん多くの人には、自分が相手に働きかけたこと、与えたいと思ったことを「受け取ってもらいたい」という気持ちが強くある。これは文章を書くときも同じですが、私もやっぱり、書いたものを誰かに読んでほしい、と思います。
でも、受け取ってもらいたい、という気持ちがあっても、本当に受け取ってもらえるかどうかはわからない。それでも、相手のことを考えて一生懸命準備して、差し出す。それしかないな、と、気づいたんです。
そして、それを誰かに受け取ってもらえたときに、やっと関係性が結ばれて、お金にもつながっていきます。絵が好きな人が、自分の描いた絵を誰かに買ってもらえて、はじめてそれが「仕事」になるのと同じですね。
このように、大学の授業や文章を書くことを通して、働くことの中心には、まずは自分が与えられるものを相手を信じて差し出すという「贈与」があるのではないかと考えるようになりました。
人間関係のやり取りにある贈与、そして、相手を信じて差し出す贈与。仕事には、このふたつの贈与的な側面があると思っています。
いったい自分は、誰に何を与えられるのか。それを理解するには、自分が何者であるかを知らなければいけません。だから最初にお話したことに戻りますが、自分を知るには他者と出会い、自分を見つめることが大切なんです。

〈松村さん提供〉
<前編>はこちら
<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:あかしゆか
漫画:したら領






