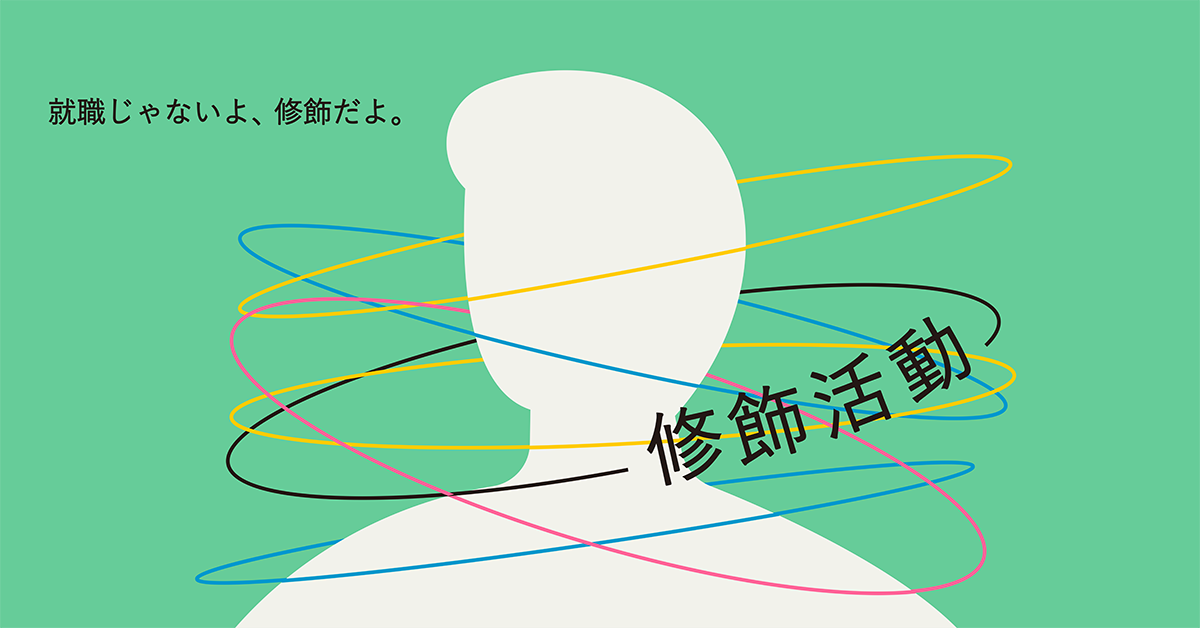業界一覧とそれぞれの特徴を紹介!選び方も就活前に知っておこう
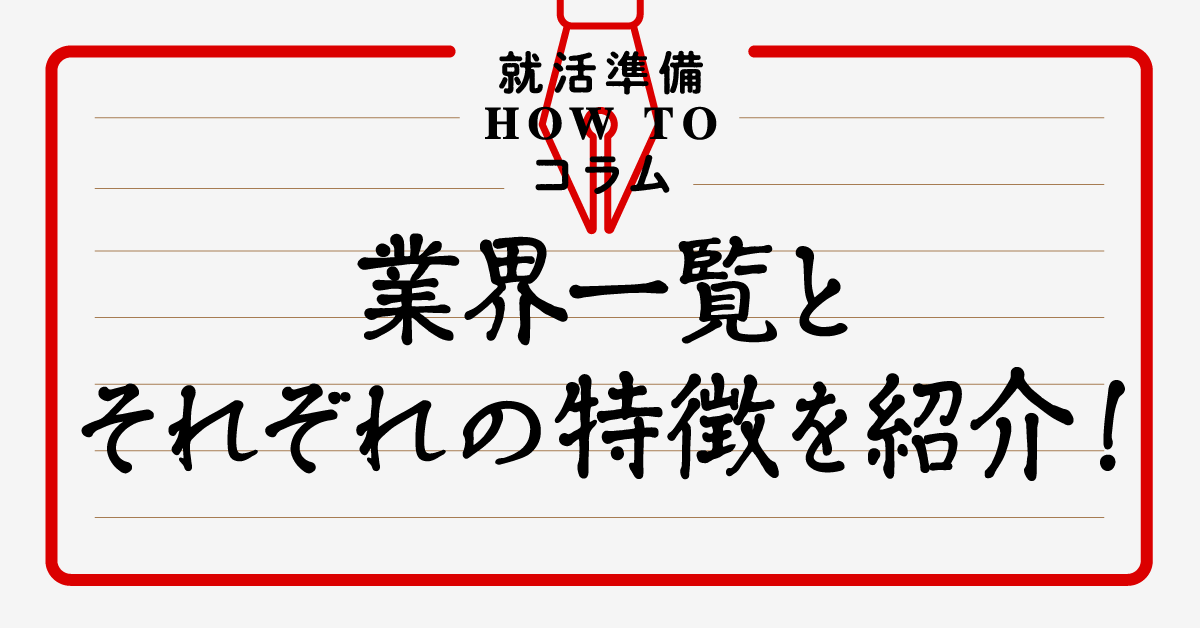
企業を分類する際に「業界」という言葉が使われることがあります。しかし「業界」とは何か詳しく知らないという方も多いでしょう。
そこでこの記事では、業界とは何か、概要とともに「業種」「職種」との違いを解説。さらに、どのような業界があるのか一覧で紹介します。
大学1・2年生のうちに、どのような業界があるのかだけでも知っておきましょう。
Content
業界とは

世の中にはさまざまな種類の企業が存在します。その企業を産業ごとに分類したものが「業界」です。
業界によって扱う商品やサービスの種類が異なるだけでなく、ビジネスモデルにも違いがあります。ビジネスモデルとは、企業が利益を生み出すための仕組みのことです。つまり、業界が異なれば、収益を上げるための手段や戦略も変わってくるのです。
大学3年生の3月以降には本格的な就職活動がスタートします。大学1・2年生のうちにどのような業界があるか知っておくと、自分が働きたい企業を見つけるのに役立ちます。
業種との違い
「業界」と混同されやすい言葉に「業種」があります。よく似た概念ではありますが、業種とは企業が提供する商品やサービスによって分類したもので、業界よりもさらに細かい分類が行われます。
例えば、小売業界に属する企業でも、実際に扱う商品はさまざまです。コンビニエンスストアと百貨店は両方とも小売業界に属していますが、提供する商品やサービスが異なるため、別々の業種に分類されます。
業界と業種の違いを理解しておくと、業界研究や企業研究の際に混乱を避けられるでしょう。
職種との違い
「職種」も「業界」や「業種」と混同されやすい概念の一つです。
職種は、仕事の内容による分類で、研究職・営業職・事務職などが挙げられます。例えばほとんどの業界には営業職の人がいるように、業界や業種を問わず仕事の内容によって分類したものを職種と呼びます。
ただし、同じ職種であっても業界や企業によって業務内容に違いが生じることもあるため、就職活動の際には具体的な仕事内容を確認しておくことも必要です。
また、日本では「総合職」として入社時に職種を限定せず、多くの職種を経験するケースが多いことも知っておきましょう。
業界は大きく8つに分類できる

業界は、大きく以下の8つに分類できます。ここでは、業界の種類と各業界の仕事の内容を紹介します。
- メーカー
- 商社
- 流通・小売
- 金融
- サービス・インフラ
- 広告・出版・マスコミ
- ソフトウエア・通信
- 官公庁・公社・団体
メーカー
メーカーは、ものを作ることを主な仕事としている業界です。
鉄やガラスといった素材を作るメーカー、素材を使って部品を作るメーカー、部品を組み立て製品を作るメーカーなどの種類に分類できます。さらに、すべての工程を自社で行う総合メーカーと呼ばれるメーカーもあります。
材料を組み立てる、加工するなどの方法で商品を作り上げ、作った商品で利益を得るのがメーカーのビジネスモデルです。
具体的にメーカーに属するのは、食品メーカー、電子機器メーカー、スポーツメーカーなどの業種です。比較的、理系の学生に人気が高い業界でもあります。
メーカー業界についてもっと詳しく知る
商社
商社は、部品の調達や商品の販売の面からメーカーをサポートする業界です。扱う商品に制限がない総合商社と、特定の分野の商品のみを取り扱う専門商社に分類できます。
メーカーが商品を製造するためには、さまざまな部品が必要です。また、商品を販売するためには、自社の商品を買ってくれる顧客を探さなければなりません。
しかし、メーカー自身がすべての材料を調達し、販路を開拓するのは非常に大変です。特に、輸入や輸出が必要な場合には大きな労力がかかります。
そこで活用するのが、商社のネットワークです。商社は必要な部品の調達や販路の開拓を行うなどの方法で、商品を販売したい企業と購入したい企業の仲介業務を行います。
最近では、メーカー自身が商社としての業務を行うケースも増えており、メーカーと商社は混同されやすい傾向にあります。
商社業界についてもっと詳しく知る
流通・小売
流通・小売は、仕入れた商品を消費者向けに販売する業界です。スーパーやコンビニのように幅広い商品を扱う場合と、特定の分野の商品のみを扱う場合に分類できます。
卸売業者などから仕入れた商品を店舗で販売するのが流通・小売業のビジネスモデルです。実店舗だけでなく、オンラインで店舗が展開される場合もあります。
また、商品を販売するだけでなく小売店が主体となって商品を開発し、メーカーに製造を依頼する「プライベートブランド」も普及しつつあります。
流通・小売業界についてもっと詳しく知る
金融
金融とは、お金を動かすことを主な業務としている業界です。例えば、お金を貸す銀行や株式取引の仲介を行う証券、個人の信用をもとに支払いを代行する信販会社(クレジットカード会社)などが金融業界に属する業種です。また、生命保険や損害保険などを扱う保険会社も、金融業界に属しています。
業種によって、ビジネスモデルが大きく異なるのが金融業界の特徴です。例えば、銀行は企業にお金を融資して利息で利益を得ているほか、振り込みや送金などの手数料でも利益を得ています。一方保険会社は、契約者が支払った契約金を元手として資産運用を行い利益を得ています。
金融業界に興味がある方は、業種によるビジネスモデルの違いを調べてみるのもおすすめです。
金融業界についてもっと詳しく知る
サービス・インフラ
具体的に目に見えるものでなく、形のないものを提供するのがサービス・インフラ業界です。物流や不動産、ホテル、教育、アミューズメントなどがサービス業界に含まれます。また、電気や水道、ガスなどの生活インフラも同じ業界として扱います。
サービスを提供することで、利用者から対価を得るのがサービス・インフラ業界のビジネスモデルです。文系の学生に比較的人気が高いのも、サービス・インフラ業界の特徴です。
サービス・インフラ業界についてもっと詳しく知る
広告・出版・マスコミ
広告・出版・マスコミ業界は、主に情報を多くの人に届けることを業務としている業界です。書籍を通じて情報を届ける出版、テレビや新聞、ラジオなどで情報を届けるのがマスコミです。
また、広告には街で見かける看板や新聞の折込広告、雑誌に掲載されている広告、テレビCMなどさまざまな形態があります。
出版は、書籍を消費者に購入してもらうことで利益を得るビジネスモデルです。マスコミは多くの人に情報を提供する合間に広告を流し、広告料によって利益を得ています。出版でも、雑誌などでは広告料による利益を得ているケースもあります。
多くの人に商品やサービスを知ってもらいたいと考えている企業と、マスコミ・出版をはじめとした広告掲載企業をつなぐのが広告企業の役割です。
広告企業は出版・マスコミ関連の企業との繋がりが強いといえるでしょう。
広告・出版・マスコミ業界についてもっと詳しく知る
ソフトウエア・通信
ソフトウエア・通信業界は、ITを活用したサービスを提供する業界です。ソフトウエアやアプリケーションの制作、ネットワークの提供、インターネットを通じたサービスの提供、パソコンの構築など、情報通信に関わる幅広い業種を含んだ業界で、IT業界と呼ばれることもあります。
進化のスピードが速く、仕事が多様化しているのがソフトウエア・通信業界の特徴です。AIの進化によって、今後もさらに大きな変化が起きる可能性がある業界でもあります。
ソフトウエア・通信業界についてもっと詳しく知る
官公庁・公社・団体
国や地方自治体、地方公共団体、独立行政法人などは、官公庁・公社・団体としてひとつの業界に分類されます。営利(財産上・金銭上の利益)を目的としないのが、他の業界と大きく異なる点です。
公平に行政サービスを提供することを主な業務とし、人々の生活を支えています。営利企業でないため、民間企業と異なり評価や給与と業績の関連性が低い点も特徴です。
官公庁・公社・団体業界についてもっと詳しく知る
自分に合う業界の見つけ方

大学3年生の3月以降に始まる就職活動では、自分に合う業界を選んで志望企業を決めるケースが多いです。しかし、大学1・2年生のうちに、自分に合う業界の見つけ方を知っておくことで、就職活動をスムーズに進めることができるでしょう。
ここでは、自分に合う業界の見つけ方を紹介します。
業界研究を行う
自分に合う業界を見つけるためには、業界研究に挑戦してみるとよいでしょう。業界研究とは、どのような業界があるかを知り、興味を持った業界について深く調べる作業です。
まずは、気になる業界を見つけ、業界のトップ企業を調べてみましょう。そこからさらに、深掘りして業界に関する情報収集を行います。情報をノートにまとめておくと、複数の業界を比較しやすいためおすすめです。
気になる業界について知識を深めておくことで、自分に合う業界を見つけやすくなります。
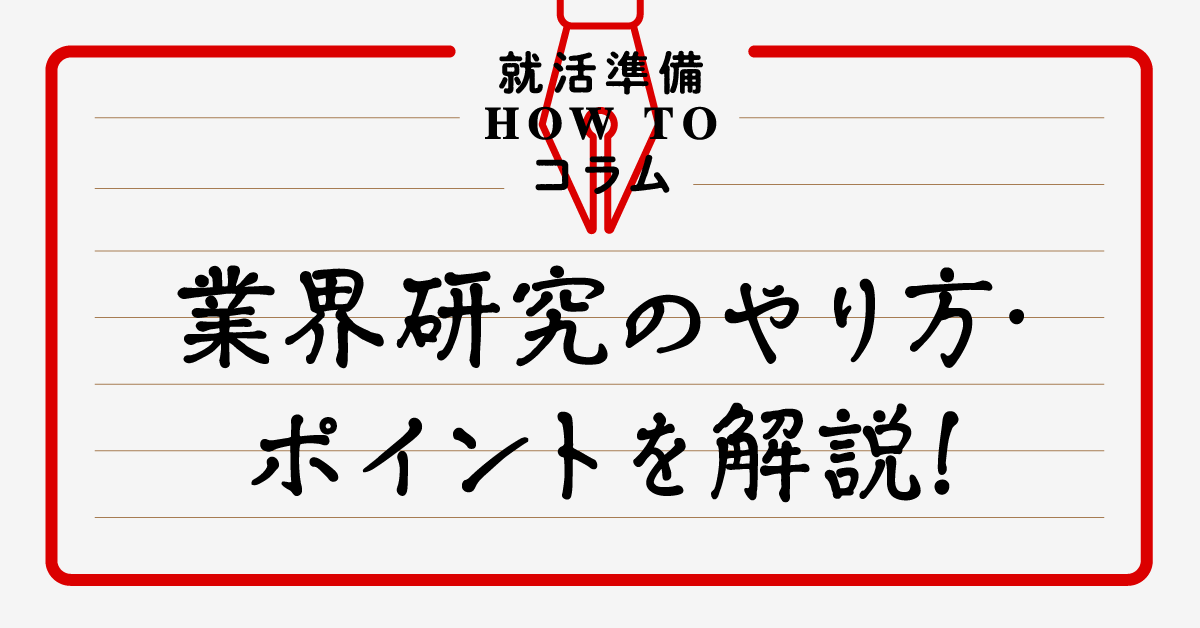
関連記事はこちら
自己分析を行う
自分がどのような業界に向いているか知るためには、自己分析も重要です。
自己分析を行う中で、自分がどのような仕事に興味を持っていて、どのような時に喜びややりがいを感じるのかが分かってきます。分析結果をもとに、自分がやりがいを感じられる業界はどのようなものか考えてみると、自分に合う業界が見つかりやすいでしょう。
さらに、自己分析を行うことで、自分に合う職種を見つけられる可能性も高まります。
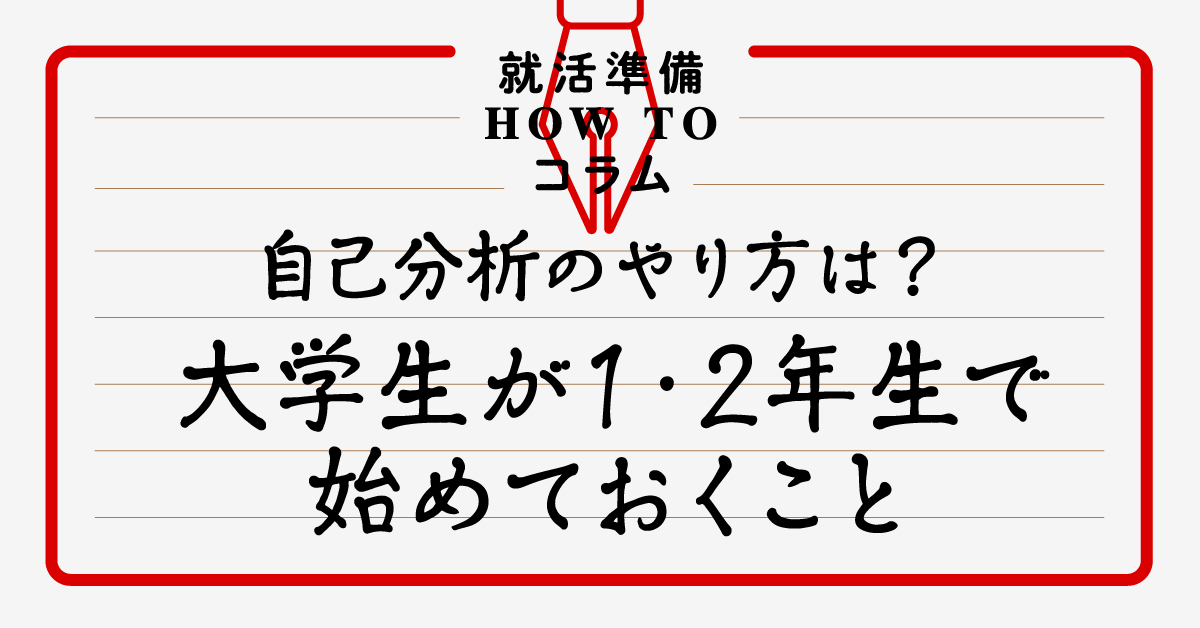
関連記事はこちら
8つの業界を知っておこう
業界とは、世の中にあるさまざまな企業を産業によって分類したものです。大きく分けて8つの業界があります。
8つもあるとどこから知ればいいか迷うかもしれませんが、まずは興味のある業界からためしに見てみるのでOKです。知ろうとすること、調べるという行動をとってみることが何よりも大切です。8つすべての業界に詳しくなる必要はないですが、概要は把握しておくようにしましょう。
また、興味がない業界は「なぜ興味がないのか?」という理由をハッキリさせておくことも大事です。興味がない理由が分かると、裏返して「興味があること」が見つかったりもします。
大学3年生の3月以降に就職活動が始まると、自分に合う業界から企業を選び、選考を受けることになります。大学1・2年生のうちに業界についての知識を深めておくと、就職活動をスムーズに進められる可能性が高まります。
まずは業界研究や自己分析を行い、自分に合う業界はどのようなものか考えてみてはいかがでしょうか。