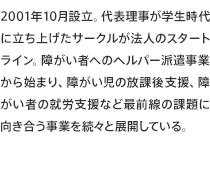みなさんが手掛ける事業について教えてください
- 永野
- 阪南福祉事業会は児童養護施設を運営しており、遺棄や虐待、父母の死亡などにより親と暮らせない子どもたちに家庭の代わりとなる場を提供しています。現在は児童養護施設が事業の核になっていますが、社会状況に応じて、必要とされる事業、施設は変わりますから、私たちも今後、変化する可能性は大いにあると思います。
- 桝谷
- そうですよね。み・らいずも最初は障がい者へのヘルパー派遣から始まりましたが、多くの人と関わるなかで学習支援や就労支援、不登校や引きこもりの子どもたちへの対応の必要性を感じ、事業が広がってきました。必要とされているけれど、今ないものをつくっていくというのが私たちのコンセプトになっています。
- 山本
- おおとり福祉会は高齢者介護に長く携わっている法人です。特別養護老人ホーム朗友館の開設に始まり、複合型施設、老人保健施設、グループホームなど施設を増やし、高齢者、そのご家族が抱える不安や課題の解決にあたってきました。お二人がおっしゃるように、目の前のニーズに応じて変わるというのは高齢者介護の分野においてもあてはまると思いますね。


- 辻
- そう言う意味では、私たちが携わるのは保育事業なので提供するサービスは明確ですが、保育方針は変わってきたと言えるかもしれません。6~7年前から「ピラミッド・メソッド」をベースにした教育を取り入れ、主体的に行動できる子どもを育ててることに注力してきました。ただ、メソッドを導入するだけで変わるわけではなく、保育者も保護者も考え方を変えなければならない…変わることに最初は反発もありましたね。
- 永野
- 例えば、どんな反発があったんですか?
- 辻
- これまで通りのやり方なら、すべてスムーズな流れに乗ってできていたことが、変われば立ち止まり、考えなければなりません。メソッドを取り入れるメリットは分かっていても、多忙な中、新しいことに挑戦するのはとても大変なこと。初めは理解してもらうのが難しかったです。でも、今では保育士の方が創意工夫しながら楽しんでメソッドを実践してくれて。むしろ私が教えてもらっているほどです。
それぞれの現場で課題となっていることはありますか?

- 辻
- 2015年度から新たな保育制度が導入され、保育所の置かれる状況も変わります。幼稚園と保育所が一体化した認定こども園も始まりますし、私たちも福祉と教育の狭間で揺れているというのが現状でしょうか。いずれに軸足を置くにしても、保育士の数が圧倒的に足りないというのが課題です。2017年度までに40万人分の施設をつくると政府が発表していますので、人材確保は今後さらに厳しい状況になるでしょうね。
- 山本
- 介護の現場も同じです。超高齢社会に突入し、私たちだけではなくどの施設も人手が足りない状況だと思います。そこを補ってもらうためにこの業界では外国人の採用も行っていますが、私は国籍が違っても理念さえきちんと理解してもらえれば提供する介護の質は変わらないと感じています。むしろ彼らの持ち前の明るさに場の空気が和むこともあると思います。
- 桝谷
- 実はおおとり福祉会さんとみ・らいずはご縁があって、私たちが関わっている引きこもりの方たちの社会復帰の場として協力していただいているんです。彼らが介護の現場で働けるようになるまでは相応の時間が掛かりますが、自立したいという思いに共感し、受け入れてくださる場所があるというのはとても心強いです。
- 永野
- 今、保育、介護の現場で人材が不足しているというお話がありましたが、それは私たちも同じです。実際問題として成り手が少ないというのもありますが、対象者が必要とする、しないに関わらず、一元的に均一なサービスを提供しようとするから人が足りなくなるのではないでしょうか。もう一歩踏み込み、何が必要とされているのかを把握できれば適切な人に適切なサービスがいきわたると思いませんか。

では最後にみなさんが携わる事業の魅力、求める人材を教えてください
- 桝谷
- 学生サークルから15年やって来て、本当に楽しくて面白かったというのが本音です。でも、私たち創設メンバーだけが旗振り役で、後から入ってきた若手はそれに従うだけ…というのはちょっと違うのかなと。「上の人が言うんだから、いいことなんだ!」と去年と同じことを繰り返すだけでなく、常に“なぜ”という気持ちを持って取り組んでほしいと思いますし、そう思える人と働きたいと思っています。
- 辻
- 今、福祉を取り巻く環境はどんどん変わっていますからね。
- 桝谷
- そうなんです。私、今日みなさんのお話を伺って、これからの福祉業界は変わるぞ、もっと面白くなるぞと改めて思いました。だからこそ、多様な考えを持つ人に来てほしい。色々なバックボーンや視点を持ち、そこから問題解決していこうと考えられる人がいいですね。関わるのは親でも兄弟でもない自分とは関係のない人たちだけど、でもその人たちが困っている、苦しんでいると思うと心がざわついて居ても立ってもいられない。そんな気持ちに共感してもらえる方とお会いしたいと思っています。
- 永野
- 多様性って今の福祉業界のキーワードですよね。私自身も法学部出身なんですが、うちの施設で今とても活躍してくれている職員も商学部卒。福祉の専門知識があることももちろん役に立ちますが、色々な視点を持ち、多様な個性や考え方を受け入れられる人は福祉業界でも必ず活躍できると思います。世の中には色々な仕事があって、なかにはこれは人の役に立つことなのかと思うものもあるでしょう。でも、児童養護施設での仕事は絶対に人の役に立つ、正しいことをしていると胸を張れる仕事です。他人を喜ばせることを自らの幸せと考えられる人、仏教の教えを借りていうならば「自利利他」の精神を持つ人ならきっとやりがいを感じてもらえると思います。
- 山本
- そうです、福祉の仕事には「ありがとう」という感謝が溢れています。高齢者の方と接していると、介護している側なのにまるで自分が諭されているような、教えられているような気持ちになることが度々あります。介護を通じて「ありがとう」と言われることが自分自身を成長させてくれるんでしょうね。人の役に立ちたいと思える方なら、介護の仕事を通じて人として大いに成長できると思います。
- 永野
- だからこそ、就職活動には真剣に取り組んでもらいたいですよね。施設見学もせずに受けにくるなんて、それはもう働くことをあきらめているとしか思えない。仕事は自分でいくらでも面白くできるものなんだから、その法人にそれができる環境があるかどうか見てやろうぐらいの気概を持ってほしいと思います。
- 辻
- 私も同感です。一緒に働く人には理念にも教育方針にも共感してもらって、「やってみたい」と思って入職してもらいたい。だから、ぜひ見学にも来てほしいですね。保育士という仕事は6年間という長い時間を掛けて人を育てていく仕事です。自分のしたことがすぐに結果に表れる仕事ではありませんが、人格形成において重要な時期に関わる保育は未来に羽ばたく人材を育てる仕事とも言い換えられます。結婚・出産・育児など自分自身の人生とのバランスをどう取ればいいのかと考える方もいるでしょうが、そんな経験がまた活かせる仕事でもあるので、あきらめず挑戦してほしいと思います。
- 山本
- 自分を犠牲にして尽くすのではなく、仕事を通じて自分の人生もより良くする。そんな風に考えてもらいたいですね。
- 桝谷
- 自分が動けば動いただけ現状が変わり、逆に動かなければ変わらない。自分が動くことで誰かの人生が良いほうに動き出す。責任もあるけれど、福祉は本当にやりがいの大きい仕事だと思います。みなさんもぜひ一緒に働いてみませんか!