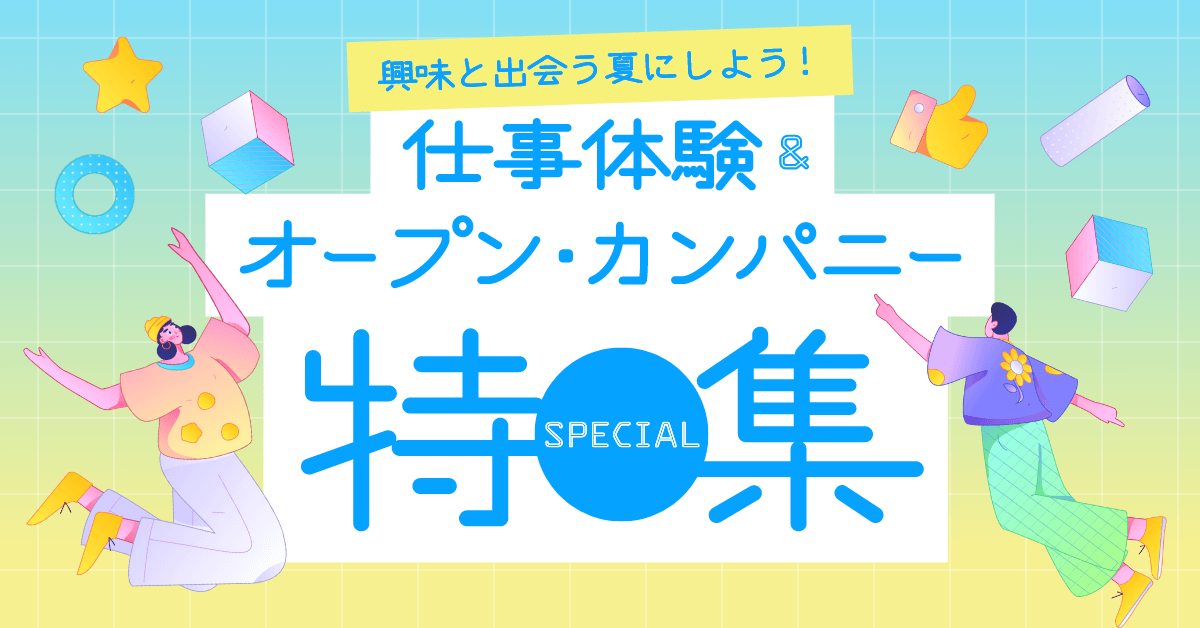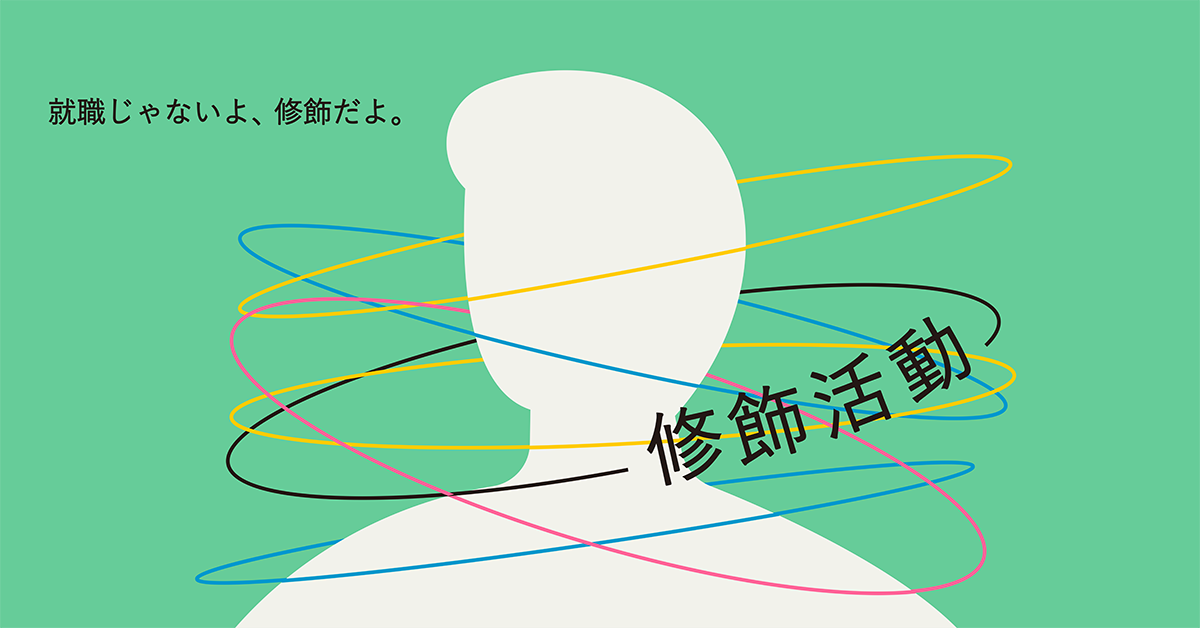<後編>あなたが断っても、きっと世界は変わらず回っていく。小説家・朱野帰子さんに聞く、「断る力」の身につけ方

プロフィール

朱野 帰子(あけの・かえるこ)さん
1979年東京都生まれ。2009年、『マタタビ潔子の猫魂』で第4回ダ・ヴィンチ文学賞大賞を受賞。2015年、『海に降る』がWOWOWでドラマ化される。2018年に刊行した『わたし、定時で帰ります。』が注目を集め、TBSでドラマ化されたことでも大きな話題に。他の著書に『科学オタがマイナスイオンの部署に異動しました』、『対岸の家事』、『くらやみガールズトーク』などがある。
Q3.断ることが苦手です。どうすればうまくなりますか?
A.断るのは「相手のため」だと考えましょう。あなたが断っても、きっと世界は変わらず回っていきます。

以前、「断るのは相手のため」という言葉を聞いたことがあるんです。特に最近になって、その言葉が本当だってわかるようになりました。
やりきれない仕事を断らずに受けた結果、たいした納品物が作れなかったり、相手に結局納期を伸ばしてもらうことになったりとか、無理をして仕事を受けると、だいたい相手に迷惑をかけてしまうんですよね。
だから、断るのは相手のため。断ることが苦手な人は、相手のために断っていると思ったらいいと思います。それでいいんです。

断るときって、「自分が断ったらその人は困るんじゃないか、悲しむんじゃないか」と罪悪感を感じてしまうことはありませんか? 以前、カウンセラーの先生にそのことを相談したら、「それは幼稚な万能感だ」と言われたことがありました。
その先生は、「あなたがいなくても人には幸せに生きていく力があるのだから、その人の運命をまるで自分で握っているかのように考えるのは、幼い考えですよ」と言っていて。「自分が見ていたから野球が負けた」みたいに思ってしまう例がわかりやすいかもしれませんが、そんなはずはありませんよね。
自分は世の中にそこまで影響を与えていないということに気づいた方がいい。そのことにすごく納得をしたんです。
極端な例ですけど、人間って、胃を切っても生きていけるよ、と言われたこともあるんですよ。自分は胃のように絶対に必要な存在なんだと思ってみんな生きていると思うんですけど、自分がいなくても社会や組織は回っていく。だから、自分を特別視しない。
厳しく感じるかもしれませんが、それが病まないため、そして断り上手になるためには必要な視点なのだと思います。

あとは、自分が断らなくていいように、そもそも「望む仕事」がくるように工夫することも必要です。
昔は、私にも、「なんでこんなに、私が望んでいるわけでもない仕事がくるんだろう?」という悩みがありました。
でも、前の記事でもお話したように、一度キャパオーバーになってしまったときに自分の「ミッション」について考えて、自分自身が「労働小説家」であるということを自覚して発信するようになったんです。
そうすると、労働系の小説や本の書評依頼が増えたり、執筆の依頼も「会社員のオフィスもので」という感じで、望む仕事が集まってくるようになったんです。そうすると、断らなくてすみますよね。

最近、私は収納に興味があるんですけど、収納ではよく「住所を決める」ことが大切だと言われます。本を置く場所、掃除道具を入れる場所……。
「住所」を決めておくと、家族も勝手に片付けてくれるようになるんですよ。でも、住所が定まっていないときには、みんなが思い思いの場所に直してしまってなかなか片付かない。
それは仕事でも同じなのだと思います。ミッションを定めて、「ここに、労働ものが書きたい作家がいます〜!」ということをずっと言っていると、自然と集まってくるんです。これは、私が40代になってようやくできるようになったことでもあるのですが。
20代のときには、「私はこれで生きていきたいです」と言い切ってしまうことが可能性を狭めることにもつながるので、これは学生さんにとってはもう少し先の話なのかもしれません。
「断るのは相手のため」という視点、そしてゆくゆくは「自分の住所を定めること」。断る力も身につけて、みなさんがそれぞれの望んだ仕事に近づいていけたらいいですね。

<前編>はこちら
<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:あかしゆか
漫画:一秒
撮影:菊田 香太郎