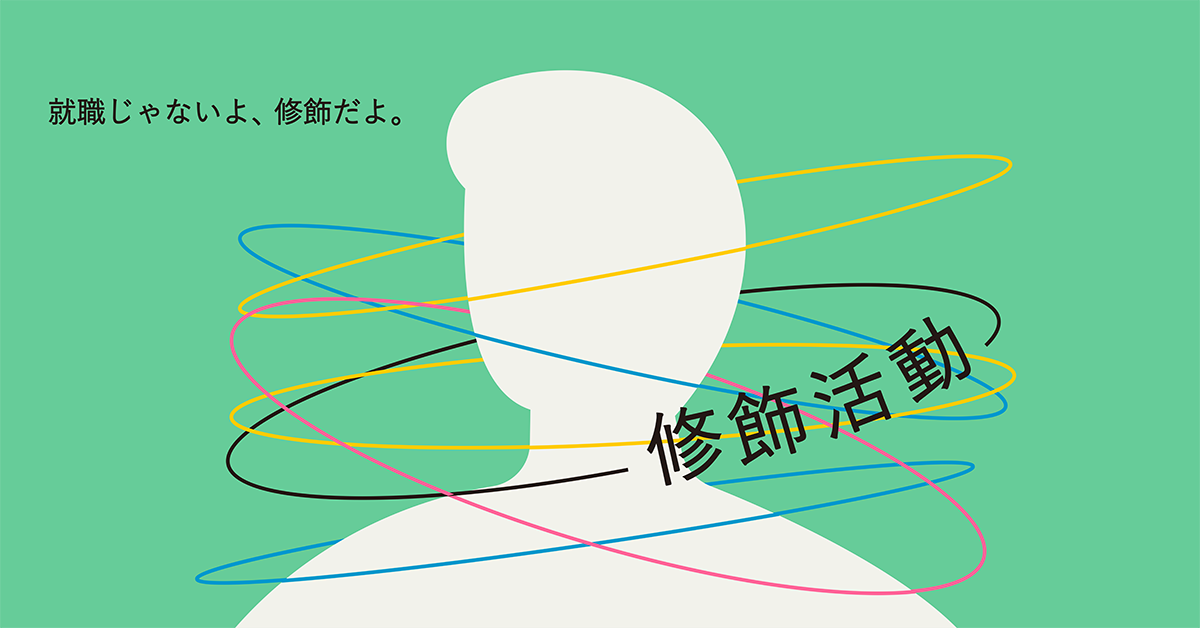<後編>「走らせてもらっている」にたどり着く、チームへの思いと想像力。東洋大学 陸上競技部・酒井俊幸監督に聞く、駅伝にある 「誰かのため」という境地

プロフィール

酒井 俊幸(さかい・としゆき)さん
東洋大学陸上競技部(長距離部門)監督。 1999年東洋大学経済学部経済学科卒。 東洋大学陸上競技部キャプテンを経て、コニカ(現・コニカミノルタ)に入社。 引退後は、母校である学校法人石川高等学校にて教員として陸上部顧問を務めた。 2009年より東洋大学陸上競技部長距離部門の監督に就任。箱根駅伝、全日本大学駅伝、出雲駅伝などでチームを数々の優勝に導く。世界レベルで活躍する選手たちを多数育成。
Q3.チームづくりに主体的に参加したいです。どんな心構えが必要ですか?
A. 自分の役割を見出して、人のために動くことです。
駅伝で勝敗を分けるものは何でしょうか。決して、選手個々のベストタイムを足したものではありません。チーム力によって、確実に明暗が決まります。
では、チーム力を高め、結果を出し続ける集団となるために必要なものとは何でしょう。

まずは、指導者がチーム・選手への情熱と愛情を持つことです。指導者が冷めたときには、チームが強くなる見込みはありませんし、絶対に勝てません。
さらには、その熱が、スタッフや選手の一人ひとりに伝播していること。指導者のひとりよがりでは意味がありません。
また、大学競技でいえば、指導者である監督以外のマネージャーやコーチ、それに大学組織の役割分担が大切です。監督がひとりでスーパーマンになって、何でもこなすなんて無理です。
チームマネジメントは体制づくりなので、黒子役や、ときに嫌われ役を買って出てくれるメンバーもいる必要があります。
「自分たちのチームはうまく回っている」と皆が実感できていて、指導者がいないときでも、充分にやっていける組織状態にあることが理想です。そして、人が変わってもマネジメントができるような組織であり続けるために、組織という「型」をつくらないといけません。

選手たちにも、一人ひとりに明確な役割を与え、やり遂げてもらいます。
箱根駅伝に出場できる選手は10人ですが、往路・復路、またどの区間を走るかによっても、戦略的な役割は大きく違ってきます。レース前にはそれぞれの選手に、チームが勝つために担ってもらいたいことをわかりやすく説明します。
戦略上の役割と、チーム的なマネジメントの役割は違います。走者以外のメンバーにも、さまざまな役割を普段から任せます。
例えば、チームに元気がないときは、ある部員には、朝練前に自主練する背中を他のメンバーに見せてほしいと伝えることもありますし、また別の部員には、チームの皆のテンションを上げるために積極的に周りに声をかけてほしい、と伝えることもあります。それは走者であることに関わらずチーム的な役割を任せている、ということです。
私のチームでは、全員に「一人一役」を実践してもらう。それによって個人の力もチーム力も向上します。役が人をつくるといいますが、これは本当です。

私が指導しているのは大学競技なので、勝負に徹するとともに、教育という要素も入ってきます。競技を通して、チーム・組織の中で、個人としてどう振る舞えばチームに貢献できるのか、人のために動くとはどういうことかを学んでもらっているつもりです。
「働」という漢字が「人」と「動」の組み合わせでできているように、「働く」って、誰かのために自分が力になるということですよね。人のために動くことで、だれもが、自分の働きができるようになります。

「誰かのために動く」というのは、まさに駅伝と同じです。走る選手だけでなく、裏方や走らないメンバーも含めて、駅伝のレースをつくります。走らない選手の役割ってすごく大事なんですよね。
チームのため、仲間のため、応援してくれる人のため、さらに、競技の舞台をつくってくれる方々や主催してくれる学生のため。
そういう裏舞台を想像できるようになってくると、選手は、「皆を代表して走ってやるんだ」じゃなくて「走らせてもらっている」という感覚になってくる。そうすると、ほんとうの感謝が生まれてきます。
そうなってこそ、大舞台で力を発揮できる選手とチームができあがるんだと思います。
<前編>はこちら
<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:山内 宏泰
漫画:まるいがんも
撮影:菊田 香太郎