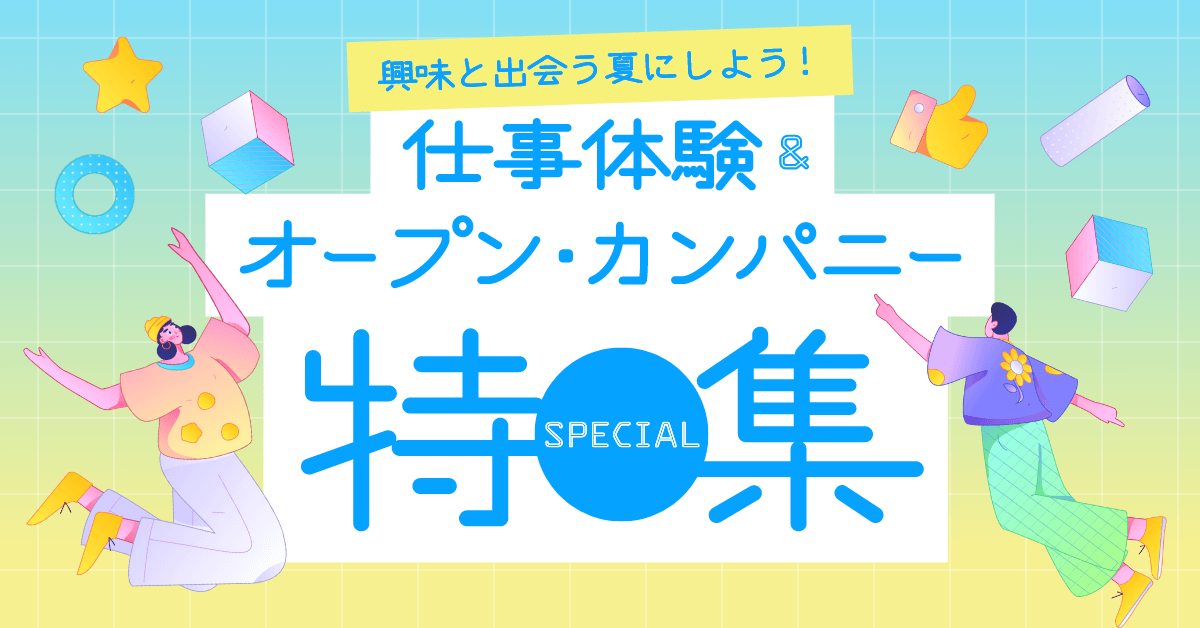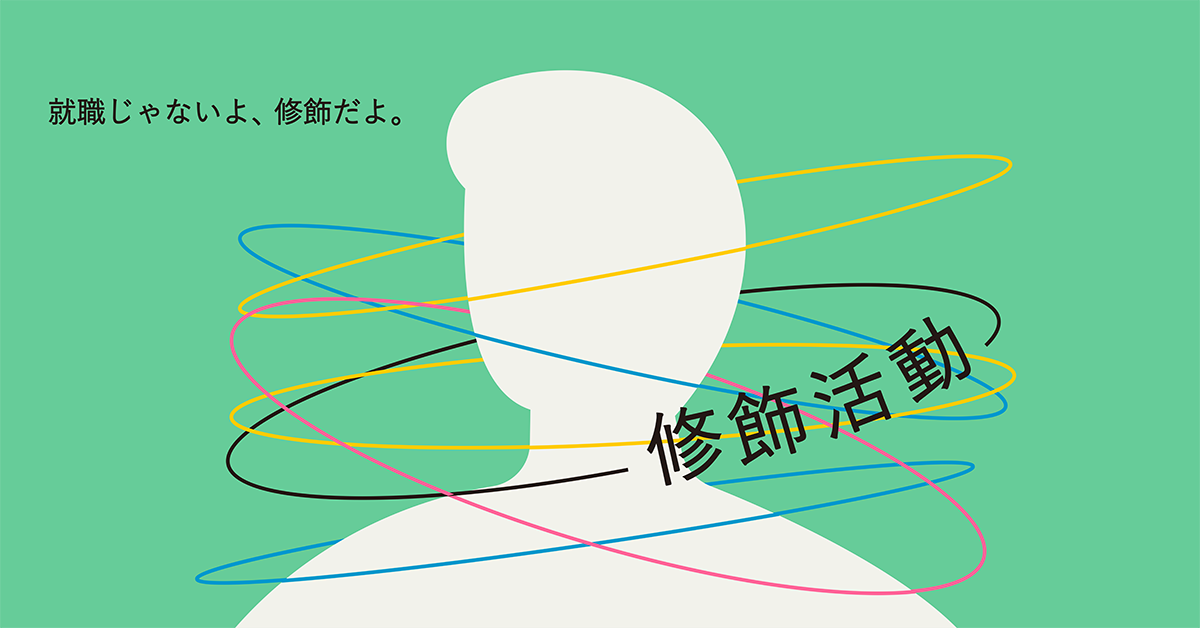<前編>フィクション作品の会話例こそ、思考実験を展開するのにぴったりなんです。言語哲学者・三木那由他さんに聞く、会話を紐解くふたつの現象
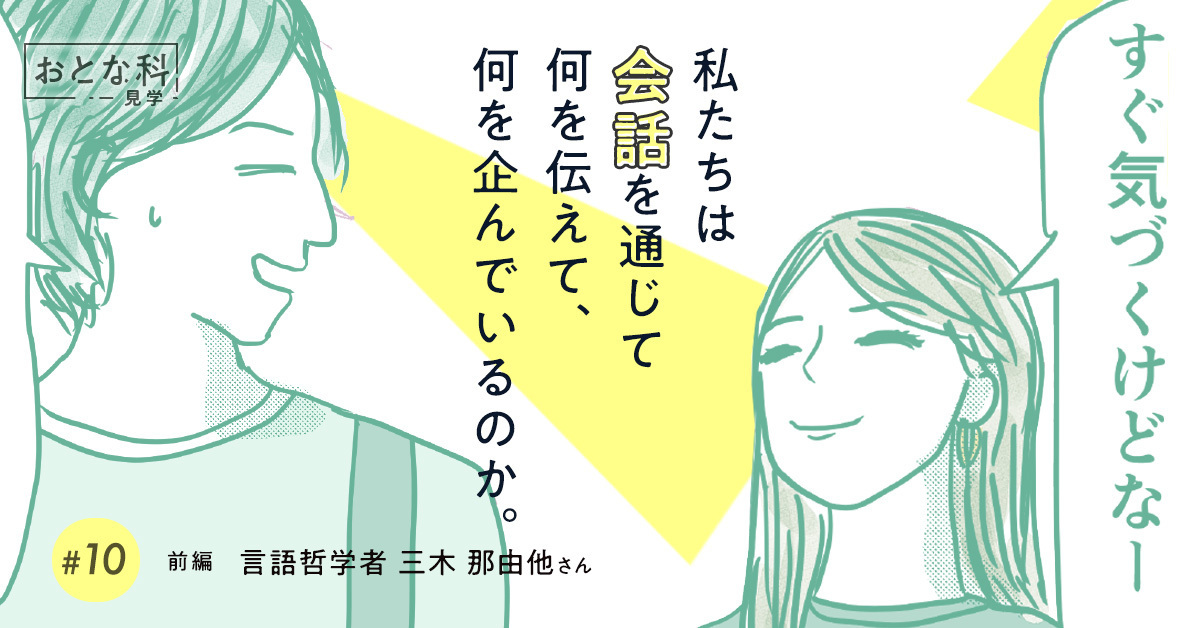
昨年秋、新書『会話を哲学する』が大きな話題を呼びました。本書が、フィクション作品を例に紐解いたのは、「会話」を構成する要素とは、コミュニケーションとマニピュレーションのふたつである──ということ。
そういわれてみると、私たちが日々交わしている「会話」って、いったい、どんな営みなのでしょうか? そして、フィクション作品に登場する会話の強みとは。
本書の著者であり、分析哲学という視点から、言語や会話について研究する三木さんにお話を聞いてみましょう。
プロフィール

三木 那由他(みき・なゆた)さん
大阪大学大学院講師。専門は分析哲学、特にコミュニケーションと言語の哲学。著書に 『話し手の意味の心理性と公共性』(勁草書房、2019年)、 『グライス 理性の哲学』(勁草書房、2022年)、 『言葉の展望台』(講談社、2022年)、 『会話を哲学する』(光文社新書、2022年)がある。文芸誌『群像』とウェブメディアRe: Ronで連載中。大学院への出願も歓迎しています。 https://researchmap.jp/nayutamiki
Q1.マンガ作品のセリフを研究・分析対象にするのはなぜですか?
A.フィクション作品の言葉って「思考実験」に使いやすいんです。
私は言語哲学という分野で、言葉とコミュニケーションの研究をしています。私たちは会話を通じて何を伝えて、何を企んでいるのか。会話がおこなわれているとき、そこでは何が起きているのか。そうしたことを明らかにしようと、日々考えを巡らせています。
研究を通してわかってきたのは、会話には、次のふたつの要素があるのではないかということ。
それが、発話を通して話し手と聞き手のあいだで約束事を構築していく「コミュニケーション」。そして、発話を通して話し手が聞き手の心理や行動を操ろうとする「マニピュレーション」です。

三木那由他『会話を哲学する』/光文社新書
著書『会話を哲学する』では、このふたつの現象について、『ONE PIECE』や『鋼の錬金術師』、『違国日記』などのフィクション作品に出てくるセリフを例にとり、論を展開しました。
結果、想定外としか言えないくらい、多くの方に読まれました。私が一番驚きましたし、感想というか、リアクションも予想外のものだったんです。

本書で論じた内容のなかで、私のオリジナルだったのは、コミュニケーションとは、お互いにその義務と権利で縛り合うような側面がありますよね、という部分です。規範的な要素がある、ということ。
ですが、蓋を開けてみると、「マニピュレーション」という言葉の意味するところに反響があったんです。こちらは言語哲学のなかではコミュニケーションに関してメジャーな立場を、「いや、それは実際にはコミュニケーションの話になってないよね」ということで、新しく「マニピュレーション」と名付けたものでした。
会話には「マニピュレーション」の要素がある。つまり、聞き手に何かを信じさせようとしていたり何かの感情を起こそうとしたりして、発話がなされることがある。そのことに、「びっくりした」、「怖かった」という感想を多くいただきました。
読者層として大きかったのは、やはりフィクション作品を例に持ってきているからか、マンガやアニメ好きの人、あるいは、マンガや小説を書いている人、演劇をつくっている人たちでした。

なぜフィクション作品から例をピックアップしたのか。それは、私が専門としているのが分析哲学だからです。
分析哲学とは、基本的に、思考実験を延々と繰り返す学問なんです。実際にはあり得ない例だけど、こんな特殊な状況になったら、どういう言葉の運用をするか? など、実例かどうかはともかく、今の問題にとってクリティカルなポイントが出てくるような例を構築して、論じていきます。
でも、私は、学者たちがこの思考実験のためにつくる例があまり好きじゃなかったんです。議論のためにつくられた例は、人工的で、非常にきれいにできていて、それゆえあまりかわいげがないように感じられます。それだけ整えたら、そりゃあ説明できるでしょう、と思ってしまう。
それに比べて、日常やフィクション作品の会話って、そんなにすっきりしたかたちにはなっていない。それに、その思考実験で扱いたくなるような、おもしろい例がフィクション作品からはたくさん見つかるんです。こちらのほうが一般の人にとっても親しみやすいはずです。
私が単にマンガ好きということも非常にありますが(笑)、哲学者だけがピンとくる議論を進めていても仕方ないですよね。フィクション作品を例にしたことで、哲学書としては異例の読まれ方をしたことを嬉しく思っています。

<中編>はこちら
スタッフクレジット:
取材・執筆:山内 宏泰
漫画:あい茶