業界とは?業種・職種・業態との違いや選ぶ際のポイントを解説
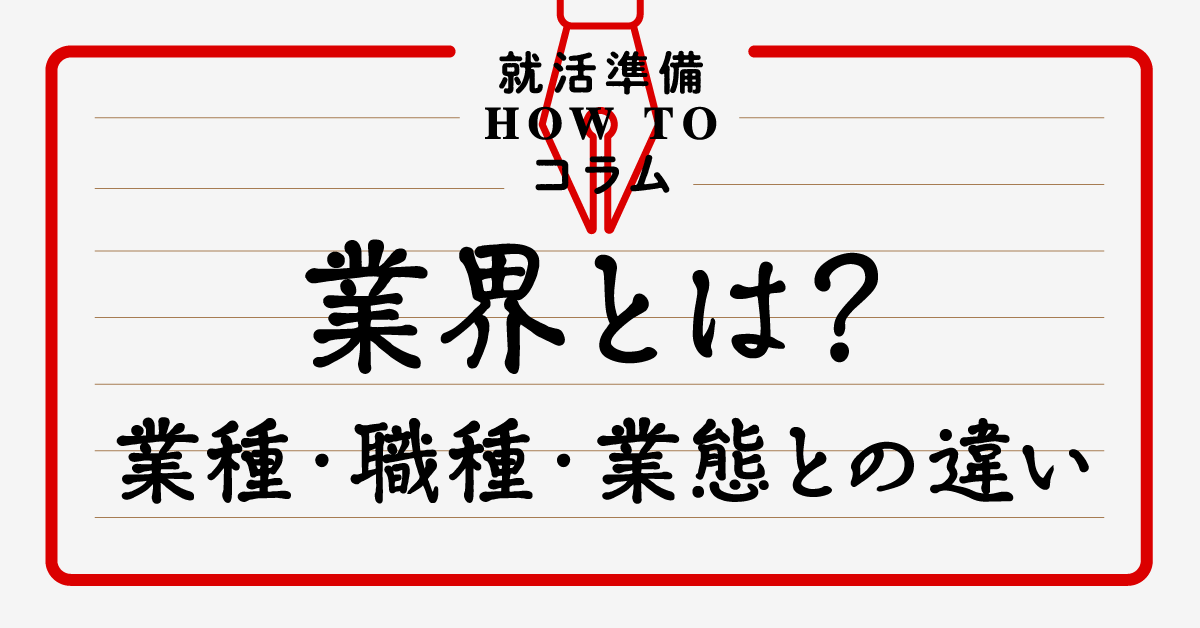
就活の際によく出てくる言葉の一つが「業界」です。しかし、頻繁に聞く言葉ではあっても、正しい意味はよく分からないという方も多いでしょう。
そこでこの記事では、業界とは何かを業種・職種・業態との違いも含めて解説。さらに、就活に欠かせない業界研究や、就職先の業界選びのポイントも紹介します。
大学3年生の3月に就職活動が始まり忙しくなる前の大学1・2年生のうちに、業界についての知識をつけておきましょう。
業界とは

業界とは、簡単に言えば企業を産業ごとに分類したものです。同じ種類の商品やサービスを提供する企業の集まりと言い換えることもできます。
単に扱う商品やサービスが異なるだけではありません。どのような仕組みで収益を得ているかというビジネスモデルも、業界ごとに異なります。
混同されやすい業界と業種・職種・業態の違いについて、それぞれの言葉の意味とともに詳しく解説します。
業界と業種の違い
業種とは、業界をさらに細かく商品やサービスの種類で分類したものです。
例えば「メーカー」という同じ業界に属する企業であっても、車を作っている企業と化粧品を作っている企業は別の業種に属します。
このように業界と業種は別のものですが、就活の際に細かい違いを覚えておく必要はないでしょう。どちらも、商品やサービスの種類によって企業を分類するものであることが分かっていれば、問題ありません。
業界と職種の違い
業界が商品やサービスの種類によって企業を分類するのに対して、職種は業務の内容によって仕事を分類したものです。例えば、事務職や営業職、研究職といった分類があります。
職種と、業界や業種の分類は無関係です。例えば、事務職や営業職は業種・業界を問わず多くの企業に存在しています。
業界の種類を知るだけでなく、職種についても知っておくと、さらに就職してからの仕事がイメージしやすくなるでしょう。
業界と業態の違い
業態は、営業形態の違いによる分類です。
例えば、同じ飲食業界に属する店舗であっても、ファストフードとファミリーレストランは別の業態として扱われます。また、商品を実店舗で売るかオンラインで売るかでも異なる業態として扱われます。
ひとつの企業が、複数の業態で店舗やサービスを展開しているケースも少なくありません。
業界の一覧とそれぞれの特徴
一般的に、業界は以下の8つに分類されます。
- メーカー
- 商社
- 流通・小売
- 金融
- サービス・インフラ
- 広告・出版・マスコミ
- ソフトウエア・通信
- 官公庁・公社・団体
ここでは、各業界の特徴を簡単に紹介します。各業界の特徴やビジネスモデルをさらに詳しく知りたい方は、次の記事もあわせてご覧ください。
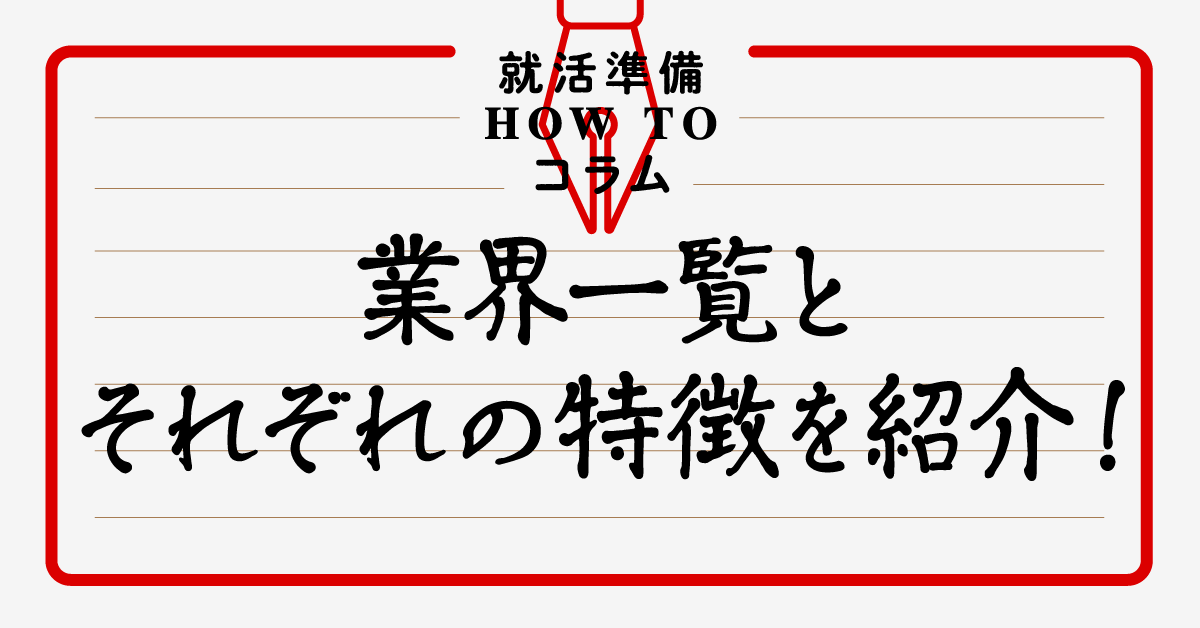
関連記事はこちら
メーカー
メーカーとは、物を作ることを主な仕事としている業界です。
「物を作る」というと製品の製造をイメージする人が多いでしょう。しかしそれだけでなく、製品を組み立てるための部品や、部品を作るための素材を作るメーカーも存在します。具体的な例でいえば、部品となるネジを作るメーカーや、ネジを作るための鉄やアルミ、チタンといった素材を作るメーカーもあるのです。
また、素材作りから製品の製造まで、全ての工程を自社で担当する総合メーカーもあります。
商社
商社は、メーカーが商品の販売や部品を購入するのを仲介する業界です。販路の開拓や部品の調達を行い、メーカーをサポートします。
特に輸出入を伴う場合、手続きが複雑で対応が難しいため、商社の役割は大きいといえるでしょう。商社が販売のサポートを行うことで、メーカーは良い製品の製造に集中できるのです。
商社にも複数の種類があり、扱う商品に制限がない商社を総合商社、特定の分野の商品のみを扱っている商社を専門商社と呼びます。最近では、メーカー自身が商社の役割を担うケースもあります。
流通・小売
流通・小売は、メーカーが作った製品を仕入れ、一般消費者向けに販売する業界です。幅広い商品を扱う業態もあれば、特定の分野の商品のみを扱う業態もあります。
小売というと実店舗での販売をイメージする人も多いかと思いますが、オンラインのみで販売している場合も小売業に分類されます。
小売業での販売には、商品を保管しておく倉庫や商品の輸送も欠かせません。そのため、倉庫業や輸送業も含めて一般消費者に商品を届ける仕事は「流通・小売」業界として扱われています。
金融
金融は、お金を動かすことを主な業務としている業界です。例えば、証券会社や銀行、保険会社などが金融業界に属しています。
業種や業態によって、ビジネスモデルが大きく異なるのが金融業界の特徴です。金融業界に興味がある方は、どの業態がどのようなビジネスモデルを採用しているのかも調べてみると良いでしょう。
サービス・インフラ
サービス・インフラは、具体的に目に見えるものではなく、形のないものを提供して利益を得る業界です。例えば、教育・アミューズメントなどの業種がサービス・インフラ業界に属しています。
また、電気や水道、ガスのように、生活に欠かせないインフラを提供する業種も、この業界に含まれます。
広告・出版・マスコミ
広告・出版・マスコミは、多くの人に情報を届けることを主な仕事としている業界です。広告が商品やサービスの情報を届けるのに対して、出版・マスコミは商品やサービスの宣伝になるかどうかにかかわらず、読者や視聴者に役立つ情報を届けています。
雑誌やテレビ番組に広告を掲載することも多く、広告と出版・マスコミは、同じ業界に属しているだけでなく、業務上でも結びつきの強い業種だといえます。
ソフトウエア・通信
ソフトウエア・通信は、ITを活用した商品やサービスを提供する業界です。IT業界と呼ばれることもあります。
通信回線の提供やソフトウエアの販売、モバイルアプリの提供など、多様な業態があります。また、1つの企業で複数のサービスを提供しているケースも少なくありません。
進化のスピードが速く、これから更なる進化が期待されている業界でもあります。
官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体は、人々に対する公平なサービス提供を主な目的としている業界です。国や地方自治体、地方公共団体、独立行政法人などが官公庁・公社・団体に該当します。
最大の特徴は、他の業界と異なり営利を目的とせずに業務を行っていることです。事業による収入を得る場合もありますが、税金や補助金、助成金、寄付金などから資金を得ている場合も多くあります。
就活に欠かせない業界研究

就活の際には、ただ企業の選考を受けるだけでなくさまざまな準備を行います。その中で欠かせないのが業界研究です。ここからは、業界研究が必要な理由や情報収集の方法を詳しく紹介します。
業界研究が必要な理由
業界研究を行うことで、その業界にどのような仕事や企業があるのかが分かります。さらに、業界のビジネスモデルも分かるはずです。
詳しく調査することで業界の全体像をイメージしやすくなるため、自分が志望する業界でどのように働きたいのかがより明確になるでしょう。希望している業界が、自分に合っているかどうかも確認できます。つまり、業界研究を行っておくことで、入社してからミスマッチに気付くことを避けられるのです。
また、さまざまな業界について調べることで、今まで知らなかった仕事に出会うこともあるでしょう。それほど興味を持っていなかった業界について、深く調べることで興味を持てるようになる場合もあります。業界研究を行うことで、志望する業界の選択肢を広げられることもあるのです。
業界について詳しく知っておくことで、志望動機をより明確に伝えられるようになることも、業界研究のメリットです。さらに、その業界で自分の強みをどのように活かせるのかを考えれば、説得力のある自己PRの作成にも役立ちます。
業界研究には時間がかかります。複数の業界を調べる場合には、さらに多くの時間が必要となるでしょう。大学3年生の3月に就職活動が始まると忙しくなってしまうため、大学1・2年生のうちに業界研究を進めておくのがおすすめです。
業界研究での情報収集の方法
業界研究の際には、多くの情報を集めなければなりません。例えば次のような資料やイベントを活用して、情報を集めてみると良いでしょう。
- 企業の情報をまとめて掲載している雑誌・書籍
- 企業のWEBサイト
- 合同企業説明会
- 就職情報サイト
- オープン・カンパニー&キャリア教育
- OB・OG訪問
例えばマイナビでは 「業界研究・職種研究徹底ガイド」 「業界研究大図鑑」といったコンテンツを用意しています。
業界地図では、企業のつながりや各業界の動向が分かる基本知識を掲載しています。どの業界に、どのような業種があるのかも把握できるでしょう。
業界研究・職種研究徹底ガイドでは、各業界の仕組みや職種の特徴を紹介しています。どの業界を調べれば良いか迷っている場合には、まず業界研究・職種研究徹底ガイドを読んでみるのもおすすめです。
業界研究大図鑑は、自分の身近にあるものから関連する仕事や業界について調べられるコンテンツです。業界大図鑑を見るだけでも、ひとつの商品にたくさんの人が関わっていることが分かります。
まずは自分の使いやすいものからチェックして、気になる業界の情報を集めましょう。
業界研究の際に調査すると良い項目
業界研究の際には、専用のノートを用意して調べた情報をまとめておきましょう。同じフォーマットを使って業界ごとに情報をまとめると、各業界の違いを比較しやすくなります。業界研究の際に調査しておきたい項目は次の通りです。
- トップの企業名、業界に属する企業の名前
- 興味を持った理由、志望動機
- 市場規模
- ビジネスモデル
- 業界の仕事内容・職種
- 業界の特徴
- 平均年齢・平均年収
- 関連する業界
- 業界の歴史
- 近年のトレンド
- 最近のニュース
- 将来性
- 課題
- 求められる人物像
- 気付いたことなど、自由記入
項目が多いため、一度に全部調査しようとせず、少しずつ情報を集めながらノートを埋めていっても問題ありません。各業界を比較し、自分に合った業界を見つけてみましょう。
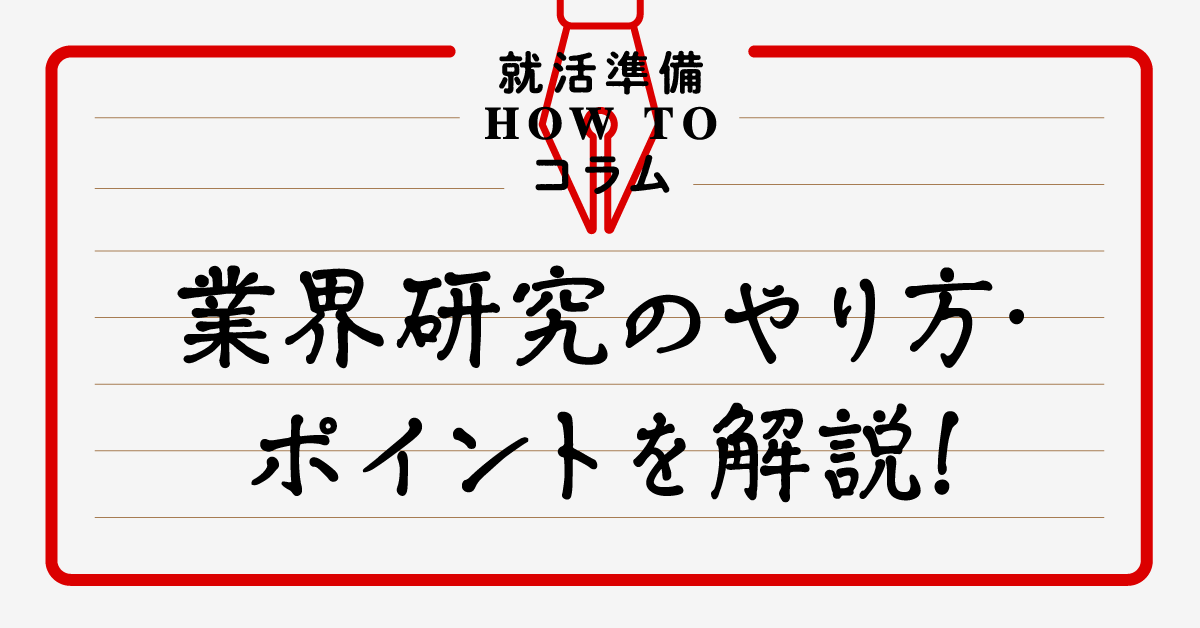
関連記事はこちら
就活で業界を選ぶ際のポイント

就活の際にどのように志望業界を決めれば良いのか迷ってしまう人も多くいます。そこでここからは、就活で業界を選ぶ際のポイントを紹介します。
自己分析をして自分に合う業界を選ぶ
志望業界を選ぶ際には、業界研究だけでなく自己分析も行いましょう。
自己分析を行うことで、自分の価値観が明確になります。自分の価値観に合う業界を選ぶと、仕事に対するモチベーションも高まりやすくなります。
また、自分をよく知っておくことで、入社してからミスマッチに気付くことも避けられるでしょう。さらに、自分にはどのような強みがあり、その強みを志望業界でどのように活かせるのかも考えやすくなるため、志望業界を選ぶ前に自己分析をしておくのがおすすめです。
自己分析では、自分はどのように社会に貢献したいのかを明らかにしておくと、自分に合う業界が見つかりやすいです。業界によって、社会で担う役割はそれぞれ異なります。その業界の役割と自身のやりたいことがマッチしているかどうか着目してみてください。
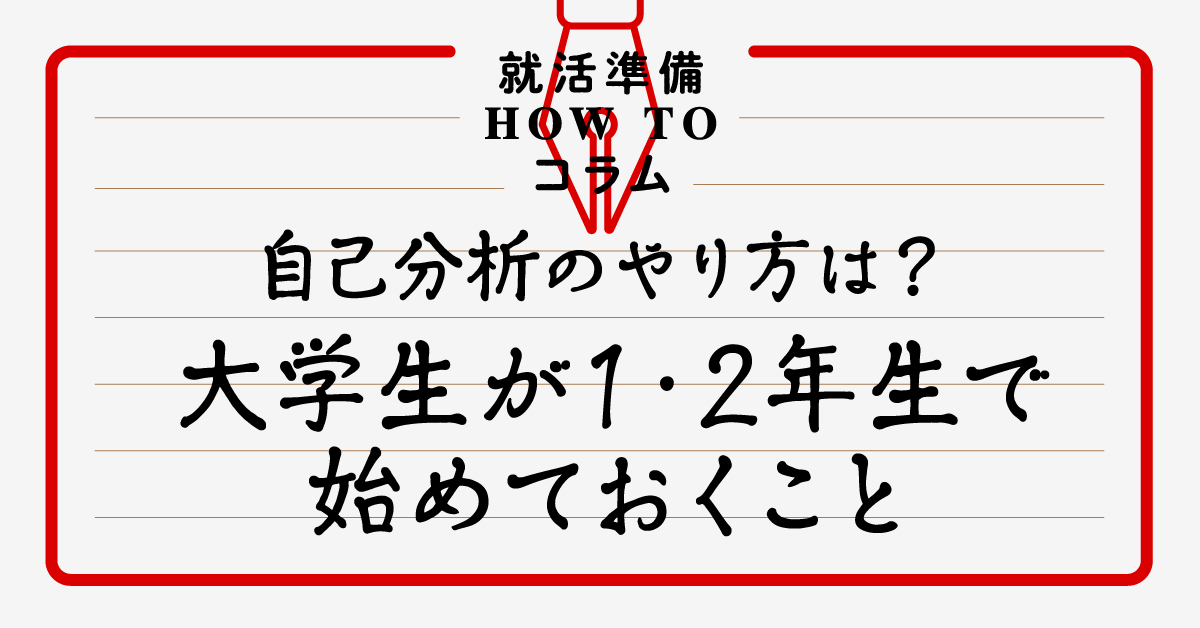
関連記事はこちら
業界にこだわりすぎない
自分に合った業界を見つけるのは重要です。しかし、業界だけにこだわり過ぎてはいけません。
業界だけに注目して志望業界以外の企業を候補から除外してしまうと、自分に合った企業を見落とす可能性があります。
第一志望の業界だけにこだわって志望企業を探すのではなく、関連する業界の企業を視野に入れるなど、幅広い企業をチェックすることで、自分に合った就職先が見つかりやすくなります。
業種や各企業の社風にも注目する
同じ業界に属していても、さまざまな業種や業態の企業があります。また、ひとつの企業にもさまざまな職種の人が働いています。さらに、企業によって社風も異なるものです。
業界だけに注目して志望企業を決めるのではなく、業種や職種、企業の社風にも注目しながら働きたい企業を見つけましょう。
業界の将来性を確認する
就活をしていると、就職がゴールに見えてしまうこともあります。しかし、就職はゴールではありません。就職後、将来もその業界で働き続けることを考えておかなければならないのです。
そのためには、今の状況だけでなく業界の将来性についても就職前に確認しておきましょう。自分が志望している業界が、将来どのようになると予想され、どのような展望を持たれているのか知っておく必要があります。
また、同じ業界に属していても、業種によって将来性に違いがある場合もあります。企業によっても、将来性には違いがあるでしょう。志望する業界・業種・企業の将来と自分の将来を重ねて考えてみるのがおすすめです。
ただし、将来性に関する情報は未来の予測であり、絶対にその通りになるというわけではありません。あくまでも現在の状況から見て考えられたものであり、確実なものではないことも知っておきましょう。
業界の垣根を越えた仕事があることも知っておく
業界は、大きく8つに分類できます。しかし、必ずしも全ての企業がいずれかの業界にぴったりあてはまるわけではありません。業界の垣根を越えた仕事をしている企業もあれば、複数の業界に属するように幅広く仕事をしている企業もあります。
複数の業界に興味がある場合には、業界の垣根を越えるような仕事をしている企業があるか探してみるのもおすすめです。
オープン・カンパニー&キャリア教育等に参加してみる
オープン・カンパニー&キャリア教育等とは、企業や職種、業界に対する理解を深めるためのプログラムです。具体的には、企業・工場見学や交流会、説明会などが実施されます。
全学年を対象としているため、大学1・2年生でも参加できます。1日で終わるプログラムであるため、参加しやすい点も魅力です。
オープン・カンパニー&キャリア教育等に参加することで、業界の雰囲気や仕事内容が分かります。また、業界や企業で求められているスキルや人物像も理解できるでしょう。
中には、実際に企業で働いている社員から話を聞けるようなプログラムもあります。オープン・カンパニー&キャリア教育等に積極的に参加することで、より自分に合った業界を選べる可能性が高まります。
まずは興味のある業界を見つけてみよう
業界とは、企業が提供している商品やサービスによって分類したものです。業界が異なると単純に販売する商品やサービスが異なるだけでなく、ビジネスモデルにも違いが生じます。
志望業界を選ぶためには、まず業界研究を行いましょう。自分が興味を持った業界を中心に、複数の業界を調査することで、自分が業界内でどのような働き方をしたいのかイメージがつかみやすくなります。業界研究の情報は一冊のノートにまとめておくと、後から比較しやすくなるためおすすめです。
企業の分析とともに自己分析も進め、自分に合った業界を探してみましょう。大学3年生の3月からの就活が始まると忙しくなってしまうため、大学1・2年生のうちに準備を始め、興味のある業界を見つけてみてください。



