
- トップ
- 就活支援
- はじめてでも大丈夫!グループディスカッション対策のコツ
- 進め方と役割
進め方と役割
グループディスカッションの進め方
グループディスカッションの実施時間で多いのが、30~45分です。制限時間内に結論を出すには、効率よく進めていくことが大切。一般的なグループディスカッションの進め方を確認しておきましょう。
制限時間30分での例
| 01 | 2分 |
自己紹介、役割を決めよう 簡単に自己紹介をし、開始されたら1番最初にそれぞれの役割を決めましょう。 |
|---|---|---|
| 02 | 2分 | 時間配分を決めよう 意見出し、整理、結論の準備など、何にどれだけの時間を割くのかタイムスケジュールを決めましょう。 |
| 03 | 15分 |
意見・アイデアを出し合おう グループのメンバー全員が議論に参加し、 |
| 04 | 6分 |
意見・アイデアを整理しよう 集まった意見やアイデアからタイプ別にまとめたり、 |
| 05 | 5分 |
結論を導いて発表の準備をしよう グループとしての結論を決定し、ほかの参加メンバーに伝わるような言葉や表現を検討して、発表の準備をしていきましょう。 |
| 06 | 1分 |
発表 特に指定がなければ、おおよそ1分程度で簡潔に伝えましょう。 |
知っておきたい役割
グループディスカッションでは、チームで討論をして決められた時間内に結論を出さなければなりません。メンバーが好き勝手に話を進めていっては結論に到達することは難しいでしょう。グループディスカッションに慣れるまでは、大まかな役割を意識しておくと発言しやすくなります。自分がチームに貢献できることは何かを考えながら、しっかり議論を進めましょう。

司会・進行役(リーダー)
複数の人間が短い時間の中で、効率的に整然とディスカッションを進行させるために必要な役割。仕切り役ではなく、メンバーが発言しやすい状況を作る役割と考えましょう。自ら発言する以上に、意見があるのに手を挙げられないタイプの人がいないかを観察し、そういう人が発言しやすい状況を作るなど、メンバーへの心配りが大切な仕事となります。
陥りやすいNGポイント
制限時間内にうまくまとめられず、チームの意見を無視して無理やり結論を出そうとする。

時間管理(タイムキーパー)
「ディスカッションは盛り上がったが、気がついたら結論を出す前に制限時間がきてしまった」では失敗です。ただ成り行きに任せて意見を交わすのではなく、自由に意見を発表する時間、発表された意見から結論を導き出す時間、発表を練習する時間などに区切り、進行していくことが成功の秘訣です。自らもしっかり発言をしながら、進行係に時間経過を知らせ、進行をサポートしましょう。
陥りやすいNGポイント
議論が盛り上がり、決めた時間配分の予定時刻になってもなかなか言い出せずにオーバーしてしまう。

書記
意見交換が盛んであるほど、すべての意見を記憶しておくことはできません。発表された意見の要点をメモして残す係が必要です。1人で大変な場合は、2人ほど任命しておきましょう。グループディスカッションの苦手な人は、この書記係を担当してチームに貢献しましょう。もちろん、積極的に発言も行いましょう。
陥りやすいNGポイント
記録をしただけで、それをメンバーと共有しない。書くことに集中しすぎてしまい、意見を言わない。

その他
何かの係についていないからといって役割がないわけではありません。メンバーこそがチーム作りの主役です。活発なグループディスカッションの進行を意識しましょう。
陥りやすいNGポイント
役割が特になく、目立とうとして輪を乱したり、自分の意見の主張が激しくなってしまう。
グループディスカッションの練習方法
-
1メンバーを集めよう!
まずは、一緒に練習するメンバー(6~8人)を集めましょう。できれば同じ就活生が好ましいのですが、友人や、ゼミ・サークルのメンバー、バイトのメンバーなど、どのような関係性でもかまいません。重要なことは、真剣に一緒に議論をしてくれそうなメンバーを探すことです。 -
2テーマを決めよう!
議論するテーマを決めましょう。日頃ニュースで目にするような社会課題や時事問題はもちろん、志望業種や企業の出題傾向を調べてテーマを選ぶとより本番の対策につながります。 -
3時間を決めよう!
ここでいう時間は、時間配分のことではなく、自己紹介~発表までの全体の時間を自分たちで決めるということです。基本的に本番は30~45分のプログラムが多いので、練習もそのくらいの時間で設定するとよいでしょう。 -
4試験官役を決めよう!
練習の目的はあくまで「議論の進め方を知ること」そして、「自分を知ること」です。1~2人試験官役を立てることで、終わった後のフィードバックを受けることができます。また、試験官役は、客観的に皆のパフォーマンスを見ることができるメリットがあります。学校のキャリアセンターの方に試験官役を頼んでみるのもひとつの手です。 -
5実際にグループディスカッションをやってみよう!
グループディスカッションの進め方を参考に、実際に練習をしてみましょう。発表の際は、試験官役の人に発表をしましょう。 -
6フィードバックをもらおう!
発表が終わったら、最後に試験官役の人が皆にフィードバックをしましょう。フィードバックのポイントは、大きく4つあります。
[1] どれだけの時間がかかったか。
[2] テーマに沿った発表ができていたか。
[3] 各役割がきちんと果たせていたか。
[4] チーム全員がディスカッションに参加できていたか。
以上のポイントを踏まえながらフィードバックを行うとよいでしょう。できれば1人ひとりに良かった点・改善点が言えるように、試験官役の人もじっくり見ておくことが大切です。
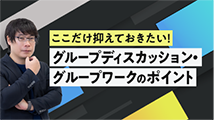
【My CareerStudy】
グループディスカッション・グループワークのポイント(Eラーニング)
※別サイトへ遷移、My CareerIDでログイン可能
グループディスカッションのポイントや、そこで出された課題の種類に対して、それぞれのアプローチ方法を具体例を交えて動画で解説します。
