知る
know

知っておきたい!
実習日誌の書き方GUIDE
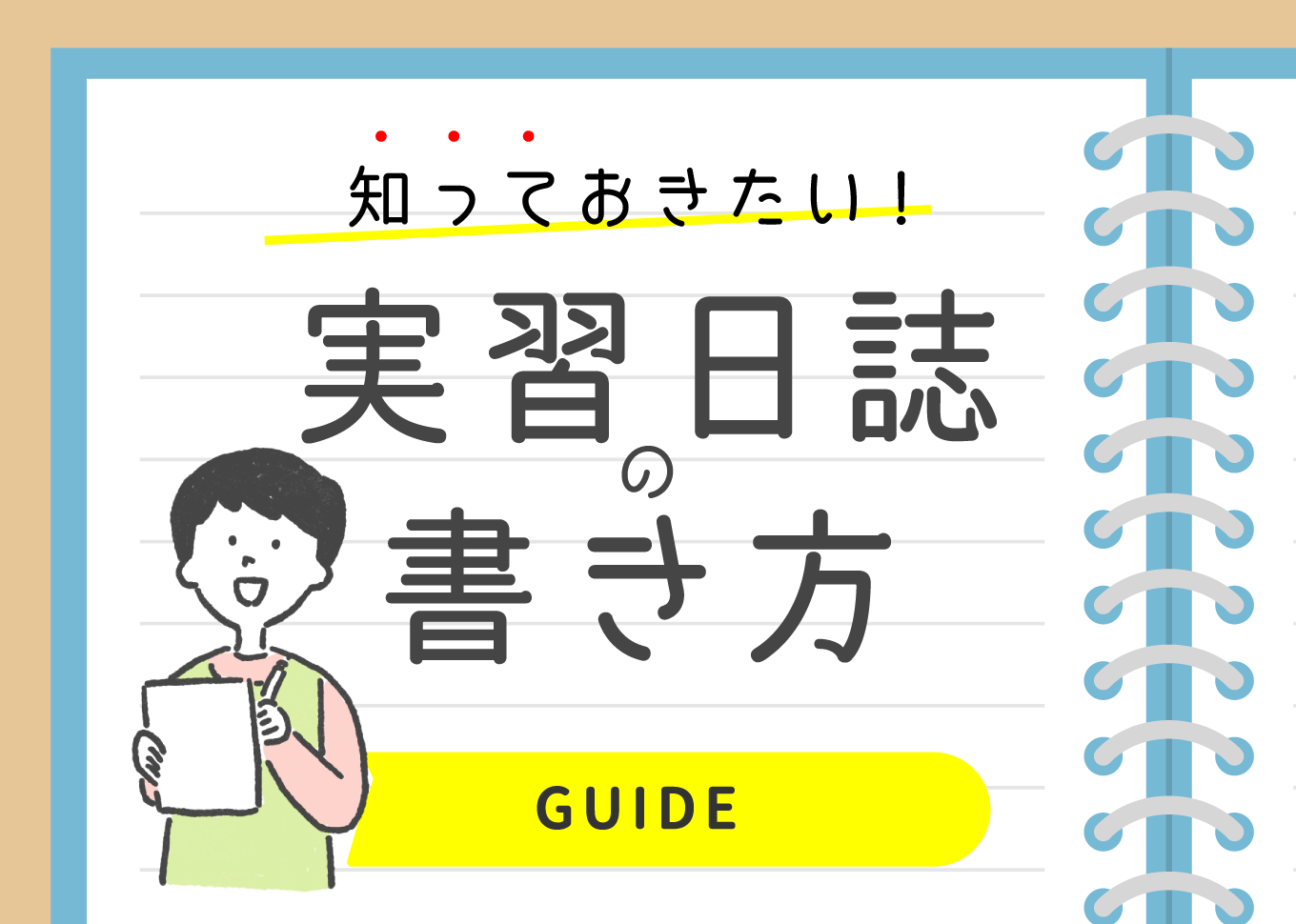
保育実習で必ず必要になるのが実習日誌と指導案です。「何を書くものなの?」「どんなことを書いたらいいの?」と不安に思う人もいるでしょう。ここでは実習日誌について、詳しくご紹介します。
実習日誌&指導案って、何?
実習日誌
フォーマットは学校によって異なりますが、主に「環境構成」「子どもの活動」「保育者の援助・配慮」「実習生の動き・気づき」など、その日にあったことを書きます。子どもたちの生活を把握し、自分のかかわりを見直すのに役立ちます。
指導案
1日を通して子どもたちにどのような指導を行うか、計画をまとめます。実施園がどのような保育を行っているのか、子どもたちの発達具合の状況に合わせて、指導内容を考えます。子どもたちと何がしたいか、という視点も大切です。
実習日誌の「基本のキ」
実習日誌を書く際、次の4つを必ず押さえておきましょう。

基本
01
大切なのは「気づき」
子どもの様子だけを事細かに書いても日誌にはなりません。もっとも大切なのは、子どもたちの行動や保育者の動きなどで自分が気づいたこと、学んだことです。

基本
02
日誌は指導計画につながるもの
毎日の日誌でまとめたことが、指導案につながります。「環境構成」も詳しく書いておくと、より具体的にイメージしやすくなるでしょう。

基本
03
「保育所保育指針」を読んでおく
子どもの正常な発達についての知識があると、子どもと接したときの気づきや考察がより豊かになります。日誌を書く際の大きな助けにもなります。

基本
04
日誌を出したら終わりでなく、実際の現場でも続く
文章を書いたりまとめたりするのが苦手な人もいるでしょう。しかし、実際の保育現場では、週案や月案、季節の行事案、個人の日誌、おたより帳など、書くものがたくさんあります。日誌はそのための練習の場でもあります。
これが実習日誌だ!
実際の実習日誌にはこんなことを書きます。いくつかポイントをご紹介します。


実習日誌のポイント
目標(ねらい)を具体的に書く
その日の主な活動と目標を書きます。担当する年齢や実習園の保育計画などを参考にします。
環境構成は図にして書く
活動ごとに、保育室がどのようになっているのか(場所、机や椅子の配置、玩具の置き方など)を図にして描きます。指導案を書く際にも役立ちます。
子どもの活動は全体と
個々を両方記す
1日の流れを時系列に沿って書きます。クラス全体の活動、子ども1人ひとりの動きや言葉なども記しておきます。
保育者がどのような動きを
しているのか学ぶ
保育者が子どもたちに対して、どのような行動をしているのか、言葉掛けをしているのかを書きます。そこに「実習生の気づき」が隠されています。
最も重要なのは
「気づき」を書くこと
実習日誌の中でも重要な箇所が「気づき」です。「〇〇があった」「〇〇と言った」などの事実と、そこから考えた考察や自分が感じたことを分けて書くよう意識しましょう。
それぞれの子どもの
留意点を記入しておく
アレルギーがあるのか、発育状況によって気をつけるべきことはないかなど、留意点を記入しておくとよいでしょう。
睡眠時の変化を
確認する
睡眠時に変化がないか、確認を行います。うつぶせ寝はとても危険ですし、体調の変化がないか、細かくチェックしておきます。
子どもだけでなく、
全体を観察しておく
子どもの動きにばかり目がいきがちですが、保育室に玩具が散らかっていないか、床に物が置いたままになっていないかなど、全体の安全にも目を配り、記入します。
思いもよらない
できごとがあっても冷静に
授業などで実習について学んだことで、こんな流れになるだろうと頭の中でシミュレーションしていても、そうはならないことがたくさん。気づいた点を記入しておくことで次につなげます。
まとめの部分は具体的に、
次の日につながる内容に
「実習での体験と考察」や「質問」はまとめの項目です。最初に書いた「目標」がどのくらい達成できたのか、次の日の実習のために確認しておいた方がよいことなどを書きます。

