
製薬会社の営業部門に所属し、医療機関へ営業活動を行うMR(医薬情報担当者)。リスクも内包する医薬品を取り扱うからこそ、単なる売上アップ以上のものが求められる仕事です。MRを取り巻く環境は激変していますが、そうした変革期にあっても活躍できるのはどのような資質を備えたMRなのでしょうか。
Index
製薬会社(MR)の最新動向

今後の展望

MRの仕事

就職活動&キャリアパス

製薬会社(MR)の最新動向
環境変化の中で生き残る戦略が必要
健康志向の高まりが追い風となっている食品メーカーは、日本のような少子高齢社会でも市場規模が縮小しにくい業界だと考えられています。ただし、美味しさはもちろんのこと、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品に代表されるような「+αの要素」が重視され、海外製品あるいは国内メーカー間における激しい競争の中で差別化を図ろうと心血が注がれています。
化粧品メーカーでも、アンチエイジングなどを謳う高機能の製品開発が進められており、大学の研究室などと連携するケースも珍しくありません。一方で、一定の品質を保ちながらもコストパフォーマンスに優れた「プチプラ」の人気も高く、高価格帯と低価格帯に製品が二極化する傾向がみられます。日本の化粧品は国外でも高い評判を得ており、海外市場にチャレンジする企業も少なくありません。

今後の展望
新たなタイプのMRが誕生、アウトソーシング化も
従来は地域や施設ごとに担当が決まりがちでしたが、近年では自社製品をすべて取り扱うジェネラルMRや、専門性の高いがんなどの分野に特化する専門領域型MRも増えています。どのようなタイプのMR育成に舵を切るかは企業により異なるので、その点も考慮に入れて志望先を検討することが必要です。また、MR業界にもアウトソーシング化の波が押し寄せていることを知っておきましょう。具体的には、医薬品販売業務受託機関(CSO)から派遣されるコントラクトMRのことで、欠員補充や特定分野の強化を目的に導入されています。
MRがやり取りする相手は医師だけだと思われがちですが、それ以外の医療従事者との関わりも軽視してはなりません。例えば、医療技術の進歩による外来治療の範囲拡大、処方日数の長期化、ジェネリック医薬品の普及などを背景に、MRが薬剤師とコミュニケーションを図ることの重要性が指摘されています。バックグラウンドを同じくする薬剤師との関わりが増えることで、薬学部出身のMRがより強みを発揮しやすい環境に近付くかもしれません。

MRの仕事
より本質的な医師へのアプローチが必須
MRは営業的な側面が強い職種ですが、やみくもに自社製品をアピールするだけでは成果は得られません。「医薬情報担当者」という名前の通り、科学的根拠に基づいた情報を医師などに伝えて診療の参考にしてもらうことが売り上げにつながっていきます。
一方で、実際に医薬品を使用する患者さんと日常的に接している医療従事者から、使用実態や副作用情報などを収集し、会社にフィードバックすることもMRの重要な役割の一つ。特に、治験時に除外されることが多い患者さん(高齢者や小児、妊産婦など)のデータをつかむことは、市販後調査という観点からも極めて重要です。
MRというと「医師への接待」をイメージする人がいるかもしれませんが、現在では業界の独自ルールにより、過剰な営業活動は禁止されています。担当する製品領域に関して医師と対等にやり取りできるだけの知識を備える、タイミング良く適切な情報提供をすることで多忙な医師のニーズを満たすといった、より本質的なアプローチが求められる時代になったといえるでしょう。
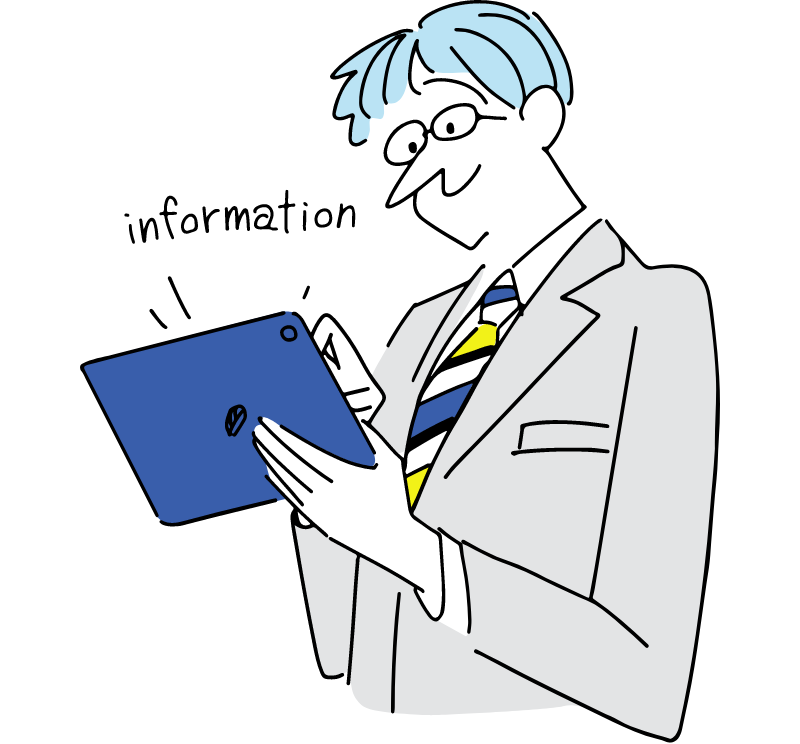
就職活動&キャリアパス
就職活動のポイント
アピール上手な文系学生に押し負けない
さまざまな学部の出身者がMRとして活躍していますが、薬剤の作用機序や体内動態を正しく理解し、医療従事者と「共通言語」で話すことができる薬学部出身者には大きなアドバンテージがあります。一方で、就職活動では専門知識の有無ばかりが問われるわけではなく、むしろ高度なコミュニケーション能力がより重視されるケースも少なくありません。アピール上手なことが多い文系学生と並んだときに押し負けるようなことがないよう、的確な自己分析と企業研究で自分を売り込む必要があるでしょう。面接対策に力を入れることはもちろんですが、日ごろからさまざまな立場の人と意識的に交流し、今のうちから視野を広げておいてください。そうして養われた自分の思いを上手に伝える力、相手と良好な関係性を築く力は、卒業してからも必ず役立ちます。
キャリアパス
営業職としてマネジメント層をめざす以外の道も
MRが担当する施設の数や種類は会社によりさまざまですが、いずれにしても数年置きに担当施設が変わっていくケースがほとんどです。現場経験を積みながら特定の領域を極めたり、チームリーダー、営業所長、支店長などのマネジメント職へキャリアアップしたりするルートが一般的でしょう。また、適性や実績によっては、MR以外の職種へ異動する可能性も。例えば、マーケティングの中心となるプロダクトマネージャー、自社製品のDI(医薬品情報)担当、MR教育担当などが考えられます。MRとして培った経験を生かせる職種は想像以上に多く、製薬会社向けの広告代理店やコンサルティングファームなどに転職して活躍している先輩もいます。
向いている人
医療への思いと営業力を兼ね備えていること
MRは、製薬会社と現場をつなぐ懸け橋のような存在です。患者さんと直接的に関わる場面は限られていますが、医師への提案やデータのフィードバックなどを通して、より良い薬物療法を実現していくことにやりがいを感じられるかがポイントだといえます。当然のことながら、コミュニケーション能力に優れている必要があり、とりわけ医師と信頼関係を築けるだけの知識や誠実さが不可欠です。また、いわゆる営業職らしいタフさも重要でしょう。自身の能力や成績がダイレクトに収入に反映されることも多く、営業目標達成のために奮起できることもMRに欠かせない条件の一つだといえそうです。


