知る
know

保育士と一般就職
徹底解説!
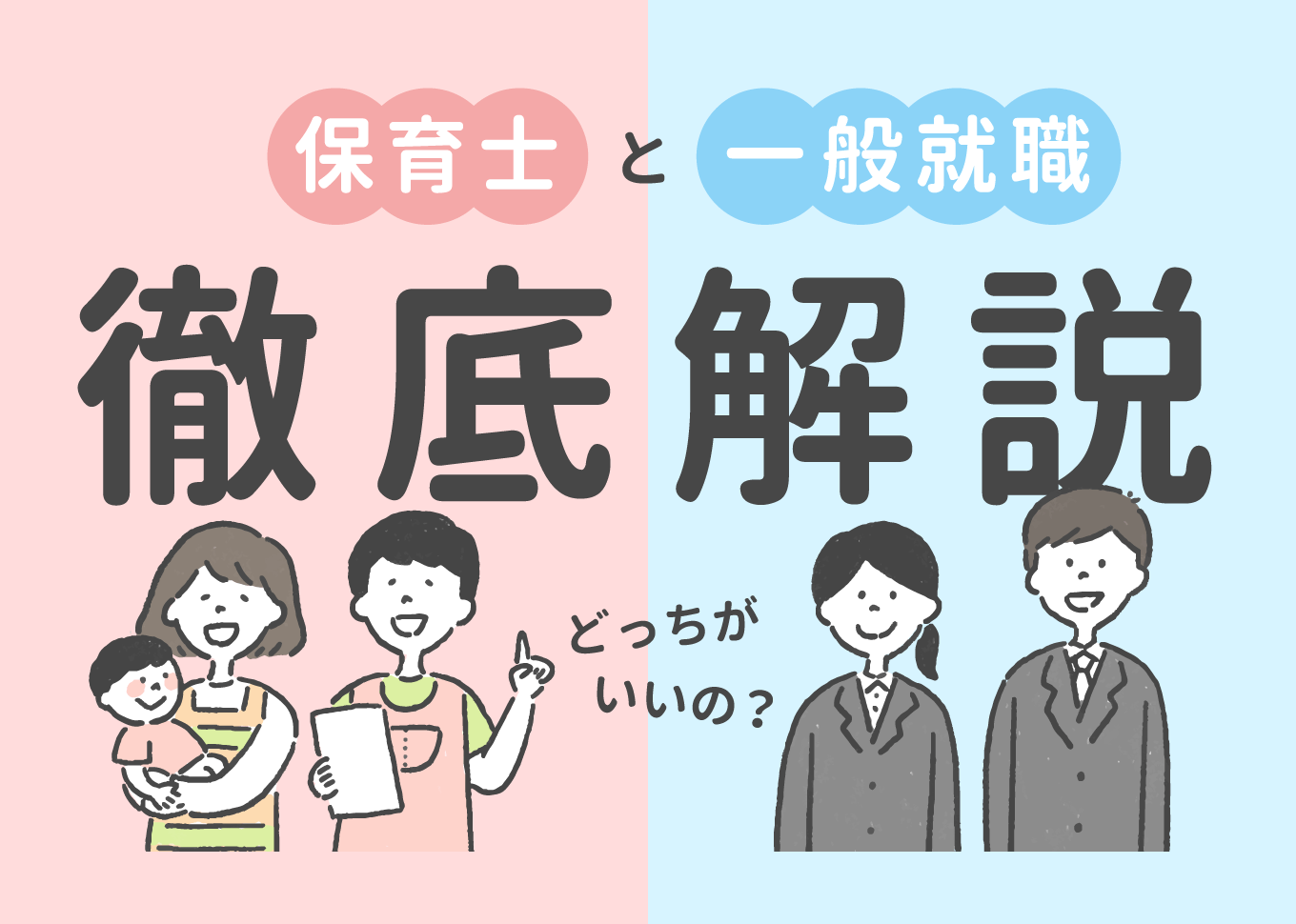
キャリア
このページでは、保育士ならではのキャリアの道筋や魅力をご紹介します。
1. 保育園におけるキャリアパスとは?
厚生労働者「保育の現場・職業の魅力向上検討会」※1が2020年に作成した資料※2によると、常勤で働く保育士のうち、約半数が経験年数7年以下の若手保育士で占められています。経験年数8~14年未満の保育士は2割程度である一方、14年以上のベテラン保育士は3割以上を占めており、保育の現場には、いわゆる中堅層が少ないという実態が浮き彫りになっています。
保育士の経験年数※


ベテランと呼ばれるようになる前に辞めてしまう人が多い原因の一つと考えられるのが、キャリアアップする機会の少なさでした。「入職してから役職に就くまで長くかかりすぎる」という問題を解決する目的もあって、2017年の「処遇改善等加算Ⅱ」制度創設に伴い新設されたのが「副主任保育士」「専門リーダー」「職務分野別リーダー」という3つの役職です。まずは、保育園におけるキャリアパスがどのようなものか、全体像を押さえておきましょう。
- ※1 厚生労働省子ども家庭局が実施する委員会。保育士という職業や、働く場所としての保育所の魅力向上やその発信方法等について、子ども家庭局長が学識者等の参集を求めて検討するのが目的。
- ※2 保育の現場・職業の魅力向上検討会(第5回)資料「保育士の現状と主な取組」(令和2年8月24日)より。
保育園における一般的な役職
| 役職名 | 必要な経験年数 | 主な仕事内容 |
|---|---|---|
| 園長 | 10~25年程度 | 資金管理や補助金の申請、保育士の採用、設備・衛生面の管理など、園全体の経営管理を担う。関係機関とやり取りする機会も多い |
| 主任保育士 | 8~20年程度 | 現場を統括し、保育士をまとめる。シフト管理や保育士の指導、指導計画の確認など。行事運営の指揮を執ったり、保護者対応の窓口になったりすることも |
| 【新】 副主任保育士 |
おおむね 7年以上 |
主任保育士を補佐する役割で、マネジメントスキルが必須 |
| 【新】 専門リーダー |
おおむね 7年以上 |
4分野以上に精通し、高い専門性を発揮して職務に当たるリーダー |
| 【新】 職務分野別リーダー |
おおむね 7年以上 |
特定の分野において一定の知見を有し、関連業務を担当する |
| クラス担任 | 1~5年程度 | 基本的に1つのクラスを担当し、指導計画に基づき ながら現場を運営する |
待機児童解消のために新規開園する事業所が増加傾向にある今、管理職やリーダーのポストも増えつつあります。特に私立保育園においては、若いころからキャリアアップを狙える可能性も高いことを知っておきましょう。
2. キャリアアップするにはどうすればいい?
私立保育園の場合、園長や主任保育士、クラス担任といった従来の役職では、特別な資格を必要としないケースがほとんど。保育士資格をベースに経験を積み重ねていくことで、チャンスが巡ってくるイメージです。園長や主任保育士については、法人によっては「管理職試験」を設け、それにパスすることが条件になることもあります。
一方、副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダーについては、同時に新設された「キャリアアップ研修」を受講し、知識や技能を習得することが求められます。
2017年に創設された保育士の役職
| 経験年数 | 概要 | 処遇改善額 | |
|---|---|---|---|
| 副主任保育士 | おおむね7年以上 | 職務分野別リーダーの経験があり、キャリアアップ研修(8)に加えて3分野以上の研修を修了して、副主任保育士として発令されること | 4万円/月 |
| 専門リーダー | おおむね7年以上 | 職務分野別リーダーの経験があり、4分野以上のキャリアアップ研修を修了して、専門リーダーとして発令されること | 4万円/月 |
| 職務分野別リーダー | おおむね3年以上 | 担当する職務分野の研修(キャリアアップ研修(1)~(6)のいずれか)を修了し、その分野における職務分野別リーダーとして発令されること | 5,000円/月 |
保育の道に進んで最初に挑戦するのは、職務分野別リーダーになる場合が多いでしょう。クラス担任として経験を積みながら特定の分野での専門性を高めていき、いずれはマネジメント職にも挑戦する……というのが、今後の保育士のスタンダードなキャリアパスとなるのではないでしょうか。
3. キャリアアップ研修の種類は8つ
それでは、新たな3つの役職に就くために必須となる「キャリアアップ研修」とはどんなものなのでしょうか。8つの分野それぞれについて解説します。なお、研修時間はいずれも1分野15時間以上と規定されています。
| (1) 乳児保育 |
|
|---|---|
| (2) 幼児教育 |
|
| (3) 障害児教育 |
|
| (4) 食育・アレルギー |
|
| (5) 保健衛生・安全対策 |
|
| (6) 保護者支援・ 子育て支援 |
|
| (7) 保育実線 |
|
| (8) マネジメント |
|
(1)~(6)は、いずれも保育分野における重要なテーマです。「他の保育士等に助言および指導ができるような実践的な能力を身に付ける」という共通した内容からも、職場でリーダーシップを発揮することが求められていると分かります。自身の理想とする保育士像を実現するためにも、将来的にどの専門分野に挑戦するか、今のうちから意識しておくといいでしょう。
一方、(7)と(8)は少し毛色の違う内容です。「保育実践研修」は、現場での実習経験が少ない保育士試験合格者や、ブランクの長い潜在保育士などが主な対象。「マネジメント研修」は、主任保育士の下でミドルリーダーの役割が期待される保育士が対象です。
4. 研修を受けるならココに注意!
注目が集まるキャリアアップ研修ですが、受講を考える際には注意したいポイントがいくつかあります。
事業所によって受講可能な人数に上限がある
研修の参加者を決めて申し込むのは、基本的に勤務先の事業所です。園児数などにより申し込み可能な枠数が異なり、受講できる保育士の数が限定されることも。希望すれば必ず受講できるとは限らないのです。
加算が全額支給されるとは限らない
研修を受講しても、その他の要件が満たされなければ、そもそも役職に就くことができません。また、加算の種類や内容によっては、事業者に配分などが委ねられている部分もあるため、加算額がそのまま給料に反映されないこともあります。
研修によっては費用負担の可能性もある
都道府県が実施する研修は無料で、テキスト代など実費のみ負担であることが多いですが、そうでない場合は費用が発生することも。「特定の条件を満たせば受講料免除」というケースもあるため、事前に確認が必要です。
新たな制度の創設で、多くの保育士さんにとって将来の展望が描きやすくなったといえます。キャリアアップと給料アップが同時にかなう処遇改善等加算Ⅱの仕組みを活用して、あなたも自分らしく満足度の高い保育士ライフを楽しみませんか?

