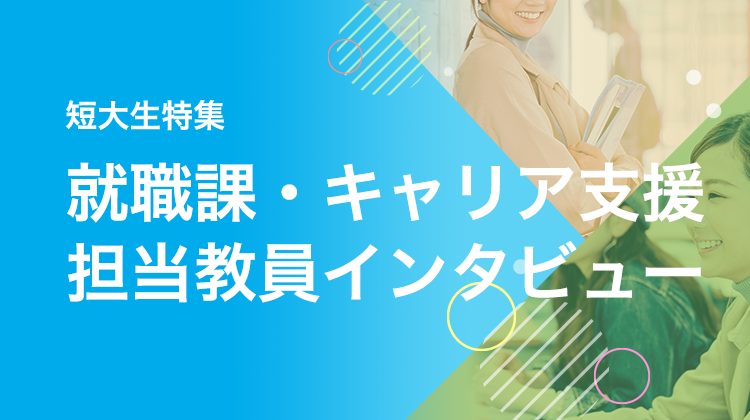Vol.02

教授・就職委員会委員長
有泉 正二さん
「自分が知っている企業」
ではなく
「やりたいこと」で選ぶ
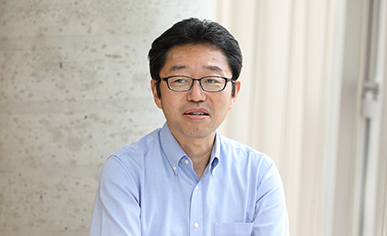
東京立正短期大学には、幼児教育専攻と現代コミュニケーション(現コミ)専攻の学生が在籍しており、9月末の時点で7割近くの学生の就職先が決まっています。本学の学生は「企業に長く勤めたい」と希望する者が多く、そのために会社の規模や知名度よりも「この会社で自分がどのくらい活かされるか」を、真剣に見ているのが特長です。これは本学が進めてきたキャリアデザイン教育の賜物と言えるでしょう。規模の小さい学校ならではの良さですが、担任をはじめとする教職員の目が行き届いているのです。就職部は常駐で、時間外でも学生の相談に乗るのが普通の光景になっています。そのように学生が社会で働く大人とコミュニケーションをとる機会はキャンパス内でもとても多いですね。そんな環境で過ごしていると、最初はただ「自分が名前を知っている企業」しか頭になかった学生も、就活を進める中で、先生の視野の広さやアドバイスの的確さに気づいていくようです。
私たちが考える就活は、内定獲得をゴールと定めていません。短大生にとっては就活自体が重要な学びです。初対面の大人に自分がどういう人間であるか伝えたり、面接に備えて社会情勢やニュースをチェックする習慣をつけたりするなど、新しい経験を積む機会ですし、何よりも自分を見つめ直す時間になります。キャリアデザインの授業では「就活は量である」と表現していますが、たくさんの企業に足を運び、選考を受けて、人に会って、そうして初めて「先生方が言っていたのはこういうことか」と腑に落ちるのです。私たちの一方的な言葉だけではなかなか響かない、学生自身の体験が伴ってこそ理解できることがあるのだと考えます。
こうしたキャリアに関する指導方針を、就職部や担任の教員が共になり長年、実践してきました。ですから本学の学生たちは一つ内定が出てもそこで就活を終わりにせず、最後までやりきって、納得して企業へ入社することが多いです。そんな就活ができた学生は自分に自信を持ち、入社後も長く勤められるのではないでしょうか。
短大生に求められるのは
柔軟で素直な若者の視点

就活に際しては、4大生と短大生では求められるものが違うと感じています。4大生には大人らしい落ち着きや知識を、一方の短大生には若さ故の柔軟性や新しいアイデアを、企業は求めるようです。たとえば金融業界の中でも信用金庫は、個人客や若い人にとってあまり馴染みのない場所ですが、そういうところで短大生が採用されるのは、若々しい視点を取り入れたいという意図があるからだと思います。周囲の大人たちから目をかけられる、可愛がられるというのは仕事をする上で大事な要素であり、短大生の素直さや率直な若者らしさは強みとなるでしょう。知識に勝る「人間としての魅力」が相手に伝わるように、面接のときも分からないことは臆せず「分かりません」と質問して、きちんとコミュニケーションを取ること。それを、常々、授業では教えています。
本学の就活が円滑なのは、学生同士が互いに良い刺激になっていることが大きいと感じています。クラスの中で、いち早く就活を意識する先頭集団が生まれると、他ののんびりした学生を引っ張り上げてくれるのです。つまり、最初の先頭集団が形成されるように促していくことが指導においては重要になってきますね。
2025年卒の就活スケジュールに関しては「現行の日程を維持」という見通しではあるものの、企業の採用方法も多様化し、選考のスピードも早くなっているので、活動量を増やして対応することが今まで以上に大切になってきます。もともと本学はキャリアデザインの授業を1年生からカリキュラムに組み込んでいますが、早くから準備するに越したことはないので、前期からインターンシップの授業や就活ガイダンスなどを始め、1年生の間に就職マインドを醸成していければと考えています。余裕を持って臨むことで悔いのない就活につながることを期待しています。首都圏外から上京し、地元企業以外に就職の選択肢を持たなかった学生でも、本学で学ぶことで東京をはじめとした地元以外の土地で働く選択肢を得て、心から「短大に来て良かった!」と思えるような機会を増やせたら嬉しいですね。就活の経験が社会人としての力になるよう、全力でサポートします。
卒業後の
ホームカミングデーでは
悩みの相談も

保育士はずっと売り手市場が続いていますが、問題はいかにこの仕事を続けていくかにあります。せっかく一生働ける資格なのに、「イメージが違う…」と半年くらいで、退職したり、他の業界に転職したりするのは、非常にもったいないなと感じます。なるべく、就職先の保育園や幼稚園とは相思相愛であって欲しいものです。ただ、一般企業と比較すると、それぞれの園の情報や様子がインターネットなどを利用しても得にくい面があるため、必ず志望先の園を訪問し、できれば実習をさせてもらい、園長先生や一緒に働く先輩たちの雰囲気が自分に合っているかを試すように勧めています。例え就職した後に「やっぱり違う」と思ったとしても、保育士・幼稚園教諭の仕事は続けてもらいたいと願っています。
本学では「ホームカミングデー」という日を設けています。これは短大の文化祭当日に、社会人として半年を過ごした卒業生が来校し、近況報告や今の仕事のやりがいについて話すイベントなのです。と、同時に、卒業生が社会人として上手くやれているかどうかフォローアップする場でもあります。現コミの卒業生の就職先は一般企業で業界も多様なため、話を聞くことですべての要望には適えられない場合もあるかも知れませんが、幼児教育については本学に専門家が揃っていますから、事例に沿って、より具体的なアドバイスができます。悩みを抱えていた卒業生もアドバイスをもらい、新しいイメージを持って現場に戻れているようです。保育園や幼稚園はとくに年間行事で動いていますから、半年で見切りをつけるのは本当に残念なのです。せめて1年続けて年間のイメージが出来上がると、楽になって続けられるケースが少なくありません。今後もこの「ホームカミングデー」のような機会を通じて卒業後の学生も支えることができればと思います。
短大生は1年生がすごく大事、
就活にも影響
短大生は就活までの時間が短いので、それまでに少しでも強みになるような武器を持って欲しいと思い、本学では資格取得を推奨しています。授業の中で資格を目指したバックアップをし、奨励金制度もあります。4年制大学へ編入するにしても、3年生からは勉強が大変になるので短大に在籍しているうちに資格取得しておくことをおすすめします。実は短大生は1年生がすごく大事なのです。資格のための勉強もそうですが、出席率や成績に関しても、最初の1年間に頑張る習慣ができると2年生になってからの生活がずっと楽になり、そのままいい形で就活に入れます。本学は常勤ではない教員も入学時から一人ひとりを気にかけて指導する、学生にとっては恵まれた環境なので、1年生からいい習慣をつけやすいのではないでしょうか。
就活する学生を見ていてつくづく思うのは、「ゼロの状態から1へ持って行くのがいかに重要であるか」ということです。なかなか就活が思うように進まない子も一つ内定をもらうことで、「人はこれほど変わるのか」と、周囲を驚かせるほど自信をつけて、さらに挑戦を続けるようになります。この最初の「1」が難しいのです。卒業後に自分一人で就活をしてゼロから1を目指すのはとても大変なことです。学生の皆さんは、サポート態勢が整っている在学中に、ぜひ1にする努力をしてください。そしてお給料をもらう嬉しさを知っていただきたいと思います。お給料は、アルバイトとは違って、会社に選ばれて「責任の伴う」仕事をした報酬です。この経験があると、例え最初の会社で上手くいかなかったとしても「働き続けよう」と思えるでしょう。
Copyright © Mynavi Corporation